契約書作成の重要ポイント7選!必要事項や契約の種類、注意点を解説
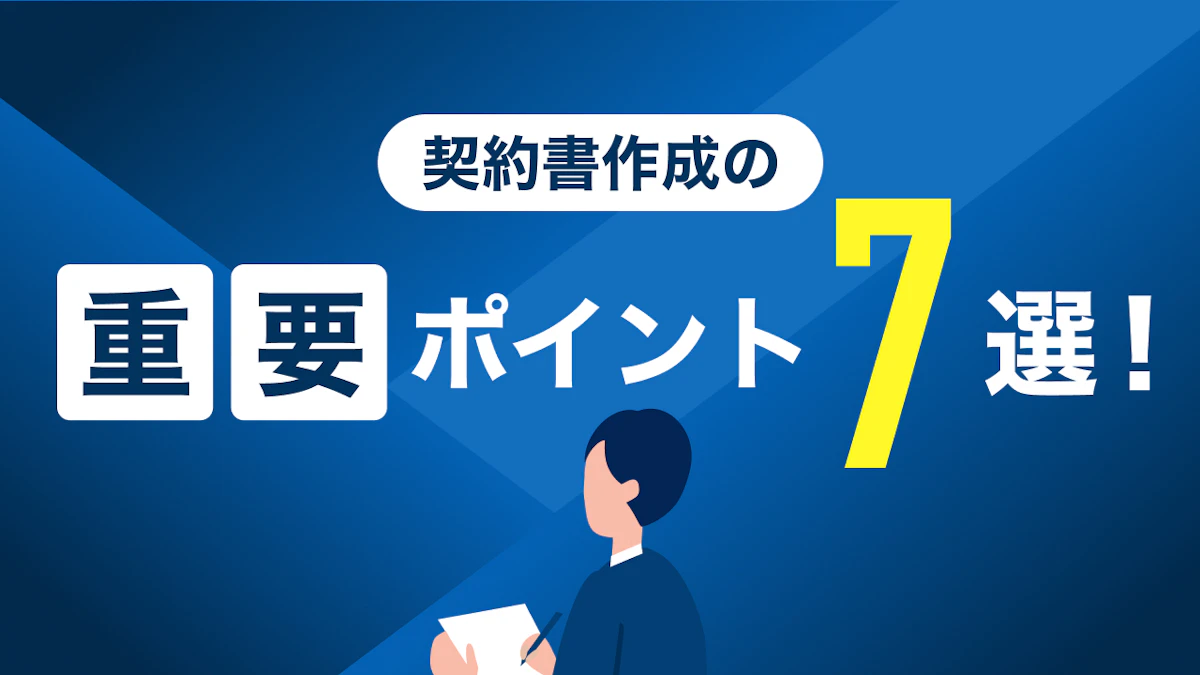
契約書は何だか難しい表現が多く、苦手意識をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ただ、契約書は相手との権利義務関係を決めるものであり、時にこちらが主張したいことを伝えるツールにもなります。
ここでは、契約書が重要な理由を説明し、作成上のポイントを説明していきます。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書とは
.jpg)
契約書とは、当事者が合意内容をまとめ、書面にしたものです。
本来契約は、口頭でも成立することがほとんどで、書面が要求されている契約類型はごくわずかです。ただ、口約束だけだと、そもそも合意内容が特定できない、違反があった場合の対処が難しくなる、といった問題が多いです。そこで、特に企業間や重要な契約においては、書面に落とし込んで内容を特定し、万が一に備えます。
こうして作られる書面が、契約書です。
契約書が重要な理由
以上のような契約書が重要な理由をまとめると、以下のように整理できます。
① 合意内容を特定するため
②ー1 紛争になった場合に、協議で解決するための足がかりにするため
②ー2 紛争になった場合に、訴訟で解決するための足がかりにするため
以下、それぞれ説明していきます。
合意があったこととその内容をはっきりさせるため
まず、契約書があれば、契約の相手方と合意をしたことが明らかになり、その合意内容もはっきりします。ちゃんと合意できたのか、合意できたとしてその内容・範囲はどのようなものだったかが、契約書をみれば分かります。
契約書がないと、言った言わないになることが容易に予想できます。この水掛け論は、特に
紛争になった場合に現実化します(後述)。
紛争になった場合、協議で解決するため
契約書の中には、トラブルがあった場合にどのようなルールで解決するかを盛り込むことがほとんどです。
契約関係から解放するか(解除条項)、お金で解決するか(損害賠償条項)などのルールを条項化しておけば、万が一トラブルが生じたとしても、契約書に基づいて対応することが可能です。
トラブルになってしまうと、お互いに引けなくなり、より水掛け論になることが容易に想像できます。契約書には、万が一に備えるという機能があります。
紛争になった場合、訴訟で解決するため
さらに、協議で解決できなかった場合、訴訟を利用することができます。
原則として訴えた側(原告)が立証する必要があるという点に注意が必要です。つまり、トラブルを起こした側ではなく、被害者側、つまりトラブルを起こされた側で立証する必要が出てくる場合が多いです。
契約書があれば、合意があったこと、合意の内容、守られなかった場合のペナルティーが盛り込まれていますから、訴訟でも契約書を足がかりにすることができます。
契約書の種類
.jpg)
以上が、契約書の作り方の分類です。次に、契約書の中身での分類をご説明します。
実務上よく出てくる、売買契約書、秘密保持契約書(NDA)、業務委託契約書についてそれぞれ説明します。
売買契約書
先に述べたように、コンビニでの売買といった日常的な売買では売買契約書は作られないでしょう。
主なターゲットは大きな買い物、例えば不動産売買契約書などです。企業間での取引についても、売買契約書が作られる傾向にあります。
みなさんが日常的にみる売買契約書としては、ネット注文の場合の発注(メール)とその承諾メール、納品書などの一連のものでしょう。「売買契約書」というタイトルの一枚紙ではないですが、発注から納品書まで一連のものが売買契約を形作ります。
秘密保持契約書
主に企業間において、取引関係に入る前あるいは入ると同時に、お互いの情報のやりとりについて定める契約書です。
秘密情報の範囲(定義)をどうするか、受領者側の義務をどうするか、有効期間をどうするかなどのポイントがあります。
近時の企業間取引は、その前提として秘密保持契約書を作成していることがほとんどです。
業務委託契約書
自分の業務の全部または一部について、第三者にお願いする時に作る契約書です。
典型的な契約(売買、賃貸借など)に当てはまらない契約のほとんどが業務委託契約で処理されている印象です。
雇用契約に近いもの(フリーランス契約など)から請負・委任契約に近いもの(製造委託契約、開発契約、コンサルティング契約など)まで、多様なものが含まれます。
契約書作成の重要な7つのポイント
次に、実際に契約書を作っていく上で重要なポイントをいくつか説明します。
①契約の目的を過不足ないものにする
契約の冒頭に契約の目的を記載することが増えました。
契約の目的自体は権利義務を規定するものではないので軽視されがちですが、契約に疑義が生じた場合に契約の目的条項から考える場合があります。
したがいまして、契約の目的に過不足がないかをよく考えて作成する必要があります。
また、冒頭に持ってくることが多いことから、各種文言の定義規定が含まれることがあります。後の条項と矛盾がないようにしておくことも重要です。
②権利と義務について明記する
契約書の核となる条項です。
通常は双務契約といって、権利と義務が対になっています。業務を委託する者がいれば受託する者もいて、報酬を支払う義務がある者がいれば受け取る権利のある者がいます。
権利または義務として一義的に分かることが重要です。不明確な記載は極力避けましょう。
代金の支払いであれば、金額、支払い時期、支払い方法、振り込む場合の振込手数料の処理など、誰がみても間違いないことが重要です。
③法定記載事項を落とさないようにする
例えばクーリングオフの法定書面や雇用契約書、フリーランス契約書などでは、法律上契約書に盛り込んでおく事項が決まっています。
この事項を書き落とすと、予定した効果が得られないばかりか、契約の全部又は一部が無効になるおそれも出てきます。
関係省庁が出しているモデル契約書なども参考にしながら、法定記載事項は確実に入れましょう。
④契約当事者でなくても分かる記載にする
契約書が重要な理由として、紛争になった場合に備えることを挙げました。
例えば当事者間では当然の前提になっている事項でも、社会一般では当然とはいえない場合には、その事項も契約書に盛り込んでおくことが重要です。紛争になった場合、契約書に記載のない事項は社会常識で判断されることになってしまうからです。
契約当事者でなくても契約書をみれば解釈できるような記載にしておくことが重要です。
⑤③や④を満たすために、業界に関連する法律・裁判例・商慣習は調査しておく
以上のように、契約書は法律(法律の解釈が問題になる場合には裁判例、法律がない場合には商慣習)によって規定されます。法定記載事項を網羅するには、法律などを調べておく必要があります。
商慣習を調べておくのは、契約当事者だけの「常識」になっていないかを考える上でも重要です。商慣習は、案外裁判では考慮してもらえない(立証が難しい)ことが多いです。「この業界なら当然」と思われることでも、それを商慣習と理解し、契約書に明記しておくことが重要です。
⑥契約書に記載されたものは合意したものとみなされてしまう
契約書は、当事者の完全な合意が落とし込まれています。食い違う点があれば、双方議論し、修正をするべきです。
逆にいえば、契約書に書いてある事項は、原則としてすべて当事者が納得したものとみなされます。消費者契約法などの関係で一部扱いが異なる場合がありますが、基本的には完全に合意したものとみなされるとお考えください。
つまり、納得していなかったけれど署名をすれば、それは納得したものとなってしまうわけです。修正が必要な点があれば、修正を求め、場合によっては契約しないことも大事です。
⑦類似の契約書に頼りすぎない
事業を続けていると、同じような契約書を作成することが増え、安易に流用しがちです。ただ、契約書は(特に契約当事者が異なれば)個性があり、同じ合意内容になることは非常にまれなはずです。
類似の契約書は要素の確認に留め、内容は毎回練り直すのがよいでしょう。
同様に、ネット上にある「ひな型」と称されるものは、取引を深く理解していないと実態に合わないものができてしまいます。ひな型を使ったと思われる契約書で、当該取引に必要な条項がなくかえって適用関係の分からない条項ばかりであることもあり、これでは結局契約書がないようなものになってしまいます。
契約書の記載事項
.jpg)
契約書作成の注意点を挙げてきましたが、実際に契約書にはどのような項目を書けばよいでしょうか。形式として決まりがあるわけではありませんが、よくある契約書の記載事項をそれぞれ説明していきます。
タイトル
必須ではありませんが、通常契約書にはタイトルを付けます。特定しやすくなりますし、管理もしやすくなります。他の契約書の中で言及する場合にも役立ちます。
特に基本契約であれば、タイトルにも基本契約書と付けると分かりやすいです。
なお、契約書とせず、覚書などとしても、法的な効力が変わるわけではありません。
前文
タイトルと条項の間に、前文を入れることが多いです。甲乙を間違えないようにしましょう。
参考条項例
〇〇(以下「甲」という。)及び〇〇(以下「乙」という。)の間で、本日、〇〇に関して以下のとおり契約する。
主要条項
契約書の中で最も重要な条項です。
なお、基本的な権利義務を定める前(通常は第1条)に、契約の目的を定める条項を入れることが増えてきました。これは、契約に疑義が生じたときに参考になるものであり、レビューの際に読み飛ばしてしまいがちですが、かなり重要な条項です。
参考条項例
甲は、乙に対し、次条で定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
権利義務の譲渡禁止
主要条項で定めた関係は、通常お互いを信頼して決めたものであり、勝手に第三者が入り込むのは困るはずです。そこで、多くの契約書では、契約書上の権利義務を原則移転させないことを約束します。
参考条項例
当事者は、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与又は担保の目的に供してはならない。
契約解除事由
当事者は契約に縛られるわけですが、事情の変更などで契約関係から解放してほしいと考えることがあります。典型的には相手が約束を守らないときです。
参考条項例
当事者は、相手方に次の各号のいずれか1つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく/催告の上、本契約を解除することができる。
・相手方が本契約上の義務を履行しないとき(以下略)
損害賠償
契約関係から解放されると共に、あるいは解放されなくても、損害を受けた場合は相手方に賠償を求めたいときが出てきます。
どこまでの損害を賠償するかを決める必要があります。
参考条項例
当事者は、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、相手方の受けた損害(弁護士費用を含むがこれに限られない/〇〇に限る)を賠償しなければならない。
反社会的勢力の排除
いわゆる反社条項(暴排条項)です。よほど古い契約や双方が見知っているような関係であれば別ですが、基本的に全ての契約書に入っています。
参考条項例
当事者は、相手方に対し、現在及び将来において、自己又は自己の関係会社、及びその代表者又は役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
・暴力団(以下略)
契約期間
契約がどの程度続くものなのかを明記します。更新が予想される場合などはもちろん、多くの契約書では自動更新条項を入れておくことが一般的です。
参考条項例
本契約の有効期間は、本契約締結日から起算して〇年間とする。ただし、期間満了の〇か月前に、当事者から書面による申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。
合意管轄
裁判になるとき、どこの裁判所で行うかを「管轄」といいます。
この管轄は、法律で特別な決まりがあるほかは、原則として相手方の住所に近い裁判所で行います。
ただ、種々の事情で裁判所を決めておきたい場合があります。そのときは、裁判を行う裁判所を合意しておきます。
参考条項例
当事者は、本契約に関し紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
協議条項
契約書に全ての場合を盛り込むことは不可能なので、何かしら疑義が生じた場合には誠実に協議する旨定めておくことがほとんどです。
参考条項例
当事者は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し疑義が生じた場合には、誠実に協議することを約束する。
後文
最後に、契約書に定型文言を入れます。
紙を2通作ることが多かったですが、近年では電子契約も増えてきました。電子契約の場合は基本的に電子データを原本としますので、書き方が変わります。
参考条項例
(紙の場合)本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がこれに署名捺印の上、各自1通ずつを保有する。
(電子契約の場合)本契約の成立を証するため、本電子契約書ファイルを作成し、甲及び乙が電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。(なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。)
日付欄と署名欄
契約した日付と、それぞれの署名捺印(あるいは記名捺印)の欄を設けます。
日付は忘れがち(空欄のまま保管しがち)ですので、確実に入れるようにしてください。契約の特定にもなります。
ハンコは三文判で問題ないことが多いですが、不動産登記関係のものなど実印が要求されることもあります。
契約書作成の流れとは
こうして内容が固まった契約書を形に落とし込んでいきます。ここでは紙の場合を念頭に置いて説明します。
①作成・製本する
フォーマットは原則として決まりがありません。横書きが主流ですが、縦書きで書いても間違いではないです。大きさや段組みも原則自由です。
複数ページにわたる場合には製本をしますが、あとで差し替えられてしまうことを防止するために、ステープルで留めた上で契印か、製本テープを用いることが主流です。
②署名・押印・割印
署名は自署に限らず、ゴム印や印字(記名)の場合もあります。それぞれ効果に違いがあるわけではないですが、一般的に自署の方が後に効力を争われにくいとは言えるでしょう。
先ほどの後文のように、2通作りそれぞれ持ち合うことが多いですが、その2通が確かにペアであることを示すため、割印をすることがあります。割印をしなくても契約書の効力に変わりはありませんが、しておいた方が丁寧な場合があります。
③課税文書には収入印紙を
収入印紙を貼る必要のある文書を、課税文書と呼んでいます。
課税文書に当たる場合(企業間の契約書はだいたい課税文書だろうと思います)、収入印紙を貼ります。契約書に記載された契約金額などによって印紙額は変わります。
収入印紙がないと直ちに契約が無効になるわけではありません。収入印紙があったほうが、多少真実らしいとは言えます。
契約書作成の注意点
以上、契約書の内容や作り方についてみてきました。以下では、実務上契約書に触れるとよくみる問題について、4つの注意点を説明します。
①保存管理方法を決めておく
特に企業の場合は、契約書の紛失は企業の信用にも関わることです。ただ、紛失は案外よくみられることです。
文書保管規程などを策定し、契約書などを体系的に保存しておく体制を構築しておくことが重要です。契約書の種類によっては、法定保存期間が定められているものもあります。
近年では電帳法の適用もあり得ますので、保存管理方法は今一度チェックしておくべきでしょう。
②契約する権限のある者が署名する
見落とされがちなのが、契約当事者を誰にするかという視点です。
当然ながら「契約する権限のある者」がサインすべきなのですが、意外にアバウトな契約書が多いです。
例えば以下のような場合に注意が必要です。
・会社が契約主体の場合
基本的に代表権のある取締役がサインする必要があります。
・未成年などが契約当事者になる場合
未成年者など、法律上契約する権限が制限されている場合があります。その場合、例えば未成年であれば親権者のサインが必要になります。
③自分が原本を保管しておくべきなのかどうかを把握する
前述のとおり、当事者1通ずつ原本を保管することが原則です。
ただ、電子契約の場合は電子ファイルが原本となり、印字したものは写しになります。
紙であっても、原本は当事者の誰かが保管し、他の当事者は写しを保管する場合もあります。「契約書原本を紛失した」と思ったら「そもそも原本をもらっていなかった」などということもあります。
自分は原本なのか写しなのかというのを意識し、後文に原本保管となっていたら確実に原本を受け取ることを忘れないようにしてください。
④書き換えられるリスクを念頭に置きながら作成する
契約書は契約内容を落とし込んだものであり、主に紛争になった後に登場します。つまり、偽造や書き換えなどをされてしまうこともリスクとして考えておく必要があります。訂正を訂正印で済ませるかといったことから始まり、複数ページなら契印、複数原本なら割印など、契約書の形式に関する実務は長年の知恵の結晶ともいえます。取引の実態や相手方との関係に合わせ、紛争になったときのリスクを考えながら形式面を決めていく必要があります。
契約書は誰が作成するべきなのか
以上、契約書の注意点を述べてきました。最後に、「実際に作るのは誰が良いのか」という視点でご説明します。
過去の経験を活かしひな型を作っておく
契約実務で実は一番重要なのが、「自分のこれまでの取引」です。「うまく行った経験」もあれば、「うまく行かなかった経験」もあるはずです。
こうした良い取引で使った契約書は活かし、うまく行かなかった契約書は修正していくというのは非常に重要です。
巷のひな型は、あなたのビジネスに必ずしもフィットしません。自身の行ってきた取引を通じてトライ&エラーした契約書が、一番フィットするはずです。
つまり、できれば「契約書は自分で作る」という方がメリットは大きいことになります。
相手が作ってきたものにリスクがある
他方で、相手が契約書を作ってくることもあります。楽はできますが、その分リスクもあるわけです。
相手の契約書をみる上でのチェックポイントは以下のとおりです。
・過去にも取引がある場合には、過去の契約書との相違をみる
・自身のひな型との相違をみる
・近時の法改正と照らし合わせる
相手の契約書にはリスクが潜んでいると考えてチェックすることが肝要です。
契約書チェックの“見落としリスク”をAIでゼロに
LAWGUEなら、相手の契約書もAIが自動で分析。
自社基準に照らして危険な条項や表記ゆれを自動検知し、確認漏れを防ぎます。
法務部門のレビュー時間を最大50%削減し、判断の質を落とさず効率化。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
以上、契約書の重要性や項目を説明し、さらに作成上の注意点についても述べてきました。
特に、「自身のひな型を作っておく」という視点は重要です。最初に私が述べた「自分の言いたいことを伝えるツール」として契約書を使う際には、自分で理解して作ってきたものが一番役に立ちます。
私の述べた内容が、お手元の契約書のブラッシュアップに少しでも役に立てば幸いです。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








