【規程作成】失敗しない社内規程の作り方と3つのステップを徹底解説!
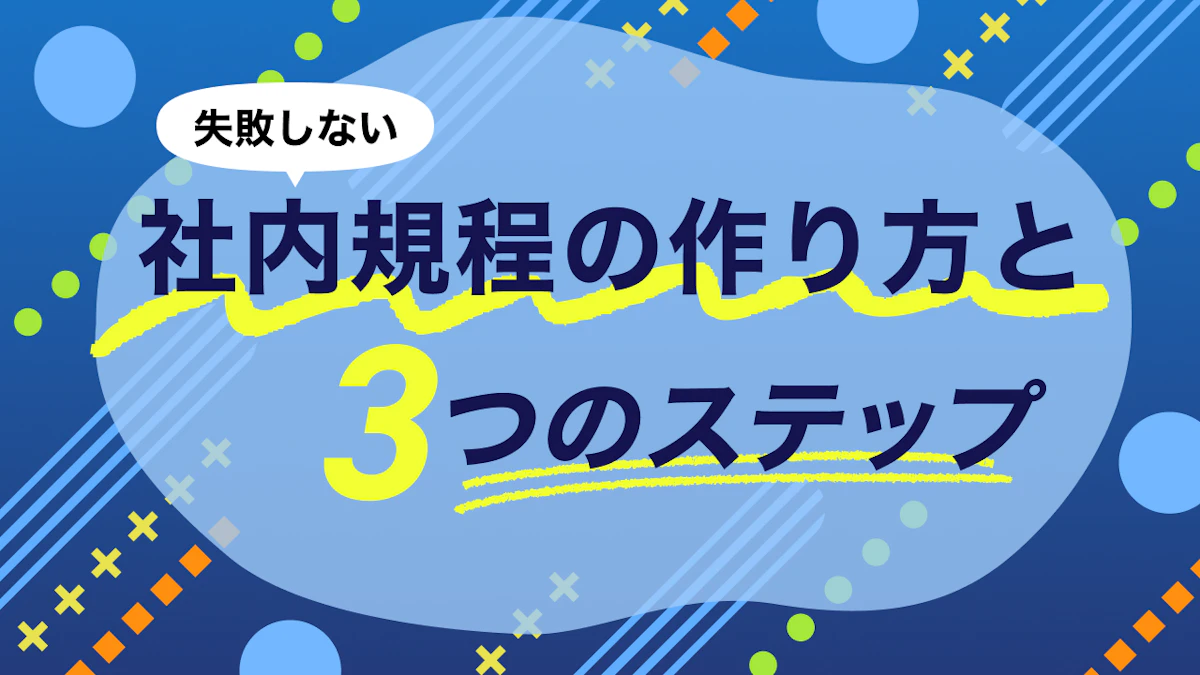
「社内規程」は企業活動に欠かせませんが、いざ作成しようとすると「どこから手をつければいいのか分からない」「法的に問題がないか不安」という悩みを抱える担当者も少なくありません。
この記事では、社内規程と就業規則の違い、社内規程の基本から作成の手順、注意すべきポイントまでを解説します。また、失敗しないためのコツもお伝えします。
【参考】規程管理ツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉規程修正における新旧対照表を簡単に作成
👉ひな形を使って新しい社内規程を簡単作成
👉条番号の修正もれを自動体裁補正で防ぐ
社内規程とは?知っておくべき基礎とポイント

社内規程とは、企業内での行動基準や業務運用のルールを定めた文書です。就業時間・休暇制度・出張旅費の精算方法など、従業員が守るべきルールが記載されています。
「社内規程」と「就業規則」は混同されがちですが、一般的に「社内規程」は法律で義務付けられているものではなく、企業が自主的に策定するルールを指します。
一方、「就業規則」は雇用契約の内容である労働条件に関する基本的事項を明記するものです。いずれも、社内統制とコンプライアンスの土台として、企業にとって不可欠な存在です。
社内規程と就業規則の違いは何か?
社内規程と就業規則は似たような文書に見えますが、法的な意味合いと運用上の位置づけにおいて明確な違いがあります。
就業規則は労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を雇用する企業に作成・届出が義務付けられています。
一方、社内規程は就業規則のような法律で義務付けられているものだけではなく、企業が自主的に整備するルールを含む広い概念です。
また、就業規則は労働条件に関する基本的事項(給与、労働時間、休日など)を明記しなければならず、違反すれば労基署から是正指導を受ける可能性があります。
一方、社内規程は例えば「出張旅費規程」「SNS利用ガイドライン」「AIツール利用規程」など、業務の効率化や明確なガイドラインの提供を目的としています。
つまり、就業規則は法律に準拠した労働契約の一部として機能し、社内規程は社内の業務運用のルールを整備する役割をはたしています。
なぜ今、社内規程が重要なのか
現代の企業経営において、社内規程の整備はますます重要性を増しています。その背景には、働き方改革・テレワーク・副業解禁など、労働環境の多様化があります。従来の慣習では対応しきれない新しい状況が次々と生じる中、明確なルール作りが求められているのです。
また、コンプライアンス・ハラスメント対策・内部通報制度など、企業の社会的責任(CSR)を果たすためにも、規程整備は欠かせません。規程が未整備な場合、従業員による不正行為やトラブルへの対応が後手に回り、企業の信用が失墜する恐れもあります。
逆に、社内規程を整備することで、従業員は自らの行動基準を理解でき、企業としても適切なマネジメントが実現可能になります。
法的効力をもつ規程とそうでない規程
すべての社内規程が法的効力をもつわけではありません。たとえば、就業規則や給与規程など、労働条件に関わる規程は労働契約として法的効力があります。このため、従業員とのトラブル発生時に法的根拠として用いることが可能です。
一方で、「SNS利用ガイドライン」や「AIツール利用規程」など内部の管理基準や便宜的な取扱いに関する規程は、あくまで社内運用ルールにとどまり、外部に対する法的効力は限定的です。
とはいえ、これらの規程が明確に定められていない場合、運用に差が生じたり、不公平感が問題化したりする可能性があります。そのため、法的効力の有無にかかわらず、実務上の影響を踏まえて丁寧に整備すべきです。
規程作成の“手戻り”を減らす!
LAWGUEなら、規程ひな形・過去の改定文書・関連資料を横断検索しながらドラフト作成を進められ、抜け漏れや表現ゆれを押さえた規程整備を効率化。差分比較・版管理で「どこを、いつ、なぜ直したか」を追えるため、改定履歴が残らず運用が属人化する問題を防止。
👉 3分でわかる資料を見る
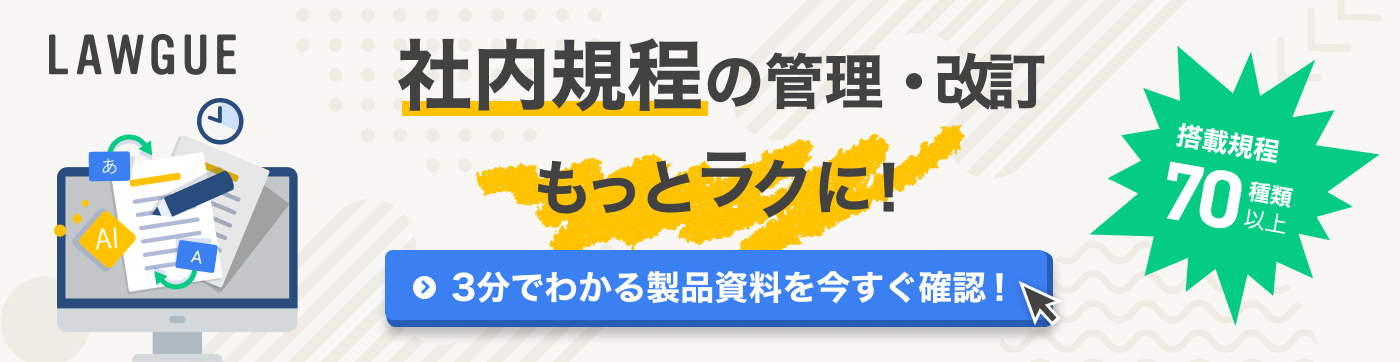
社内規程の主な種類
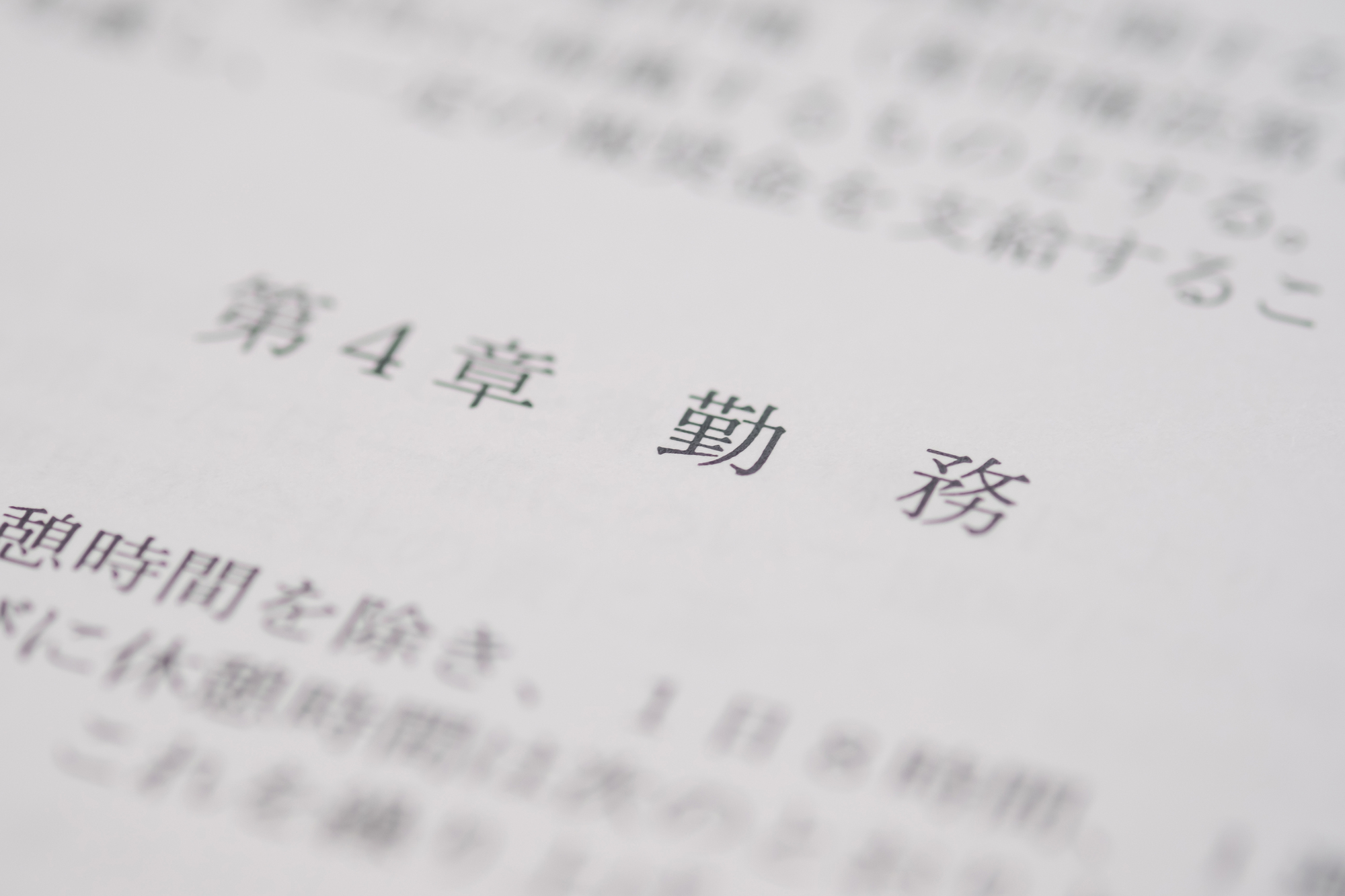
社内規程にはさまざまな種類があり、会社の経営方針・業種・規模に応じて内容は多岐にわたります。大きく分けると、以下のような分類が可能です。
- 経営
- 会社運営にかかわる規程
- 人事労務に関する規程
- 安全衛生
- 情報管理に関する規程
- 最新のビジネス環境に対応した規程(例:テレワーク)
中小企業では必要最小限にとどめる場合もありますが、規模が大きくなるほど、より詳細で専門的な規程の整備が求められます。
基本経営・会社運営にかかわる規程
企業の組織運営を円滑に行うための基盤となる規程です。主な例としては以下のものがあります。
- 定款
会社の根本規則であり、設立時に必須となる法的文書 - 取締役会規程
取締役会の構成・開催・決議方法などを定めたもの - 職務権限規程
役職ごとの決裁権限や業務範囲を明文化したもの
これらはガバナンスの強化・意思決定の迅速化・責任所在の明確化に役立ちます。特にIPOを目指す企業では、内部統制の観点から整備が必須です。
人事・労務に関する規程
人事・労務に関する内容は、最も一般的かつ重要なカテゴリです。以下のような規程が含まれます。
- 就業規則
労働基準法に基づき作成される基本的な規則 - 給与規程
基本給・諸手当・賞与・昇給などの制度設計を明記したもの - 退職金規程
退職給付の算定方法や支給条件などを定めたもの
これらの規程は、労働条件の明示義務(労働契約法)との関係で法的効力が強く、行政指導の対象となることもあります。
また、育児介護休業・メンタルヘルス・パワハラ防止など、新しい法制度に対応するための追加規程も必要となる場面が増えています。コンプライアンスを徹底する意味でも、人事系の規程整備は最優先事項と言えるでしょう。
最近注目されている新しい規程の種類
近年、社会・技術の変化により、下記のような新たな種類の社内規程が注目を集めています。
- テレワーク規程
在宅勤務の対象範囲・通信費補助・労働時間の管理方法などを定めたもの - 副業規程
許可制・届出制、副業による競業・秘密保持リスクへの対応を定めたもの - DX推進規程
クラウド活用やAI導入に関する社内ルールを明文化したもの
これらは従来の制度ではカバーできない新しい働き方や経営方針を支える重要な規程であり、制度の整備が従業員の安心感にもつながります。
規程作成の“手戻り”を減らす!
LAWGUEなら、規程ひな形・過去の改定文書・関連資料を横断検索しながらドラフト作成を進められ、抜け漏れや表現ゆれを押さえた規程整備を効率化。差分比較・版管理で「どこを、いつ、なぜ直したか」を追えるため、改定履歴が残らず運用が属人化する問題を防止。
👉3分でわかる資料を見る
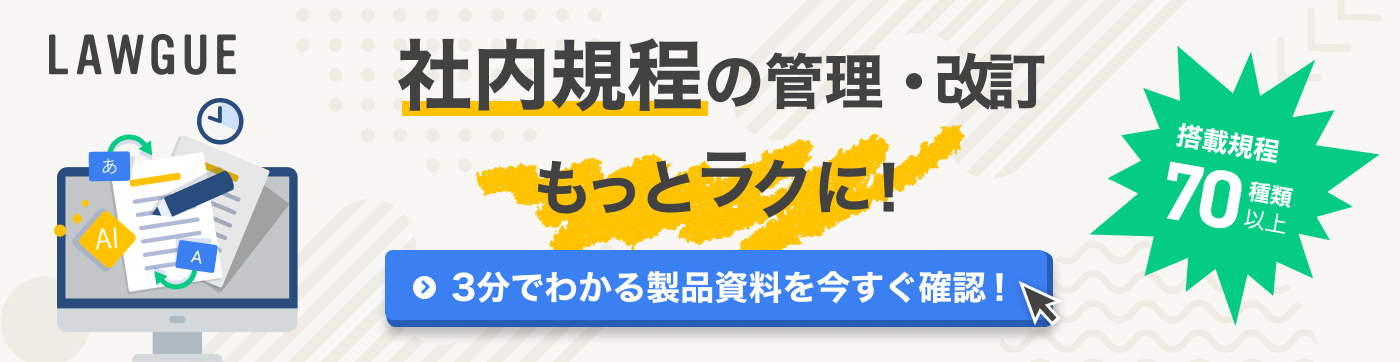
社内規程作成の3つのステップ

社内規程の作成は、単にテンプレートを流用するだけではなく、自社の現状に即した設計が不可欠です。以下の3つのステップに沿って進めることで、実効性のある規程を整備できます。
- 現状分析と目的の明確化
- わかりやすい草案の作成
- 専門家によるチェックと周知の徹底
各ステップには重要な意味があり、順を追って丁寧に取り組むことが成功の鍵です。
STEP1:現状分析と目的の明確化
まずは、自社の現状を正確に把握するところから始めます。これを怠ると、現場で機能しない机上の空論になりかねません。以下のような観点から、実務の実態を整理しましょう。
- 業務フローに抜けや曖昧さがないか
- トラブルや相談が多い領域はどこか
- 他部署や従業員間で対応に差異はないか
現場ヒアリングを通じて「規程があれば防げた混乱」や「判断が属人的になっている業務」などを洗い出すことが、実態に即した規程作成の第一歩です。
分析手法としては、業務プロセスの棚卸しやRACIマトリクスの整理、ヒヤリ・ハット事例の収集といった方法が有効です。どこにルールを整備すべきか、なんのために規程を作成するのかという目的を明確にしましょう。
STEP2:わかりやすい草案の作成方法
社内規程の草案は、読み手にとって「理解しやすいこと」が最も重要です。どれだけ制度として優れていても、難解な文章や抽象的な表現では、現場で正しく運用されません。法律文書のような形式にこだわりすぎず、平易な日本語で記載しましょう。
作成のポイント
- 見出しを設けて構造を明確にする
例:「第3章:出張」など、章立てで全体像を把握しやすくする。 - 定義は冒頭で明示する
例:「出張とは、通常の勤務地を離れて業務を行うことをいう」 - 曖昧表現や二重否定は避ける
✕:「出張を行わない場合には精算は必要ではない」
〇:「出張を行わない場合は精算は不要」 - 数値情報や条件は表・箇条書きで整理する
金額・日数・例外条件などを整理しておくことで、視覚的に理解しやすくなり、誤解やトラブルを防止できます。 - 「想定Q&A」や「過去の相談事例」を盛り込む
実際に起こりがちな誤解や判断に迷うケースを事前に盛り込むことで、現場での理解・定着が進みます。
また、主語や責任主体が不明確な文章は混乱を招くため、「誰が」「何をするか」を明記するよう心がけましょう。文章作成の際には、社内の実務担当者や利用者の目線を持つことが、分かりやすさと実用性の両立につながります。
STEP3:専門家によるチェックと周知方法
社内規程の草案が完成したら、法務の専門家によるチェックが不可欠です。特に、就業規則・労働時間・休暇・懲戒など労働条件にかかわる規程は、労働基準法や判例との整合性を確保しなければ、無効やトラブルの原因になるおそれがあります。弁護士や社会保険労務士など、該当分野に精通した専門家に確認を依頼しましょう。
その上で、従業員への周知徹底も非常に重要です。制度を策定しても、周知されていなければ意味がありません。以下のような工夫を通じて、内容の理解を深めましょう。
- 社内研修や朝礼を通じて直接説明する
- チャットツールやメールでQ&A形式の案内を配信する
- クイズやアンケート形式での理解度チェックを実施する
- ポスターやイントラ掲示など視覚的な啓発ツールを活用する
こうした多面的なアプローチによって、従業員の関心と理解を引き出し、実務に役立つ規程を作成・運用することができます。
最終的には、現場で自然に運用される状態を目指すのが理想です。
規程作成で押さえるべき注意点

社内規程を作成する際には、形式や内容だけでなく、運用面や法令との整合性にも細心の注意を払う必要があります。
以下の4点は、特に見落とされがちな注意点です。
- 法令違反を防ぐ確認体制の構築
- 規程同士の整合性の確保
- 実態と合致した運用設計
- 定期的な見直しと更新の仕組み
これらを意識することで、形だけで終わらない、機能する規程の整備が実現できます。
法令違反を防ぐための確認事項
規程が労働基準法や個人情報保護法などの法令に違反していないかを確認することは、非常に重要です。以下のチェックポイントが役立ちます。
- 就業時間や休憩時間の規定は、労働基準法第32条などに準拠しているか
- 副業・兼業に関する制限は、不当に職業選択の自由を侵害していないか
- 個人情報を収集・利用する際の目的
- 範囲は明示されているか
特に、労働時間管理に関する規程は、近年の裁判例や厚生労働省の通達を踏まえた見直しが必要です。また、業界特有の規制(例:建設業における安全管理基準、医療業における倫理規範など)についても考慮しなければなりません。
万一、規程が法令に抵触していた場合、行政指導や損害賠償請求のリスクが生じます。必ず専門家によるリーガルチェックを受けましょう。
規程間の整合性を保つコツ
社内には複数の規程が存在するため、内容が矛盾しないよう整合性を保つことが求められます。そのためには、以下のような工夫が有効です。
- 規程一覧表を作成し、相互に参照してチェックする
- 用語を統一する(例:「従業員」か「社員」か)
- 上位文書→下位文書の順で整備する(例:就業規則→出張規程)
また、制度変更などの際は、該当するすべての規程への適用を意識する必要があります。例えば、在宅勤務制度を導入する場合、就業規則・勤務管理規程・セキュリティポリシーなど、複数の規程の修正が必要になることもあります。
実態に合った運用しやすい規程にするには
社内規程は、実際に職場で無理なく運用できる内容であることが何よりも重要です。どれほど良質な内容であっても、現場の実態とかけ離れていれば「あるけれど誰も読まないルール」になりかねません。
そのためには、作成段階から次のような工夫を取り入れることが有効です。
- 現場担当者や管理職へのヒアリングを通じて、実務上の課題や現状を把握する
- 実際の業務フローや判断基準を反映させ、具体的な行動に落とし込む
- 例外やイレギュラー対応に備えて、柔軟性のある表現を取り入れる
(例:「原則として〜とする。ただし、やむを得ない場合は上長の承認により〜できる」)
また、「すべてを禁止・制限する」ような過度に厳格な内容は、現場の反発を招きやすくなります。重要なのは、「守れるルール」「活用できる仕組み」であることです。制度と実務との乖離をなくし、従業員の納得感と利便性を両立することが、運用される規程をつくる鍵です。
定期的な見直しと更新の重要性
どれほど内容が充実した規程であっても、時代の変化・法改正・組織の再編などによって会社に合わなくなるリスクは常に存在します。規程は一度作って終わりではなく、継続的な見直しと更新が不可欠です。
推奨される見直しサイクルは、次のとおりです。
- 年1回の定期的なレビュー
(法改正、監査結果、業界動向などを踏まえて) - 重要制度の変更時の都度改訂
(例:人事制度改革、評価制度の刷新、ITツールの導入)
加えて、改訂を行った際には「変更履歴表」や「改定通知文」などを整備し、どこがどのように変更されたかを従業員に明確に伝えることが非常に重要です。これにより、従業員の混乱を防ぎ、変更後の規程がスムーズに浸透します。
まとめ
社内規程は、企業活動の秩序と効率性を保つための重要なインフラです。制度設計の段階から、実務との整合性、法令遵守、そして従業員への浸透までを意識して取り組むことで、形だけでなく「活きた規程」を整備することができます。
今回ご紹介した3つのステップと注意点を踏まえて、自社に最適な規程を作成・運用していきましょう。適切な支援を受けながら整備することで、トラブルの予防にもつながります。
よくある質問
会社の規定は誰が作る?
会社の規定(社内規程)は、一般的には人事部や総務部が主導して作成されますが、内容に応じて各部門の責任者や経営層が関与することもあります。
特に、就業規則や給与規程など労働条件に関する規程は、労働基準法に基づく届出や労働者代表の意見聴取が義務付けられているため、法務部門の関与・弁護士・社会保険労務士など外部専門家の助言を受けることが重要です。適切な手続きを経ることで、規程の有効性と信頼性が担保されます。
規定と規程はどう使い分ける?
「規定」と「規程」はいずれも「きてい」と読みますが、実務上は次のように使い分けられることが一般的です。
- 規程:制度や業務運用の全体的な枠組み(例:人事規程、出張規程)
- 規定:規程の中に含まれる、個別項目の具体的な取り決め(例:「◯◯は〜とする」)
ただし、法律上の厳密な定義の違いはなく、企業や業界によって表記や運用に差があるのが実情です。そのため、社内文書においては用語の使い分けや表記を統一し、混乱を避けることが望まれます。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。





