契約書での「甲乙」の使い方とは?意味やメリットをわかりやすく解説

「甲」「乙」と聞くと、契約書をイメージされる方が多いでしょう。
契約書に対する難解なイメージとあいまって、「甲」「乙」と聞くだけで何だか難しい印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、文章を短くし分かりやすくするためのものであり、難解にならないようにする工夫なのです。
この記事では、契約書における「甲」「乙」について、使い方なども含めて解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書での甲乙とは?

契約書における「甲」「乙」は、甲(こう)、乙(おつ)は、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)と順番に続いていきます。
古代中国の暦に使われていた十干(じっかん)の最初のほうにあるのが甲、乙です。漫画の「鬼滅の刃」の中でも階級で使われていました。
契約書において、契約当事者の1人目を「甲」と呼び、2人目を「乙」と呼ぶことが通例です。
数学で、「xとおく」「yとおく」などと書いたご記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。契約書では、xyではなく、甲乙とおいているのです。
甲乙丙、、、と続いていくということは、契約当事者として3人目が登場すれば「丙」、4人目が登場すれば「丁」となります。
契約書での甲乙の使い方
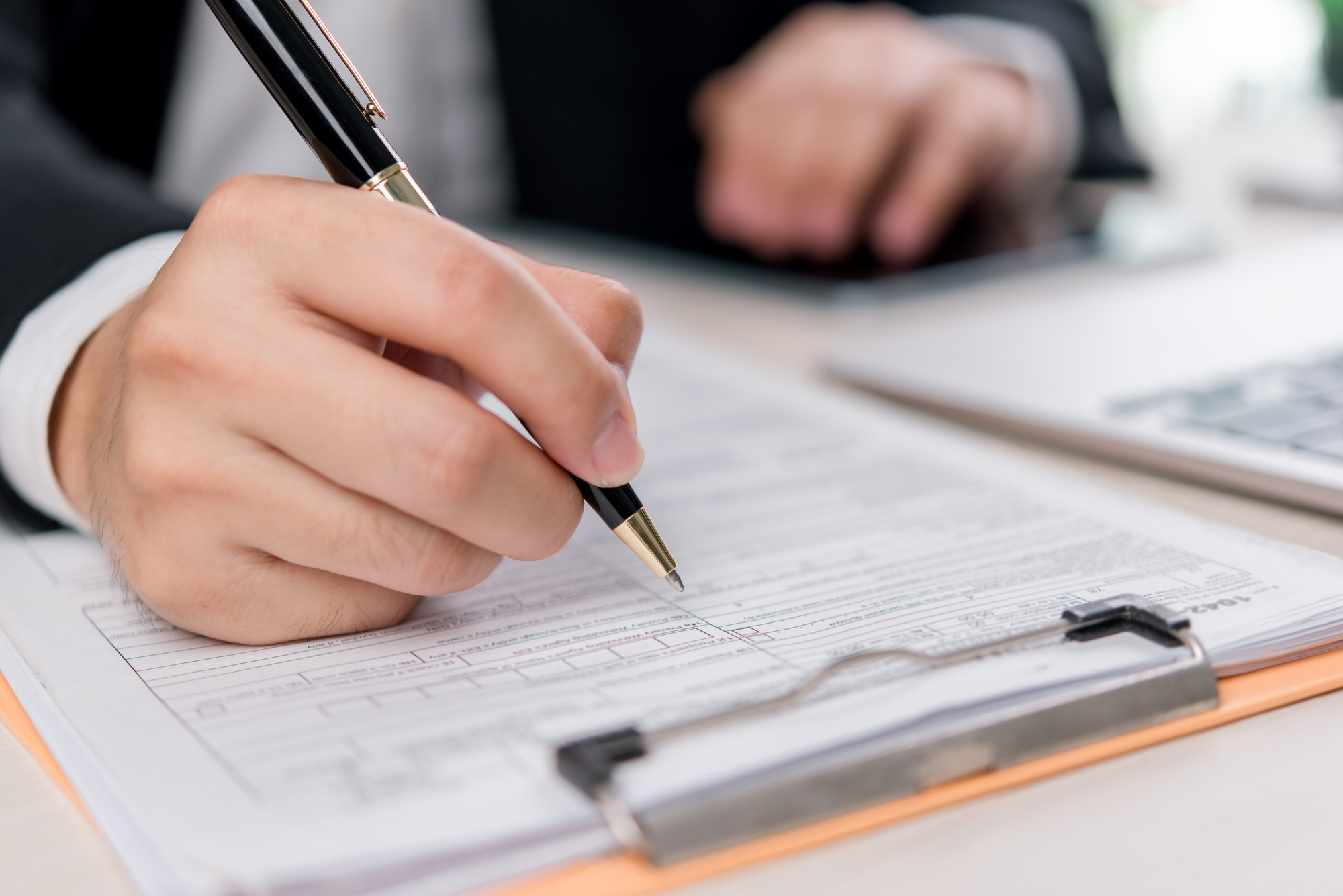
以上を整理すると、契約書で甲乙は、次のように使うことになります。
例えば、山田太郎さんが、自分の土地を、1,000万円で鈴木二郎さんに売った。
とします。すると、契約条項としては、
山田太郎は、山田太郎の所有する土地を、金1,000万円で鈴木二郎に売り渡し、鈴木二郎はこれを買い受けた。
となります。
ここで、山田太郎さんを甲、鈴木二郎さんを乙と置き換えると、
山田太郎(以下「甲」という。)は、甲の所有する土地を、金1,000万円で鈴木二郎(以下「乙」という。)に売り渡し、乙はこれを買い受けた。
となります。
甲乙は、同一人物がほかの条項に登場した際、契約当事者を置き換えて表現するときに使うのです。
前提として使い方に法律上の決まりはない
ほとんどすべての契約書では「甲」「乙」となっていますが、契約書で「甲」「乙」という書き方にしなければならないと法律で定められているわけではありません。
つまり、「A」「B」と書いてもよいですし、「山田太郎」「鈴木二郎」と省略しなくても問題ありません。
契約書において、当事者をどう表記するかの法律上の決まりはないのです。
ただ、日本では慣習上、「甲」「乙」(3人目以降は「丙」「丁」・・・)を使うことが圧倒的に多いです。
契約書は、法律上の権利義務を規定し、契約内容を言語化するものであり、いわば法律のプロ同士が作成し合うことが多いでしょう。
いわばプロの間で使われる共通言語が「甲」「乙」です。それ以外の呼称を使うのは間違いではないですが、読みにくいですし、相手に癖の強さを印象付けてもしまいます。
法律上の決まりはなくても、慣習上「甲」「乙」を使うものとお考えください。
甲を上、乙を下にすることが多い
それでは、契約当事者のうちどちらを甲に、どちらを乙にすればよいでしょうか。
これも、どちらを甲にすべきという順番に関する決まりがあるわけではありません。
ただ、先に述べたとおり、甲、乙、丙、、、が漫画の階級にも使われたと説明しました。慣例的に一番位の高い階級が甲、一番低い階級が癸とされ、甲>乙>丙・・・という感覚があります。
したがって、目上の者、立場の強い者が「甲」、目下の者、立場の弱い者が「乙」になることが多いでしょう。
企業間の取引をするとき、自社が「乙」になっていることが多いのではないでしょうか。これは、取引先を敬う、つまり「甲」にするため、自社はへりくだって「乙」にすることが多いからだと考えられます。どちらが作成したかによっても変わることがあります(作成した側がへりくだって乙にするなど)。
当事者が3人以上でも使用できる
契約当事者が3人いれば甲乙の次である「丙」、4人いればさらに「丁」を使います。
理論上は10番目まで行くことになりますが、実際には多くても5番目の「戊」くらいまでしか使われません。
これも慣習ですが、「丙」は、甲乙と比べると立場が一段下がる者や厳密な意味での契約当事者ではない者に使われることが多いです。
例えば甲が乙にお金を貸すとき、「丙」は連帯保証人になります。金銭消費貸借契約の直接の当事者は甲乙であるところ、保証人は厳密な意味での当事者ではないということで「丙」にすることが多いです。
他方、共犯者が2人いる場合など、立場が同じ人がいるときには、
被害者=甲
犯人1人目=乙1
犯人2人目=乙2
と並列関係がわかりやすくなるように記載することもあります。
契約書で甲乙を使う2つのメリット

契約書では甲乙を使うメリットとしては大きく分けて以下の2つあるとされています。
①文章を短くできる
②一般的であり読みやすい
それぞれ説明します。
①文章を短くできる
先ほどの例を再掲します。
山田太郎(以下「甲」という。)は、甲の所有する土地を、金1,000万円で鈴木二郎(以下「乙」という。)に売り渡し、乙はこれを買い受けた。
この後に、
乙は、甲に対し、前条の金員を、甲指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
と続きます。
これを甲乙と置き換えていなかったら、
佐藤二郎は、山田太郎に対し、前条の金員を、山田太郎指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は佐藤二郎の負担とする。
となり、冗長になります。甲乙と置き換えることは、数学で「X=ax+…」と置き換えているのと同じように、文章を短くし分かりやすくしているのです。
②一般的であり読みやすい
法律家としては、
乙は、甲に対し、前条の金員を、甲指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
と、
佐藤二郎は、山田太郎に対し、前条の金員を、山田太郎指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は佐藤二郎の負担とする。
であれば、圧倒的に前者ばかりを相手にします。振込手数料は振り込む側(今回は乙)が負担することが一般であり、振込みの主語と負担者が一致していることが一見して分かります。
他方で固有名詞が入っていると、見慣れておらずとても読みにくいです。
契約書で甲乙を使う2つのデメリット

契約書で甲乙を使うのは、よく契約書を取り扱っている者のためであるといってもよいかもしれません。
他方で、甲乙を使うデメリットもあります。メリットの裏返しで、逆に契約になじみのない方にとっては、使いにくさを覚えるでしょう。
大きく分けると、以下の2つのデメリットがあります。
①相手に分かりにくい場合がある
②主語を間違えるミスが多い
①相手に分かりにくい場合がある
まず、①相手への分かりにくさです。
例えば、危険負担と呼ばれる条項では、以下のようなものがよくみられます。
目的物の引渡し前に生じた目的物の滅失は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とし、目的物の引渡し後に生じた目的物の滅失は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とする。
要は、「目的物に何かあった場合、目的物を管理している者が責任を取る。例外的に相手が悪い場合にはその悪い人が責任を取る」という意味なのですが、契約書を見慣れていないと意味が取りにくいと感じるはずです。
条項が長くなればなるほど、また、契約書に普段から接していなければいないほど、甲乙とすることで余計分かりにくくなるというデメリットがあります。
②主語を間違えるミスが多い
さらに、甲乙がミスの原因になることがあります。実際に契約書を見慣れている者も見落とすことが多いので、①以上に一般的なデメリットかもしれません。
甲・乙と抽象化することで、主語を取り違えるミスが起きることがあります。
極端な例だと、
甲は、甲に売り渡す
のように、自分が自分に何かするような文章になってしまっていることすらあります。
このミスを防ぐには、次のことに気をつけましょう。
- 固有名詞にしておいて、変換機能を用いる
「山田太郎は~」、「鈴木二郎に対し~」と固有名詞で条項を作っておいて、最後に「山田太郎→甲」「鈴木二郎→乙」と変換すると、ミスはかなり減ります。
ただ、これでは甲・乙と書くメリット(短くなる)が作成中は活かされず、個人的には本末転倒な気がしています。
チェックのために甲だけを固有名詞に変換して頭から読んでみて、ミスを発見するといった手法を取ることがあります。 - 甲・乙ではなく特徴的な略語を用いる
甲・乙ではなく、例えば山田太郎を「売主」、鈴木二郎を「買主」という略語にすれば、ミスはかなり減ります。不動産売買契約書の場合は「売主」「買主」とすることがかなり多いので、読みやすさも保てます。
契約書で甲乙以外を使うケース
甲乙以外を使うケースもあります。ただ、どんな契約書にもオリジナルな略称を使うと、やはり読みにくくなります。
一般的に甲乙以外を使うことが多いケースをまとめておきます。
会社の略称を使用する
会社が複数登場する契約書などでは、「株式会社」を省略した略称を使うことがあります。
株式会社〇〇(以下「〇〇」という。)
などのようにです。
ただ、会社が2社しか登場しない場合などでは、やはり会社の略称ではなく甲乙が一般的でしょう。
よくみるのが、丙の立場の会社に対して、丙とせず略称を用いる場合です。
例えば、検査条項にしか出てこない検査機関が出てくる場合には、丙と定義するとかえってどこで定義したか分かりにくくなるので、上記のような略称を用いることが多いでしょう。
英文契約書では記号化しない
英文契約書では、Party A/Company A,Party B/Company Bといった表現もなくはないですが、日本の甲乙のように一般的ではありません。
海外の企業との取引は売買とライセンス契約が多いですが、売買であればSellerとPurchaserあるいはそのまま会社の略称を使うことが多く、ライセンス契約であれば、LicensorとLicenseeが多い印象です。
契約書の種類によって違う略称が使用されている
契約書の種類によっては、甲乙と同じくらい一般的な別の略称も存在します。
不動産売買契約書であれば、売主・買主とすることが相当数ありますし、賃貸借契約書などでは、貸主・借主とすることが相応にあります。請負契約書などでは、発注者・受注者とすることも少なくありません。
甲・乙を使うもともとのメリットは、文章を短くでき、一般的なので読みやすい点にあります。「売主・買主」「貸主・借主」のように、略称が短く、ある程度一般的に使用される略称であれば、甲・乙に代わって(あるいは甲・乙と同じくらい)広く使われている略称があるといえるでしょう。
さらに、NDAのように、どちらかが甲で乙であるということが重要ではなく、どちらも開示者になって受領者になるような類型の場合には、甲の権利・乙の義務という定めではなく、開示者の権利・受領者の義務という定めが必要です。
このような場合には、甲・乙を定義はしつつ、条項上で「開示者」「受領者」も定義し、甲・乙よりも開示者・受領者で条項を作っていくことになります。
契約書の定義漏れ・表記揺れを減らす
LAWGUEなら、契約書や覚書のひな形・過去文書・条文表現を横断的に確認できます。
甲乙丙の定義漏れや表記ゆれ、修正履歴の見落としを防ぎ、文書の整合性を保ちやすくなります。
法務だけでなく、営業・管理部門も同じ文書を参照でき、確認作業の属人化を防止。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
以上、今回は契約書における「甲乙」の解説をしてきました。
要点は以下のとおりです。
- 契約書の甲乙は、法律によって決まっているわけではない。慣例によるところが多い
- 甲乙を使うメリットは、文章を短くでき、一般的で読みやすくなる点
- 甲乙を使うデメリットは、読み手によっては読みにくくなり、主語の取り違えが増えてしまう点
- このデメリットを克服するために、甲乙以外の呼称を使うときもある
以下では、よくある質問について答えていきます。
よくある質問
契約書で甲と乙とは何ですか?
契約当事者の略称です。
一方当事者を「甲」、他方当事者を「乙」と置き換えます。
「甲」「乙」とするのは、契約上の慣例によるもので、「甲」「乙」にしなければならないという決まりがあるわけではありません。
甲と乙はどっちが自分?
甲と乙のどちらも自分になる可能性があります。
甲乙にしなければならない決まりはないように、どちらが甲でどちらが乙かという決まりもありません。
多くは契約書の冒頭部分に甲乙を定義していますから、その定義部分を読んで、自分が甲乙のどちらであるか確認してみてください。多くの場合署名欄も甲欄と乙欄に分かれていますから、確実に自分のほうに署名をしましょう。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








