契約書のコピーの効力は?原本との違いと印紙税を節約する方法を解説
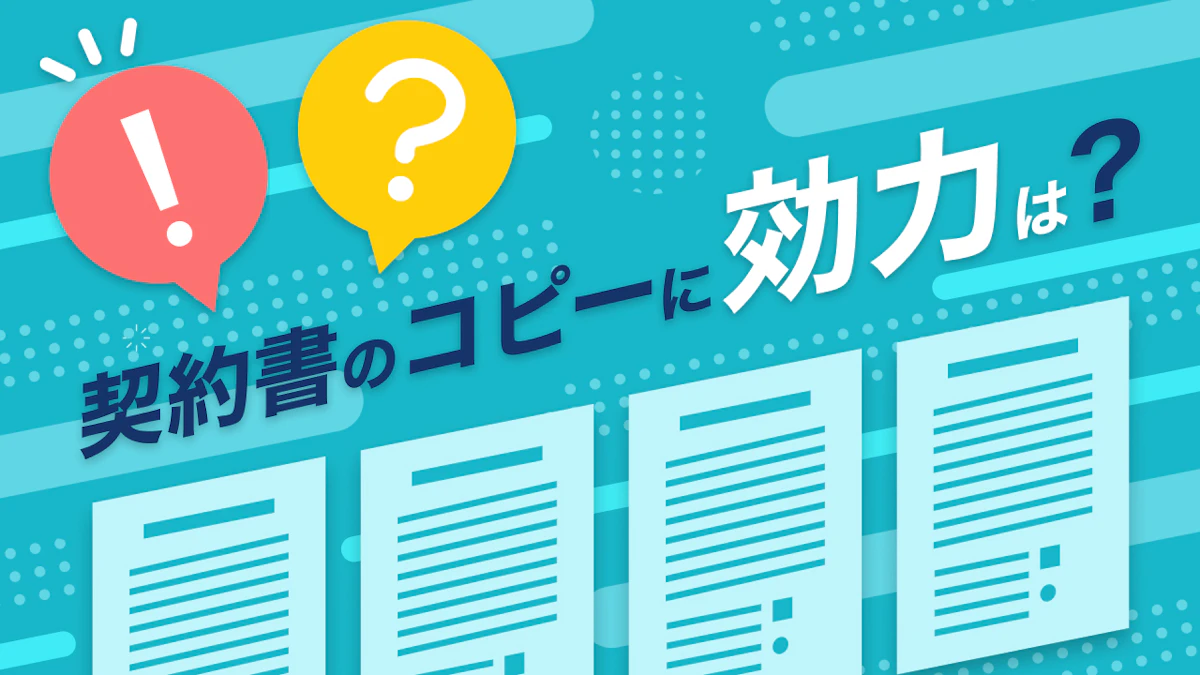
デジタル化が進み、企業で扱う資料もPDFにすることが増えました。デジタル化されたファイルにはリモートでもアクセスできるメリットがあり、今や書類や資料を紙だけで保存することのほうが少ないかもしれません。
契約書も、デジタル化することが増えてきました。ただ、そこで扱いに困るのが紙の原本です。捨てていいのでしょうか、そもそもコピーになった場合、法律上問題はないのでしょうか。
この記事では、契約書をコピーするということ法律上どういった意味があるのかについて、契約書のPDF化にも触れつつ解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
そもそも契約書のコピーに効力はある?

まず、契約書のコピーに法的な効力があるのかについて説明します。
そもそも契約は、原則として意思表示と承諾によって成立します(民法522条)。つまり、契約書のような形式が揃っていなくても、原則として契約は有効に成立します。
ただ、契約書は、確かに契約が成立したことや、契約がどんな内容だったかについて立証する上で非常に有益で、特に原本は、証明力(証拠力)が高いとされています。
コピーは、原本と比べ、改ざんされているおそれがあります。他方でコピーでも、言った言わないと揉めている場合と比べれば、契約の存在や内容は多少なりとも証明しやすいといえます。
このように、契約書の法的効力とは、契約の有効要件ではなく、契約の存在や内容を立証する上での証明力(証拠力)があるということになります。
そして、契約書のコピーは、原本と比べると多少劣るものの、一定の証明力があるといえます。
契約書の「どこだっけ?」を、二度と起こさない
LAWGUEなら、紙のスキャンデータや契約書ファイルをクラウドで一元管理。
契約書ごとに更新履歴をひも付けておけるので、紛失リスクを抑えつつ、必要な契約をすぐに検索・閲覧できます。
日々の契約実務、まとめてスマートにしませんか?
👉 3分でわかる資料を見る

契約書の原本とコピーの違い

それでは、何が契約書の「原本」に当たり、何が「コピー」に当たるのでしょうか。
先ほど述べたとおり証明力が異なるものですから、原本とコピーの区別は重要です。
原本とはオリジナルの文書
契約書には、多くの場合「甲」や「乙」という契約の当事者がいます。自分が当事者として作成するという意味で作成名義人と呼ぶことがありますが、この作成名義人が作ったオリジナルの文書を「原本」と呼びます。
原本には、多くの場合作成名義人の署名・記名と押印があります。改ざんされにくいという点で押印されているほうが良いですが、押印がないからといって契約書の効力がなくなるわけではありません。
また、契約書の中には「課税文書」という印紙税法で定められた文書に当たる場合があり、課税文書には所定の印紙を貼る必要があります。
課税文書の例としては、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などが挙げられます。なお、印紙がなくても契約が無効になるわけではないですが、印紙の貼り忘れが発覚すると余計に印紙税を納める必要が出てしまいます。
コピー(写し)は原本のコピーで効力は弱い
コピーの法的効力を考えるには、もともとの契約書の法的効力から考えていくと分かりやすいです。
先ほど説明したとおり、契約書は契約の存在や内容を立証する上での証明力(証明する証拠になる)があります。原本であれば、作成名義人の自筆があったり、朱肉でハンコが押してあったりします。
他方で、コピーにしてしまうと、筆跡・筆圧・インクの種類などが分かりにくくなります。そうすると、作成名義人ではない別の者が書いた可能性が否定できなくなることがあります。同じように朱肉が付いていればそのようなハンコで押したことが推定されますが、印刷されてしまうと白黒になり、印影の切り貼りの可能性が否定しきれません。
このように、写しにすると、改ざんのおそれが介在することになります。原本と比べ改ざんのおそれを検討しなければならない状態は、証明力が一段落ちていることを意味します。
ちなみにコピーは、法的には「写し」と呼ぶことが多いですが、コピーと写しとで呼び分けているわけでもなく、ほとんど同じ意味(原本のコピー)で使われています。
契約書の原本が必要な場面

以上のように、原本の役割とは、契約の存在や内容を立証するための証拠であるといえます。
そうすると、契約書の原本が必要な場面というのは、「契約の存在や内容を立証したい場面」と言い換えることができます。
契約の存在や内容を立証したい場面というのは、大きく分けて契約の相手方に履行を求める場面、国に対して契約があったことを明らかにしたい場面の2つです。
①契約の相手方に履行を求める場面
契約の相手方が履行に応じず、「そもそも契約などしていない」「そんな内容の契約をしていない」などと反論してきた場合です。
契約の相手方が争ってきたところに履行を求めるわけですから、「ちゃんと契約した」「こういう内容の契約だった」と主張する必要があります。
そんなとき、契約の存在や内容を端的に示せるのが契約書の原本になるわけです。
特に民事訴訟では、契約書のような重要な書証は原本を確認してもらうのが基本となっています。
②国に対して契約があったことを明らかにしたい場面
原本が最も必要とされるのは、税務調査の場面でしょう。取引の証明のために、契約書の原本が確認されます。
印紙税を節約する方法

契約書の原本には印紙を貼らなければならないというのは先に説明したとおりです。
基本的に契約書に記載された金額に応じて印紙税額が決まっており、大きな取引になるほど印紙税額も大きくなっていきます。違法にならない程度に印紙税額を軽減する方法はいくつかありますのでご紹介します。
①契約書のPDF化
まず、契約書をPDF化することが考えられます。契約書のやりとりをメールで行う(紙ではやりとりしない)やり方です。
出力せず紙の原本が存在しないので、印紙を貼る必要がありません。
ただ、大きな問題があります。メールで添付されたデータには署名押印された紙そのものではないので、ファイルは原本ではなく写し扱いになります。
これでも証明力があるという言説も一部でありますが、実務上紙と同様の証明力まで認められているとはいえません。改ざんや取り違えなどがあり得、署名をさせない以上争われたら弱いという実情があります。
印紙の節約のためだけにPDFでのやりとりを行うのはおすすめしにくいです。
そこで、電子データそのものを原本として扱う方法として、電子契約があります。電子署名法により、電子署名とタイムスタンプで改ざんを防止しつつ利便性も確保されているのが特徴です。実務上、電子契約は原本ではあるものの、印紙を貼らなくてよいとされています。
印紙税法基本通達に、課税文書の作成は「用紙等」に課税事項を記載することとされており、電子契約は「用紙等」に記載してはいないから、などがその理由と考えられます。
契約書の電子化により印紙税にも配慮するのであれば、電子契約を導入するのを検討すると良いでしょう。
②契約書のコピーを利用する
「課税文書」である原本に印紙を貼ることになるので、原本を減らせば印紙も減らせることになります。
通常契約当事者が2名の場合、原本も2通作ることが多いでしょう(契約書に「甲乙各1通ずつ原本保管」と記載されているのをよく見ると思います)。
これを、「甲が原本を1通保管、乙は写しを1通保管」とすることで、1通分の印紙で済みます。
ただ、この方法はリスクがあるので注意が必要です。
甲は原本が保管できるので良いのですが、乙は写しを保管することになります。つまり、契約の存在や内容が争われたとき、甲は原本をもって立証できますが、乙は原本を使った立証はできないのです。
印紙を貼らなくてよい経済的なメリットと、争われる可能性、争われて負けた場合のデメリットなどを天秤にかけて写しでよしとするかを考えていきます。
特に一方のみ原本を保管する場合は、交渉力に違いがある場合も多く、この手段を採るべきか慎重に検討する必要があります。
③契約金額を明確に記載する
国税庁の「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」という通達があります。
通達によれば、契約書の中では1号文書と2号文書は、消費税額などが区分記載されている場合または税込価格と税抜価格が書かれている場合には、税抜価格が印紙税の対象になるとされています。
1号文書と2号文書というのは、印紙税法中に表があり、その分類に従って〇号文書と呼ばれているものがあるのですが、1号文書は不動産譲渡などの契約書、2号文書は請負などの契約書になります。
例えば、「契約金額〇万円、うち消費税額等〇万円」「契約金額〇万円(税抜価格〇万円)」などと記載されていれば、区分記載されていることになりますから、税抜価格が対象です。
金額によって印紙税額が変わりますから、税込価格よりも税抜価格のほうが印紙税額は安くなることがあることになります。
契約書の「どこだっけ?」を、二度と起こさない
LAWGUEなら、紙のスキャンデータや契約書ファイルをクラウドで一元管理。
契約書ごとに更新履歴をひも付けておけるので、紛失リスクを抑えつつ、必要な契約をすぐに検索・閲覧できます。
日々の契約実務、まとめてスマートにしませんか?
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
以上、今回は契約書のコピーについて、原本の違いや印紙税の問題も絡めて説明しました。
要点は以下のとおりです。
- 契約書のコピーであっても、契約の存在や内容を立証するための証明力はある。ただ、原本と比べると落ちる。
- 原本とは、作成名義人が作ったオリジナルのことで、コピー(写し)は原本をコピーしたもの。
- 原本は契約の存在や内容を立証するときに使う。具体的には訴訟と税務調査。
- 原本には印紙を貼る必要があるのが原則。電子契約であれば印紙を貼らなくてよく、税込/税抜を駆使することで印紙税額が安くなる契約書もある。
最後に、よくある質問に回答していきます。
よくある質問
契約書はコピーでも良いですか?
契約書はコピーでも良いですが、可能な限りコピーではなく原本を用意すると良いでしょう。
コピーであっても契約が無効になるわけではありません。ただ、原本と比べて証明力が落ちますので、コピーが望ましいとは言いにくいです。
原本があれば契約の相手方に争われても、契約の存在や内容を立証しやすくなります。
電子データにしたいのであれば、紙をPDFにすることは望ましくなく、電子契約が良いです。
契約書は原本とコピーどちらを保管するのでしょうか?
税務調査を考えれば、保管すべきは契約書原本です。契約の相手方から争われた場合を考えても、やはり保管すべきは契約書原本ということになります。
印紙の負担軽減や保管コストの削減などのために、コピーを保管したいこともあるでしょう。最終的にはその契約の重要性なども加味して考えていく必要がありますが、多少の金銭の節約のために大損しないよう注意しなければなりません。
コストのことが気になるのであれば、電子契約を検討すべきでしょう。
契約書のコピーは証拠能力がありますか?
契約書のコピーに証拠能力はありますが、証拠能力が問われる場面はほとんどありません。
そもそも、証拠能力と証明力(証拠力)は異なります。
証拠能力とは、そもそも証拠とできるのか、というものです。
他方、証明力は、証拠とできるとして、どのくらい強く立証できるかを指します。
民事上、証拠能力が問題になる場面はほとんどありません。違法に収集してきた証拠(盗撮など)が問題になり得ますが、非常に例外的です。
契約書のコピーは、原則として証拠能力があります(盗まれた契約書のコピーを違法に入手したような例外的な場合のみ問題になります)。また、契約の存在や内容を証明するものですから、証明力も少なからずありますが、原本と比べると証明力は落ちます。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








