契約書の甲乙丙とは?意味と使い方、記載時の注意点を解説

契約書の多くは2者間のものですが、時に3者間以上の場合もあります。
みなさんにとって一番身近な3者間契約は、おそらく賃貸借契約書でしょう。独り暮らしをするとき、親に保証人になってもらったのではないでしょうか。そのとき、大家が「甲」、借主が「乙」となり、親が「丙」になっていたはずです。
このように、意外にも3者間契約はとても多くの人が体験しているはずのものだといえます。
この記事では、この3者間契約について、特に「甲乙丙」の使い方などについて詳しく解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書の甲乙丙とは

契約書での「甲乙丙」は、契約当事者を置き換えるのに使います。
契約当事者が株式会社A、B株式会社、株式会社Cといる場合に、毎回「株式会社A」「B株式会社」「株式会社C」と書くのは面倒です。
そこで、株式会社Aを「甲」と置き換え、以降はすべて甲と書けば済むようにします。B株式会社とも書くのは面倒なので「乙」にし、株式会社Cもたいへんなので「丙」とだけ書いていけばよいわけです。
以下では、甲乙丙の意味を詳しく説明すると共に、どうして甲乙丙を使うのかという理由についても順に説明します。
甲乙丙丁の意味
甲乙丙は、古代中国の暦に由来します。
古代中国の暦である十干(じっかん)は、甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)と続いていきます。
この十干の順番に従い、1番目の契約当事者を「甲」、2番目の契約当事者を「乙」、3番目の契約当事者を「丙」、4番以降を丁、戊、、、と呼称するようになりました。
通常の契約書であれば甲乙で終わり、そこそこ丙まで書かれた契約書があり、時々丁まで書かれた契約書があるという印象です。5番目の戊は非常にまれで、己以降はほとんど目にすることはありません。
なお、3番目だから必ず丙にしなければならないわけではなく、グループに分けられる場合には少し違った記載をすることがあります。
例えば、被害者1人に対し、加害者が2人いる場合などは、
加害者1(以下「乙1」という。)及び加害者2(以下「乙2」という。)は、被害者(以下「甲」という。)に対し、・・・
などとすることもあります。この場合、甲乙丙とそれぞれ独立するというより、被害者側(甲)と加害者側(乙)という2つのグループがあるとみて、乙グループの中で乙1、乙2と分けています。
甲と乙の立場の区別
それでは、契約当事者のうちどちらが甲になり、どちらが乙になるのでしょうか。
当事者をどう置き換えるかは、法律で決まっているわけではなく、理論的には誰が甲でも乙でもよいことになります。
ただ、通常は上位の者・立場の強い者が甲になり、下位の者・立場の弱い者が乙になることが多いです。
これは、十干の順番に由来します。先に述べたとおり、十干は、甲、乙、丙、、、と並んでいます。
そこで、一番目の甲が上位、二番目の乙がその次、三番目の丙がさらにその次というように、序列が決まることになります。特に丙は、連帯保証人のように、純粋な契約当事者ではない一段落ちた立場の者になることが多いです。
最初に述べた賃貸借契約書が分かりやすいでしょう。賃貸借契約書の純粋な当事者は、貸す人と借りる人です。貸す人のほうが立場が強いですから「甲」、借りる人は「乙」になることが多いです。連帯保証人は一段落ちるので「丙」になります。
企業間の慣習では、相手の企業を「甲」、自社を「乙」とすることも多いです。へりくだった印象になります。
契約書の定義漏れ・表記揺れを減らす
LAWGUEなら、契約書や覚書のひな形・過去文書・条文表現を横断的に確認できます。
甲乙丙の定義漏れや表記ゆれ、修正履歴の見落としを防ぎ、文書の整合性を保ちやすくなります。
法務だけでなく、営業・管理部門も同じ文書を参照でき、確認作業の属人化を防止。
👉 3分でわかる資料を見る

契約書で甲乙丙を使う理由
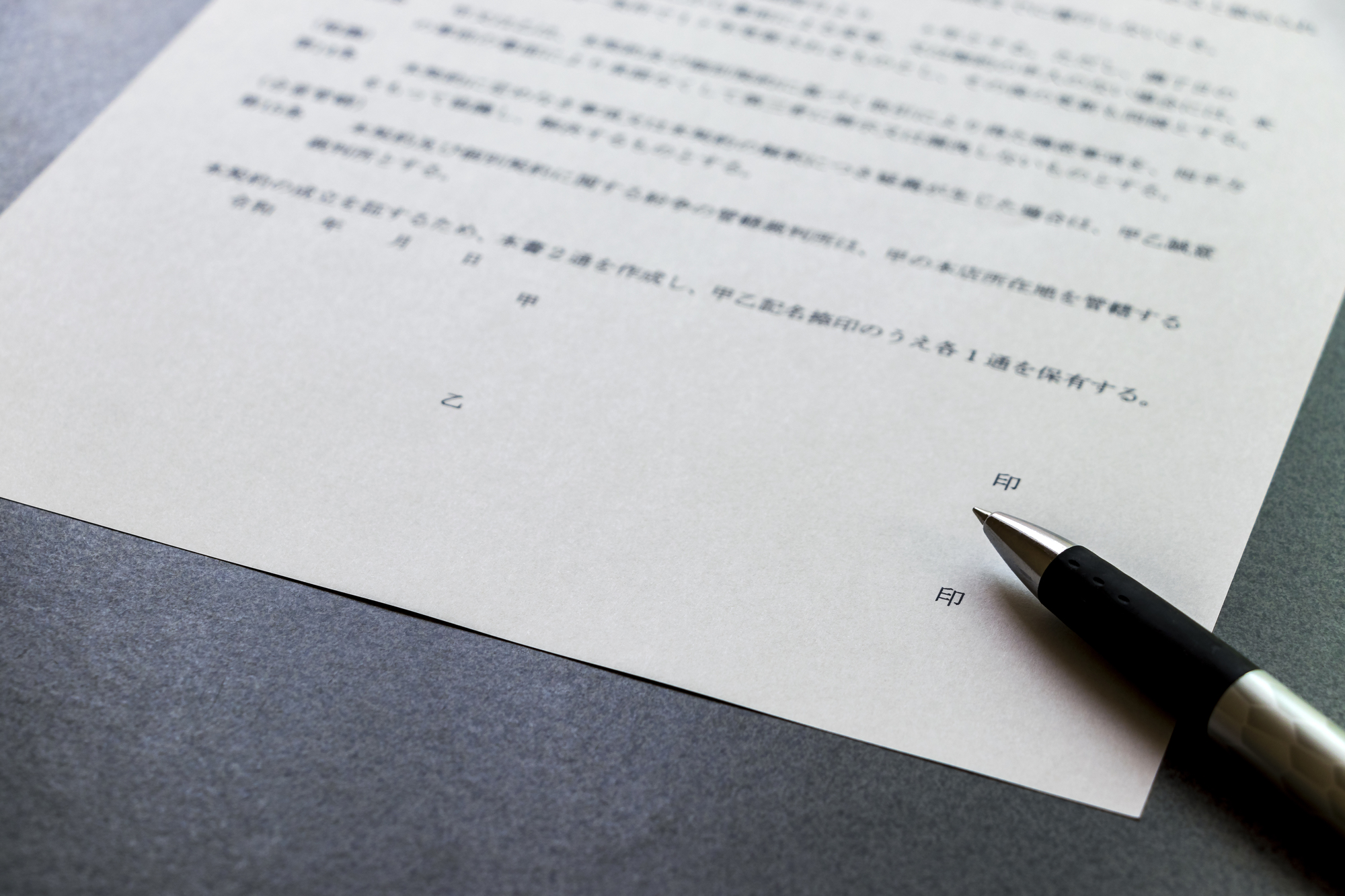
契約書で甲乙丙を使うケースは多いのですが、どうして甲乙丙を使うのでしょうか。
先に述べたとおり、法律で決まっているわけではなく、慣習によって甲乙丙が使われています。
つまり、法律上の要請というより、実際の使い勝手の良さから、使われるようになったと考えられるのです。
使われるようになった理由としては、大きく分けて次の2つが考えられます。
- 契約書の可読性向上
甲乙丙を使わないとすると、条項に当事者が出てくるたびに「株式会社〇〇」と記載する必要が出てきます。これを「甲」と置き換えられれば文章が短くなり、読みやすくなります。
後ほど実例を使って説明します。 - 契約当事者の明確化
甲が貸主、乙が借主のように、契約書を見慣れている者からすると一見して分かりやすく、甲・乙それぞれの権利義務を把握しやすくなります。これも後ほど詳しく説明します。
契約書の可読性向上
まず、契約書の可読性向上について説明します。
例えば、以下の条項をみて、すんなりと頭に入るでしょうか。
1 山田太郎は、鈴木一郎に対し、本日、以下の約定で金〇万円を貸し付け、鈴木一郎はこれを借り受けた。(中略)
2 鈴木二郎は、鈴木一郎が本契約にて負担する一切の債務について、鈴木一郎と連帯して履行することを保証する。(後略)
名前が何度も登場して、文章が長くて分かりにくいのはないでしょうか。
これを「山田太郎(貸主)=甲」、「鈴木一郎(借主)=乙」、「鈴木二郎(連帯保証人)=丙」と置き換えてみます。
1 甲は、乙に対し、本日、以下の約定で金〇万円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。(中略)
2 丙は、乙が本契約にて負担する一切の債務について、乙と連帯して履行することを保証する。(後略)
こうすると、第1条は甲乙間の貸し借りの話、第2条は丙の話であることが分かります。
読み慣れていないと甲乙丙としても恩恵は感じにくいかもしれません。しかし、少なくとも文章の主語を捉えることで、この条項が誰に関連する話なのかが一見して分かります。
契約当事者の明確化
次に、契約当事者の明確化について説明します。
先の例をご覧ください。
甲>乙>丙という上下関係が反映されていることが多いことを前提に、甲が貸主、乙が借主、丙が連帯保証人というのが基本的な慣習です。
つまり、「山田太郎」と何度も書いても「鈴木一郎」との立場の違いはすっと入ってきませんが、「甲」「乙」と書かれれば、「甲が立場が上なので貸主、乙は逆で借主」とすぐに理解できるようになります。
したがって、第1条は、どちらがどちらに貸し、どちらが借り受けたかについて、見慣れた者にとって一見して理解できることになります。また、甲乙が逆転してしまっている場合にも、すぐに発見することができます。
さらに、丙は連帯保証人であるというのが多くの契約書でみられることですから、例えば第2条の主語が「乙」などとなっていれば、たちどころにミスを発見することが可能です。
契約書の定義漏れ・表記揺れを減らす
LAWGUEなら、契約書や覚書のひな形・過去文書・条文表現を横断的に確認できます。
甲乙丙の定義漏れや表記ゆれ、修正履歴の見落としを防ぎ、文書の整合性を保ちやすくなります。
法務だけでなく、営業・管理部門も同じ文書を参照でき、確認作業の属人化を防止。
👉 3分でわかる資料を見る

甲乙丙の正しい使い方

甲乙丙の使い方は法律で決まっているわけでないので、厳密な意味での「正しい使い方」というのは存在しません。
ただ、先に述べたとおり実際の使い勝手の良さから甲乙丙を使っていることから、「一般的な使い方」から外れた使い方では、当事者の混乱を招くことになります。
一般的な使い方としては、以下のようなものでしょう。
- 契約当事者が何人であっても共通するルール
契約書に登場する最初に定義する。途中で入れ替えない。途中で略称を止めることもしない。最後まで同じ人を指し続ける。 - 契約当事者が二者の場合のルール
甲と乙を用いる。甲が目上であることが多い。例えば貸主・借主であれば貸主、元請・下請であれば元請が甲になりやすい。 - 契約当事者が三者の場合のルール
甲乙丙を用いる。当事者間でグループ分けをしたほうが分かりやすい場合には、甲1・甲2、乙1・乙2といったように甲乙間で枝番号を付けるときもある。
丙の立場がやや特殊であることが多い。連帯保証人など。
なお、厳密には契約当事者は二者ではあるが、当事者以外の者でも頻出の場合には、丙とすることもある。
例)甲乙間の離婚協議書において、子を丙として親権者・養育費などを定める
2者間契約での表記方法
契約書に最初に登場する箇所であるため、冒頭で当事者の定義をすることが多いです。例えば前記の例では、このような前文が付きます。
貸主山田太郎(以下「甲」という。)と借主鈴木一郎(以下「乙」という。)との間で、本日、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
1 甲は、乙に対し、本日、以下の約定で金〇万円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。(後略)
固有名詞の前に貸主・借主と表記しない例もありますが、理解しやすくなるので入れることも多いです。
第2条以降も、山田太郎はすべて甲として、鈴木一郎はすべて乙として記載していきます。
契約書の最後に、甲署名欄・乙署名欄を設け、甲欄には山田太郎が、乙欄には鈴木一郎が、それぞれサインをします。
冒頭で甲乙を定義しているので、そこを確認すれば甲乙欄の記入間違いを減らすことが可能です。
3者以上の契約での表記方法
3者間では、例えば以下のような前文を付けます。
貸主山田太郎(以下「甲」という。)、借主鈴木一郎(以下「乙」という。)及び連帯保証人鈴木二郎(以下「丙」という。)との間で、本日、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
1 甲は、乙に対し、本日、以下の約定で金〇万円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。(中略)
2 丙は、乙が本契約にて負担する一切の債務について、乙と連帯して履行することを保証する。(後略)
山田太郎が出てくる箇所はすべて甲に、鈴木一郎が出てくる箇所はすべて乙になっていることが分かるでしょう。さらに丙として鈴木二郎が定義されており、乙と連帯して責任を負うことが明記されています。
四者目が出る場合には、「戊」を使います。四者間契約が出てくることは少ない(四者目を覚書にするなどして別書面にすることも多い)のですが、契約当事者以外の者が出てくる場合に戊を使う例は相応にあります。例えば以下のような例です。
甲乙当事者間の長男A(令和〇年〇月〇日生。以下「丙」という。)及び二男B(令和〇年〇月〇日生。以下「戊」という。)の親権者を母である乙と定め、今後、乙において子らを監護養育する。
甲乙丙を使う際の注意点

甲乙丙は、読みやすさのために使われているので、一般的ではない使い方やミスがあると、逆に分かりにくくなってしまいます。そのため、甲乙丙を使う際に気を付けるべき点をまとめます。
- 一般的な使い方をすること
甲乙丙はある程度立場とリンクしていますので、一般的な使い方を学びましょう。例えば乙を連帯保証人、丙を借主にするようなことは、混乱を招くだけです。 - 最初に定義すること
契約書に最初に登場した箇所で定義しましょう。例えば第1条で山田太郎と略さず、第2条で急に山田太郎(以下「甲」という。)と定義した場合、第1条の山田太郎と第2条の山田太郎は別人ではないかという疑義が生じてしまいます。 - 途中で甲乙を取り違えないこと
どうしてもミスは起きてしまうのですが、やはり一番多いミスは甲乙の取り違いです。
ミスを減らすため、例えばwordの置換機能を使ってみて、文章の意味が通るかなどを確認することもあります。 - 最後まで同じ略称とすること
途中で使わなくなったり、1箇所だけ略称を使わなかったりなどの使い方はやめましょう。
②に記載したとおり、途中で表記が変わると、別人を指すものと読まれてしまいます。
表記の一貫性を保つ
この表記の一貫性について、もう少し詳しく説明します。
先ほどの例でみていきます。
1 山田太郎は~
2 山田太郎(以下「甲」という。)は~
3 山田太郎は~
4 山田太郎(以下「丙」という。)は~
という記載があった場合、最初に定義する慣習からみて、第1条の山田太郎は甲ではないと読まれてしまう可能性があります(厳密には「以下」と定義しているので、第1条も甲と読むことは可能なのですが、無用な混乱を招きます)。
また、第3条の山田太郎は、第2条の「以下甲」という定義からすると、甲とは別人と読むほうが自然です。
さらに第4条は、違う略称を定義してしまっているので、確実に甲とは別人と理解されるでしょう。
定義が揺れてしまうと、契約の意味内容が変わってしまうのです。
これを避けるため、当事者名や甲乙で文書検索をかける、置換してみて意味が通るか読んでみるなどの方法があります。
甲乙丙を使わないケース
先に述べたとおり、甲乙丙は実際の使い勝手の良さから使われているものであり、甲乙丙を使わないほうが分かりやすい場合には、甲乙丙にこだわらない場合もあります。
例えば貸主・借主をわざわざ甲・乙と置き換えず、
山田太郎(以下「貸主」という。)と鈴木一郎(以下「借主」という。)
としてしまうのもよいでしょう。
この表記であれば、以降も貸主・借主と記載されますから、一見して条項の意味が分かるようになります。また、甲乙を取り違えるリスクも減ります。さらに、甲乙を使うと上下関係を示してしまうことにも繋がりかねないので、企業の略称を使うこともあります。
現在では、甲乙を使わない例が増えてきています。
法的に決まりができたわけではなく明確な理由はありませんが、英文契約書は企業の略称を使うので、英文の慣習を流用するようになったのかもしれませんし、甲乙が古臭さや堅苦しさを感じさせるからかもしれません。
電子契約における甲乙丙の扱い
電子契約でも、甲乙丙は同じように使われます。
ただ、後文(契約書の最後に記載するもの)は、少し変わるので注意が必要です。
紙であれば、
本契約の成立を証するため、甲及び乙は、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
として、記名をすることが明記されます。
他方で電子契約であれば、記名はしないので、
本契約の成立を証するため、甲及び乙は、本電子契約書ファイルを作成して電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
などとし、原本をどうするかなどを記載していきます。
また、電子署名やタイムスタンプがあるので住所欄は不要ではないかという考えもありますが、契約書そのものから当事者の特定ができたほうが安全なので、住所欄を設けることが多いです。
まとめ
以上、今回は「甲乙丙」の解説をしてきました。
要点は以下のとおりです。
- 契約書の甲乙丙は、法律によって決まっているわけではなく、使い勝手の良さから使われている
- 甲と乙では甲が目上になることが多く、丙はやや特殊な立場であることが多い
- 甲乙丙を使うことで、可読性を上げることができるなどのメリットがある
- 甲乙丙を使う際には、最初に定義し、最後まで一貫させることが重要
- くれぐれも甲乙の取違いには注意
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








