覚書と契約書の違いとは?使い分け・書き方を完全解説!

企業間の取引では、合意を証明するための書面として一般に契約書が用いられますが、覚書が用いられるケースも少なくありません。
覚書は、特に正式な契約書を作成する前の合意事項を簡潔に記録したり、契約書の内容を補完、変更したりする場合に使用されます。
本記事では、覚書の基本的な意味や役割、契約書や念書との違い、覚書の作成ポイントについて解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
覚書と契約書の違いとは

覚書とは、一般に当事者間の合意事項を記録した書面を意味します。
ビジネスシーンで日常的に用いられている契約書も、当事者間の合意事項を記録した書面のことを指します。そのため、覚書は契約書の一種ということができますが、覚書と契約書は、次のような違いがあります。
- 記載する内容
- 使用するのに適した場面
- 法的拘束力を持たせるか否か
「覚書」と「契約書」の本質的な違い
まず、契約書と覚書は、記載する内容が異なります。
契約書は、取引当事者が合意に至った内容を詳細に記載し、権利と義務の関係を明確にするために作成するものです。複雑な契約事項を含む契約は特に、支払いの条件や引き渡しの条件など、具体的な内容を記載するほか、一般条項もある程度網羅的に記載することで、契約内容全般について取り決めるものとするのが一般的です。
これに対して、覚書は、正式な契約書の締結前の交渉段階で、重要な事実や合意事項を記録するための文書として締結します。また、契約書作成後に契約内容を変更・補完するために作成される補足的な文書でもあります。
法的拘束力はどう異なる?
覚書は、記載される内容や使用される場面が異なるだけで、契約書の一種であるため、基本的には契約書と同様の法的拘束力を持ちます。
各当事者の意思に基づき作成された覚書であれば、原則として当事者は覚書に定められた内容の権利を得、義務を負います。
ただし、覚書の中には、M&Aや事業提携などの大型契約の交渉に先立ち、基本的な事項を暫定的に合意しておく趣旨で締結することもあります。このような場合は、確定的な契約内容は各当事者の交渉や検討の後に確定させることとして、覚書の段階では、法的拘束力を持たせないことも可能です。
例えば次のように、法的拘束力の有無を旨明記しておくことが実務的に見られます。
本覚書のうち第○条及び第●条についてのみ法的拘束力を有し、その他の条項については法的拘束力を有しない。
フォーマットと形式の違い
上記のとおり、覚書も契約書の一種であり、当事者間で契約内容を合意するための文書です。
一部の契約類型を除き、特定の方式でおこなうことは契約の成立の要件ではないため(民法第522条第2項)、覚書や契約書に特定のフォーマットや形式はありません。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
もっとも、実務上、契約書については「売買契約書」「金銭消費貸借契約書」のように契約内容を示す表題を付けます。覚書については「契約条件変更の覚書」「個人情報の取扱いに関する覚書」といったように、何に関する覚書であるかを表題に付けることが一般的です。
契約書・覚書が増えても迷わない文書管理
LAWGUEなら、契約書・覚書・関連資料をまとめて保管し、過去文書も横断検索。
契約が混在する環境でも、文書の所在や履歴を把握しやすくなります。
法務だけでなく、関係部門間で同じ文書を共有でき、確認作業の手戻りを減らします。
👉 3分でわかる資料を見る

覚書とは?役割と特徴

「覚書」とは、一般的には、忘れないように書き留めておく文書、メモ、備忘録などのことです。しかし、ビジネスシーンにおいては意味が異なり、覚書は多くの場合、当事者間の合意内容を記載した文書を指します。
「覚書」と題する文書であっても、書面の内容が当事者同士の意思表示の合致を証明するものであれば、契約書には変わりありません。つまり、覚書は契約書の一種ということができます。
覚書の意味と主な役割
覚書は、使用する場面や記載する内容が異なるものの、契約書の一種であるため、次のように、契約書と同様の役割を持っています。
- 当事者間の合意を示す客観的な証拠となるため、後のトラブルの防止に役立つ
- 合意内容を覚書(契約書)に反映する過程を通じて、当事者双方の認識のすり合わせがなされるため、後のトラブルの防止に役立つ
- 契約締結後、取引実行の手順書になる
覚書で守られる範囲は?
覚書は契約書の一種であるため、それによって得られる法的効果についても契約書と同様に考えることができます。
覚書が正式な契約書に先行して暫定的に合意するために用いられる場合、覚書には記載していたものの契約書には記載していない内容・条件が出てくる場合があります。
このような内容は、契約内容となっているか否か、法的拘束力があるか否かをめぐって、後に当事者間で見解の相違が生じることが懸念されます。
そのため、覚書に記載していた重要な条件は、正式な契約書において、法的拘束力の有無を明確にしたり、完全合意条項を設けたりするなどして、覚書と契約書とで内容が矛盾衝突しないように手当しておくことが重要です。
【完全合意条項の例】
本契約は、本契約締結時における甲及び乙の合意の全てであり、本契約締結以前における甲乙間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ等は、本契約の内容と相違する場合は、効力を有しない。
また、覚書であること、契約書であることを問わず、内容が不明確な契約条項については一般に法的拘束力が否定されます。
覚書は、そのタイトルや使用される場面からして、抽象的・不明確な内容で締結してしまいがちです。法的拘束力を生じさせることを意図していたのに、後に相手方に法的拘束力を争われ、訴訟で否定されてしまわないよう、条文の内容の明確性には注意しましょう。
覚書を作成するメリット
覚書は、使用する場面や記載する内容が異なるものの、契約書の一種であるため、契約書と同様の役割を持っています。
- 当事者間の合意を示す客観的な証拠となるため、後のトラブルの防止に役立つ
- 合意内容を覚書(契約書)に落とし込む過程を通じて、当事者双方の認識のすり合わせがなされるため、後のトラブルの防止に役立つ
- 契約締結後、取引実行の手順書になる
契約書ではなく覚書を用いるメリットとしては、一般的には次のようなものが挙げられます。
- 契約書と異なるタイトル・形式の文書を用いることで、正式な契約締結の前段階の暫定的な合意であることが明確になる
- 契約書の内容の一部だけを変更しようとする場合に、契約書そのものを締結し直すよりも決裁者やレビュー担当者の事務負担を軽減できる
契約書とは?法的効力と重要性

契約書とは、取引当事者が文書によって契約を締結する場合のその文書のことです。
契約書の性質上、原則として、契約書に記載されている内容がそのまま当事者間の契約内容として法的拘束力を持つことになります。そのため、企業が取引をおこなう際も、後にトラブルとなった際も、契約書が重視されているのです。
契約書の本質と目的
契約は、当事者の申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立します(民法第522条1項)。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、特定の様式によることを要しないため、口頭の合意によっても契約を成立させることはできます。
しかし、企業間の取引では通常、契約内容を記載した契約書を作成し、契約書への署名捺印または記名押印により合意をします。これは、契約の申込みの意思表示と承諾の意思表示を契約書という文書によっておこなっているということです。
関係者が多数関与する企業間取引においては、口頭で契約を締結することは実質的に不可能でしょう。また、契約内容・条件も複雑で多岐にわたるため、両当事者が確実に合意を形成し、かつ、その内容の明確な証拠とする必要があります。そのために、契約書という文書が使用されるのです。
なぜ契約書は重要視される?
契約書は、文書によって一定の取引条件についての合意を成立させるものであり、この文書自体が、当事者の契約の申込みと承諾の意思表示で、契約内容を示すもっとも直接的な証拠となります。
したがって、取引をめぐって当事者間でトラブルが生じた場合、契約書が当事者の意思に基づいて作成されたことが確認されれば、裁判所はその契約内容に則して判断をします。
また、業種や企業によって差はあれど、企業が取引をおこなうにあたって契約書を取り交わすことが一般的であるため、重要な取引については、契約書を作成していないこと自体、契約内容に合意していないと窺わせることにもなりえます。
そのため、重要な取引や、自社に有利な重要な条件を含む取引については、特に契約書などの文書に契約内容を定めておくことが重要となります。
契約書があれば必ず保護される?
契約は当事者の申込みと承諾の意思表示の合致により成立し、原則として特定の様式を要しません。
もっとも、契約の成立要件と有効要件は別物であり、公序良俗・強行法規(公序の維持や弱者保護などの目的から、無効とされる内容もあります。
- 消費者契約法の規定に反して事業者の損害賠償責任を免除する条項
- 利息制限法の制限利率を超える利率の金銭消費貸借契約の利息条項
- 労働基準法に違反する雇用契約の条項
- 借地借家法に反して借主に不利な賃貸借契約書の条項
また、独占禁止法や各種業法などの取引について一定の規制を課している取締法規に違反した場合、当然に契約が無効となるわけではないものの、違反した条文の趣旨などによっては訴訟において契約が無効と判断されることもあります。
そのほか、条文の文言が多義的であったり不明確であると、相手方や裁判所に自社が意図したものとは異なる内容と判断されたり、条項自体が無効とされたりする可能性が否めません。
問題のある内容の契約書を締結してしまうと、後のトラブルや意図したとおりの効力が認められない原因となってしまうため、契約書作成の段階で契約内容の適法性・妥当性については慎重に検討する必要があります。
覚書と念書の違いとは
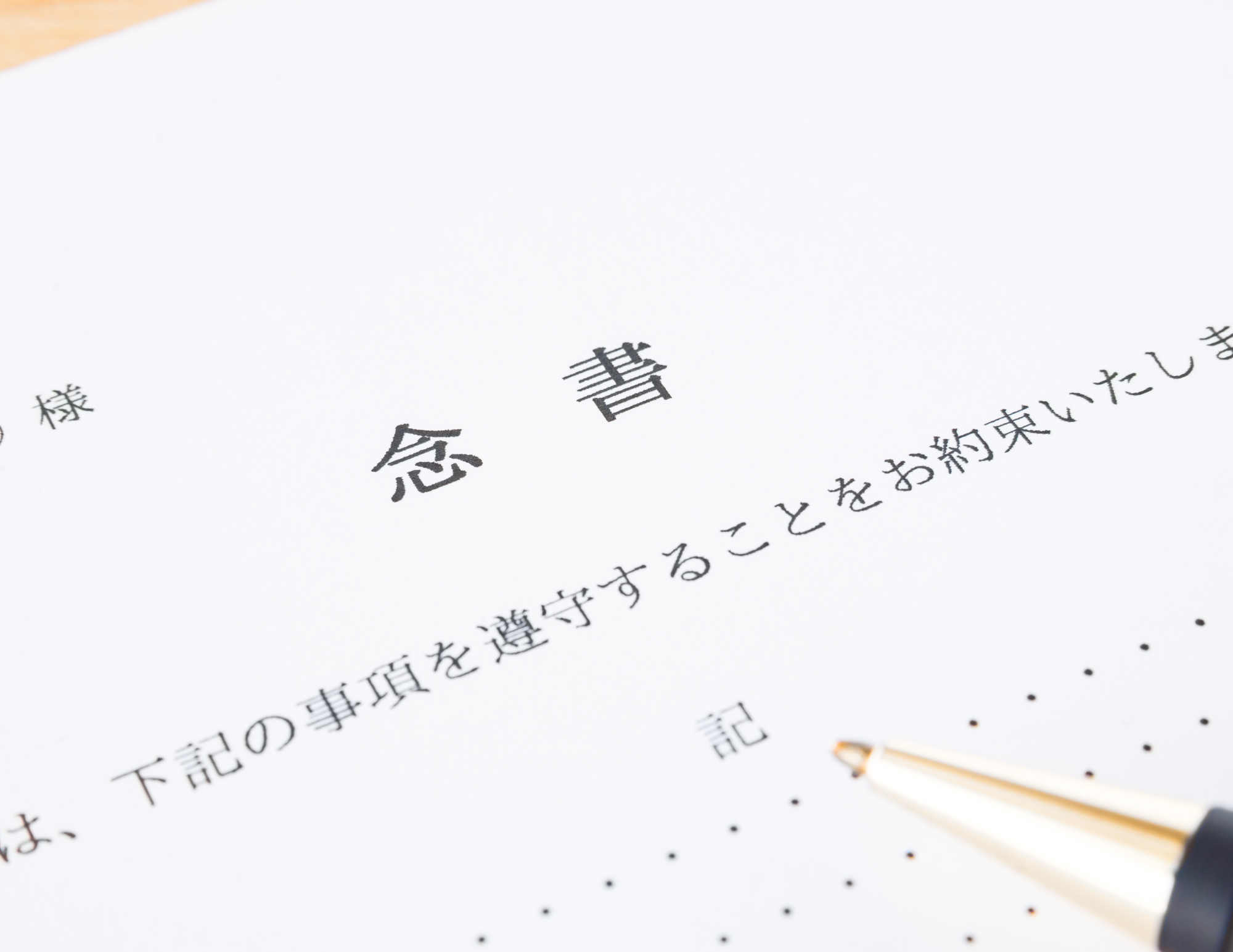
取引の場面では、覚書と似た「念書」という文書が使われることがあります。念書と覚書は語感が似ていますが、使用される場面や法的な意味は異なります。
以下では、念書の特徴や覚書との違いについて解説します。
念書とは?主な特徴
念書とは、当事者の一方が相手方に対して約束した内容を記載して差し入れる書面を指します。「誓約書」などの表題を付けられることもありますが、法的な意味合いは同様です。
一方当事者が相手方に履行を求める事項を記載して念書を渡し、念書を受け取った側が署名または押印して差し入れる形をとられるのが一般的です。
念書は、例えば次のような場面で用いられます。
- 退職時に、退職者が会社に対して秘密保持や競業避止義務を負うことを確認する場合
- 金銭消費貸借契約において、借主が借入金額や返済期日を記載して貸主に差し入れる場合
双方の合意を前提とした覚書とは異なり、念書は、契約当事者の一方からの約束事を記した文書です。しかし、一般的には他方の当事者も内容に納得し、そのとおりの履行を望んでいます。
つまり、念書は、この文書によって一方当事者が意思表示をおこなったという証拠であり、かつその念書の内容は他方当事者が求めた内容であるといえます。そのため、念書も、契約書や覚書と同様、当事者間で記載内容の合意が成立したことを証明する文書となるのです。
作成目的が異なる覚書と念書
覚書は複数の当事者がお互いに相手方に対して義務や責任を負う場合に、それを文書として残すために取り交わすものです。これに対して、一方が相手方に対して義務や責任を負うことを確認しようとする場合は、その一方当事者が書面を相手方に差し入れれば目的は達成できます。
このような場合は、契約当事者の双方が署名押印する契約書や覚書ではなく念書や誓約書が用いられることが多いです。
覚書を使うケースと書き方
これまで見てきた覚書と契約書・念書の違いを踏まえると、次の場合は覚書が適しているといえるでしょう。
- 当事者双方がお互いに相手方に対して義務を負う合意
- 正式な契約書の締結前の暫定的な合意や、正式な契約書の一部を変更するなど付随的な内容についての合意
効力を高める覚書の書き方ポイント
覚書は基本的に契約書の一種であるため、契約書による合意が有効に成立するためのポイントと同様です。
覚書を作成・レビューするにあたっては、
- 文言は明確、一義的か
- 公序良俗・強行法規に違反しないか
- 取締法規に違反しないか
などに注意を払う必要があります。
また、覚書特有の注意点としては、例えば
- 既存の契約書の内容と矛盾・抵触しないか
- どの契約書に関する覚書か特定できているか
に注意が必要です。
覚書作成時の必須記載項目
覚書は基本的に契約書の一種であるため、合意内容と当事者名の記載は必須ですが、それ以外については法律上特定の様式や記載事項はありません。
もっとも、次のような構成になっているものが一般的です。
【表題(タイトル)】
覚書の冒頭には、表題(タイトル)を記載します。「契約条件変更の覚書」「個人情報の取扱いに関する覚書」のように、具体的な表題をつけます。
【前文】
次に、前文には契約に合意した当事者を明記し、契約書と同様、当事者は「甲」「乙」や、「買主」「売主」などと記載します。すでに契約書を交わしている場合は、その契約書と同じ呼称を使いましょう。混乱を避けることができます。
【本文】
本文では、当事者双方が合意した内容を記載します。契約書と同様、条文形式で記載するのが一般的です。
既存の契約書の内容と関連する内容を定める場合は、「○年○月○日締結の○○契約に関し」といったように、関連する契約書を特定します。
正式な契約書の締結前の覚書において、法的拘束力を生じさせない条文がある場合は、上記のとおり、どの条文に法的拘束力を持たせるのか(持たせないのか)明確にしておきましょう。
既存の契約書の内容を変更する覚書の場合、変更前の条文を記載することまでは必須ではなく、記載する場合もしない場合もあります。いずれにしても、一目で変更後の条件を把握できるようにしましょう。
【後文・契約締結日・署名押印欄】
契約書と同様、「以上、合意の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通ずつ保有するものとする。」などの書き方が一般的です。
最後に、契約締結日と当事者双方の署名、押印をおこないます。上記のとおり、署名または押印することで、本人(企業においては、通常代表取締役またはその指示を受けた従業員)が覚書を作成したことの証拠となりますので、事実上、署名または押印が必須です。
覚書に印紙は必要?税法上の扱い
覚書は契約書の一種ですので、契約書と同様、課税文書に該当する場合は記載された契約金額に応じた印紙税の支払いが求められ、収入印紙の貼付が必要です。
課税文書に該当するかどうかは、以下の3つの条件を満たしているかで判断されます。
印紙税の対象となる文書とは
次の3つの要件を満たす文書は印紙税の対象となる課税文書に当たります。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を1つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容に基づいても判断することとなります。また、その文書の内容判断に当たっては、単にその名称、呼称や記載されている文言により形式的におこなうのではなく、文書に記されている文言、符号などを用いることについての当事者間における了解や慣習などを加味して総合的におこなう必要があります。
第2号文書(請負に関する契約書)や第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)は比較的多くの企業で使用される契約書の類型ですので、覚書締結の際は、注意しましょう。
覚書への印紙貼付の判断基準
「覚書」や「念書」などの表題を用いて、原契約書の内容変更をする旨の文書を作成する場合があります。これらの文書が課税文書に該当するかどうかは、「重要な事項」が変更契約書に含まれているかどうかにより判定することとされています。
国税庁は「タックスアンサー(よくある税の質問)」において、重要な事項の変更について、次のように述べていますので、印紙の要否の判断の際の参考になります。
- 原契約書が、課税物件表の1つの号の文書のみに該当する場合で、その号の重要な事項を変更するものであるとき
原契約書と同一の号の文書として取り扱われます。 - 原契約書が、課税物件表の2以上の号に該当する場合
(1) その2以上の号のいずれか一方のみの重要な事項を変更するもの
その一方の号の文書として取り扱われます。
(2) その2以上の号のうち2以上の号の重要な事項を変更するもの
一旦、それぞれの号の文書に該当した上で、印紙税法別表第1「課税物件表の適用に関する通則」3の規定に基づいて最終的な所属が決定されます。
契約書・覚書が増えても迷わない文書管理
LAWGUEなら、契約書・覚書・関連資料をまとめて保管し、過去文書も横断検索。
契約が混在する環境でも、文書の所在や履歴を把握しやすくなります。
法務だけでなく、関係部門間で同じ文書を共有でき、確認作業の手戻りを減らします。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
覚書は、正式な契約書作成の前の合意事項を記録したり、契約書の内容を補完したりする場合に使用される、契約書の一種です。
覚書の締結にあたっては、契約書一般に共通する注意事項のほか、締結済みの契約書との関係性など、覚書特有のポイントにも注意しましょう。
よくある質問
覚書と契約書は同じ効力ですか?
表題が異なるものの、覚書は契約書の一種です。そのため、法的拘束力の有無は基本的には同じです。しかし、契約書締結前段階での覚書については、あえて法的拘束力を持たせない場合もあるため、覚書の作成・レビューに当たっては、法的拘束力を持たせるか否かが検討事項になります。
覚書はどんなときに使うのですか?
契約書に付随する内容、既存の契約書の内容の一部を変更する場合などに用いられます。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








