規程管理システムとは?効率化とガバナンス向上の実現方法について解説

規程管理システムを導入した、あるいは導入を検討している企業は増えてきているように感じます。
雑多な社内規程集では、どこに何が書いてあるか分かりにくく、最新の法改正に対応しているのか、対応するためにどこを改正すべきかもすぐには分かりません。
規程管理システムを導入すれば、改正や検索も容易になります。
今回は、規程管理システムの概要を説明した後、それがどのような点で企業にとって効率化をもたらすか、セキュリティ対策を通じてガバナンスがどう向上するかなどを解説します。
【参考】規程管理ツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉規程修正における新旧対照表を簡単に作成
👉ひな形を使って新しい社内規程を簡単作成
👉条番号の修正もれを自動体裁補正で防ぐ
規程管理システムとは何?

規程管理システムとは、主に企業内のことについて使われる概念です。つまり、企業内で定められている各種の社内規程を管理するためのシステムを、規程管理システムと呼ぶことが多いといえます。
「規程」というのは、ルールという意味で、法律でいえば法律そのものを表します。似たような言葉に「規定」がありますが、これはルールの中の1つ1つの条文を指すことが多いです。法律でいえば、多くの場合、法律の中の各条項を規定と呼びます。
例えば規程は民法を指し、規定は民法第1条を指すといった具合です。
しかし、規定は規程と同じように使うこともあり、規定が民法も民法第1条も指すことはあります。一方で規程を規定と同じように使うことはまずなく、民法第1条を指すことはまずありません。
つまり、規程管理システムといった場合、社内の各種規程そのものを管理することを意味します。
企業のルールブックを一元管理する仕組み
規程管理システムを導入していない場合には、社内のいたるところに規程が分散しているのが通常です。
労務関係の規程は人事に、賃金を含む支払いに関するものは経理に、取締役会などの各種組織の運営に関するものは総務・法務に、それぞれ管理されていることが多いでしょう。
これを分散管理といいます。
分散管理では、担当者がすぐに該当の規程に当たることができるというメリットがありますが、ほかの部署の規程にはなかなか当たることができません。
その結果、規程同士の関係が分かりにくくなったり、矛盾したりします。
他方で規程管理システムには、社内規程をほとんどすべて登録しておきます。いわゆる一元管理です。
社内規程は、通常階層的に存在します。人事・労務は就業規則を頂点に、賃金規程・賞与規程などが下にあり、さらに細則などの細かいマニュアルが存在するというかたちです。経営であれば取締役会規則があり、その下に取締役会議事細則があります。
規程管理システムでは、規程を階層で管理し、規程相互の主従関係を分かりやすくすることで、相互に矛盾がないように確認しやすくなります。
規程を新しく作成・修正する際にも、同種の規程を参照しやすくなるのが特長です。
このように、分散管理では複数の規程にわたるような事象が発生した場合に対処しやすいというメリットがあります。
紙からデジタルへ:規程管理の進化
近年、社内規程集といった紙での管理から、社内規程ファイルといったデジタルでの管理が主流になっています。
紙からデジタルへの移行には、さまざまな段階があります。
- PDFなどで取り込んだだけの段階
当初は、PDFなどでただ取り込んだだけの管理がおこなわれました。
改ざんのリスクはありませんが、規程の新規作成や改正のたびに取り込み直す必要がありました。 - 作成そのものをデジタルにする段階
ついで、各種規程をWord(一部Excel)で作成することが増えました。作成や改正は楽になりましたが、改正履歴の保存ができていなかったり、改ざんされていても発見が遅れたりと、規程を作成した後の管理段階がままならないことがあります。 - 規程管理システムを導入する段階
現在は、規程管理システムを導入して管理することが増えつつあります。
後で述べますが、作成する段階で形式面での補正をする機能や、改正履歴を保存する機能などさまざまな機能があり、規程を作成した後の管理段階もより有機的におこなうことができるようになりました。
規程管理システムは、法務DXの一環として位置付けられます。
契約書作成は電子契約サービス、契約書チェックはAIレビュー、規程管理は規程管理システムといった具合です。これらを相互にリンクさせることも進められています。
規程管理システムの主な機能

規程管理システムは、社内規程を一元管理するシステムです。
したがって、一元管理しやすいような機能が備わっています。例えば主に以下のような機能があります。
- 規程作成段階
新規作成機能:ひな形の備付、アンケート回答による自動作成など
編集機能:条数修正、表現のゆらぎ修正など - 規程改正・廃止段階
履歴保存機能:修正箇所、修正内容の記録、廃止規程の保存
検索機能:関連規程の全文検索など - 運用段階
周知機能:従業員への周知など - 保管段階
検索機能:体系検索、全文検索など
このうちのどの機能を重視するかは、業種や企業規模などによって変わります。例えば、企業規模が大きくなるほど規程の階層が増える傾向にあるために検索機能が使いやすいものが適しているでしょう。
それぞれの機能を解説していきます。
規程文書の作成と編集を効率化する機能
多くの規程管理システムには、専門家が作成した典型的規程のひな形が入っています。いくつかの質問に答えるだけである程度の形にしてくれるアンケート機能を備えたものもあります。
従来であれば、同種の規程やひな形を探し、当てはめていく作業が必要でした。規程管理システムを使えば、より簡単に作成することが可能です。
条数や表現のゆらぎなどを自動で修正してくれる機能もあります。条項番号のズレはやりがちなので、とても助かります。「または」と「又は」、「取り消す」と「取消す」など、どちらの表現を基本にしていたかも忘れがちですが、表記揺れを指摘してくれるので表現の統一が図りやすくなります。
また、編集の際に複数人で同時に作業する機能が含まれ、編集履歴の管理がしやすいものもあります。ワークフローと連携させれば、作成・編集・承認などのプロセスも効率化することができます。
ワークフローとの関係は、次項で詳しく説明します。
承認フローと権限管理で更新プロセスを最適化
多くの企業では、社内規程を策定するルールがあります。
例えばまずは法務部が文案を作り、法務部長が承認をし、さらに取締役のチェックが入り、と階層的に進んでいきます。
規程管理システムにより、承認フローそのものを管理することができます。つまり、システム上で承認をすることで、より上部の管理者に移っていくのです。
承認フローを適切なものにするには、権限管理が不可欠です。役職に応じて権限設定をします。規程管理システムには、権限管理機能も付いていることが多いです。
役職によって、例えばアクセスできる規程の範囲を変えたり、権限の範囲(閲覧、作成、修正、削除など)を変えたりすることもできます。
権限管理を規程によって変えれば、例えば部門間連携が必要な規程の場合に異なる部門が一緒に更新プロセスに参加できるようになります。
バージョン管理と履歴追跡で変更を可視化
多くの規程管理システムには、履歴保存機能が付いています。
これにより、どのタイミングでどのような規程だったかが分かります。履歴を追跡すれば、どのように変更されたかを可視化できます。
規程は、原則としてその時点のものが適用され、遡及的に適用されることは稀です。したがって、現時点の規程以上に、過去のある時点での規程の内容が重要になる場合が多いといえます。
近時の法改正は、特に労務部門で当初努力規定とし、徐々に義務規定とする運用が増えています。例えば、年次有給休暇、有期雇用、定年制などです。
法改正がどの時点で盛り込む必要があるか、実際に盛り込めたかを確認するために、履歴の追跡は非常に重要な意味を持ちます。
監査においても、義務規定を適時に規程に取り込めているかは重要なポイントです。規程の履歴の保存は、監査対策にもなります。
検索・閲覧機能で必要な規程にすぐアクセス
多くの規程管理システムには、検索機能が付いています。
通常、複数の検索機能があります。五十音検索はもちろん、全文検索もできます。特定の階層や分野に限定した検索も可能です。
規程に適切なタグをつけておけば、タグ検索をおこなうことで特定の事項に関係する規程を検索することもできます。
規程管理システムによっては、関連する規程を表示してくれるものもやAIサジェストに対応しているものもあります。
また、モバイル端末による閲覧に対応しているものもあり、企業によっては、どこでも閲覧できることが強みになることもあるでしょう。
他方で、閲覧機能を充実させることは、その分漏えいのリスクをはらむことになります。
規程の性質や重要性にあわせて、また、従業員の役職にあわせて、閲覧権限を調整することが考えられます。
規程管理システム選びのポイント

規程管理システムには多様な機能があり、どの機能が充実しているかなどのバリエーションがあり、さまざまな商品があります。
どの規程管理システムを選べばよいのでしょうか。
多くの場合で検討すべき項目は以下のとおりです。
①社内ニーズの把握やコストとの兼ね合い
②操作性
③セキュリティ
選定する際には、実際に使うであろうと想定される者(法務、規程作成者、規程管理者など)を巻き込み、社内ニーズを把握することが重要です。
以下、詳しく説明します。
自社規模と管理規程数に合った拡張性は十分?
まず、社内ニーズから導き出される必要機能の絞り込みです。
例えば、改正が多く見込まれるのであれば履歴の保存が大切ですし、多くの者が確認する必要があれば閲覧機能が重要になります。
機能の選定は、コストとの兼ね合いでも重要なポイントになります。不要な機能を削ぎ落すことは、コスト節約に繋がります。
機能で絞った後は、企業規模に合ったシステム(コース)を選ぶことになります。
一般に、費用は規程数と使用者数(アカウント数、ライセンス数)で決まります。
登録したい規程数と使いたいシステム(コース)がマッチしているかは、重要なポイントです。
さらに、近年法改正に伴って必要な規程が増え、増加傾向にあります(例えばハラスメント、有給休暇、定年など)。ある程度余裕をもったコースとし、将来的な拡張性も視野に入れたものを選定しましょう。
拡張性は、その拡張度合いもさることながら、改修費用も確認しておく必要があります。
操作性とユーザーインターフェースの使いやすさ
規程は参照されてこそ意味がありますので、ユーザーにとって見やすさ、使いやすさは非常に重要なポイントです。
規程の参照のされ方には2種類あります。
管理者(規程作成者、改廃権限者、法務など)からの参照と、適用される側(多くは従業員)からの参照は、場面や用途が異なります。
管理者からのインターフェースを重視するのであれば、規程作成機能が充実していたり、社内業務フローと接続しやすかったりするものを選ぶことになるでしょう。
他方で被適用者からのインターフェースを重視するのであれば、閲覧機能や検索機能を重視することになります。
企業や業態によって、どちらのインターフェースを重視するかは変わります。
セキュリティ対策とアクセス制御の堅牢性
規程管理は、例えば顧客情報と比べるとセキュリティの必要性が落ちるため、疎かになりがちです。
ただ、規程には、社内の重要な情報(賃金体系や組織運営など)も含まれており、一定のセキュリティ対策は必要でしょう。特に、規程に限らず社内情報の漏えいは、コンプライアンスに問題があると思われ、社会的信用を失いかねません。
規程管理システムのセキュリティ対策の鍵は、適切な権限設定にあります。
閲覧できる者の範囲を定め、修正できる者の範囲も定めます。例えば一定の役職以上にのみ修正権限を与え、一般従業員は閲覧権限を与えるなど、社内の立ち位置によって権限を変えるのが一般的です。そして、権限設定自体も管理しておきます。
規程管理システムを選ぶ上では、セキュリティ対策が自社とマッチしているかも選別ポイントの1つです。
社内規程の改定時の新旧対照表を簡単に作成
LAWGUEなら、社内規程や関連文書を横断検索しながら改定ポイントを見つけやすくし、改正作業の手戻りを減らせます。新旧の比較・版管理で改定履歴を追えるため、「どれが最新版か分からない」「改定理由が追えない」を防止。法務・人事・総務など部門横断で同じ文書基盤を共有でき、規程運用の効率化とガバナンス向上につながります。
👉 3分でわかる資料を見る
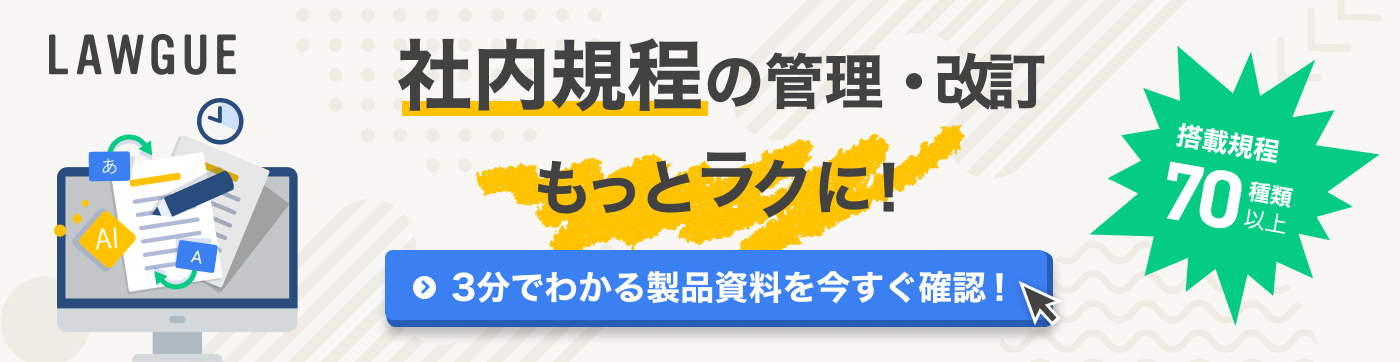
まとめ

今回は規程管理について解説しました。
要点をまとめると次のとおりです。
- 規程管理システムは、社内規程の作成・修正・管理・閲覧などを容易にするシステムのこと。
- 作成・編集機能、履歴保存機能、検索機能など、多様な機能がある。履歴の保存は、法改正に対応する上でも重要。
- 規程管理システムの選定には必要機能の絞り込みとコストの兼ね合いが重要。規程は参照されるものなだけに、インターフェースやセキュリティも重要な要素。
最後に、よくある質問について簡単にお答えしておきます。
よくある質問
規程管理とは何ですか?
一般に、社内規程を作成・修正・管理・閲覧などすることを容易にすることを指します。
現在規程管理というと、デジタルでのシステムによる管理を指すことが多いでしょう。ひな形やアンケート機能によって作成を容易にできたり、改正履歴を保存できたりします。
規定と規程、どちらが正しいですか?
どちらも日本語としては正しく、使い方が異なります。
規定は、個々の条文を指します。他方で規程は条文の集合体である規則そのものを指すことが多いです。
「きてい」管理といった場合は、個々の条文ではなく規則(就業規則、退職金規程など)を管理しますから、「規程」管理と書くのがより正確といえます。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。





