契約書の正しい押印ルールをわかりやすく解説!

契約書に押印することは、日本のビジネス文化に根ざした重要な慣習です。印鑑を押すことで、当事者間の同意を明確に示し、法律上の効力を補強します。
本記事では、なぜ押印が必要なのか、その法的な背景と印鑑の種類、押印すべき場所、失敗した際の対処法まで丁寧に解説します。初めて契約書にかかわる方にも安心してご活用いただけるよう、条文・判例に基づいた実務的な情報をお届けしますので、ぜひお読みください。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書に押印はなぜ必要なのか

契約書があると、当事者間の意思表示の存在が明確になりますし、だからこそ契約書を作成するのですが、その前提としては、当事者がその内容を承諾したといえることが必要です。日本の民事訴訟法においては、二段の推定といって、裁判になった際、押印があることによって、契約の有効性が推定されると考えられています。
当事者の同意を明確にするため
契約書というのは、契約の際の当事者の決め事を紙にまとめたもので、確かに、取引内容の明確性を保つ上で欠かせないツールです。
しかし、いくら契約書があったところで、当事者がその内容を認識し、同意していたのでなければ、まったく意味がありません。
押印は、署名と同様に本人がその内容に同意したことを視覚的に示す行為です。日本では署名よりも印鑑が慣習的に用いられてきたため、押印には固有の信頼性がありますし、当事者の押印があることにより、見ただけで誰に対してもその当事者の同意が明確になるというメリットがあります。
二段の推定の効果のため
二段の推定とは、民事訴訟において、契約書などの私文書に押印がある場合、その文書が本人の意思に基づいて作成されたと推定する考え方です。
具体的には、まず、実印による押印があれば、通常、実印は大切に保管され、本人以外の者が押すとは考えられません。そのような慣習から、それが本人の意思によるものと事実上推定されます(一段目の推定)。
次に、本人の意思による押印があることで、民事訴訟法228条4項に基づき、文書全体が本人の意思で作成されたと法律上推定されます(二段目の推定)。この推定により、文書の成立の真正が証明されたとみなされ、どちらかの推定を覆すような特段の事情がない限り、契約書が当事者の意思を反映したものであるとされます。
押印がない契約書の効力は?

民法上は契約書すらなくても口頭でも契約が成立したとされるので、署名押印も必ずしも要件とはされていません。しかし、実際に契約の存在を立証できるかは別問題です。押印がない以上、別の方法で、当事者が契約をしたと立証する必要があり、押印済みと比べて裁判所での認定が難しくなります。
しかも、契約書に押印がされていないということは、むしろ、あえて契約書の案を作成していながら押印しなかった→何らかの事情で結局契約しなかったのでは、ということを推認させてしまい、かえって不利な証拠になる恐れすらあります。
したがって、押印がないからといって直ちに無効というわけではないものの、実務上は、ちゃんと押印まで済ませることが強く推奨されます。
最新版の契約書を「探せる・確認できる」状態に
締結された最新版の契約書は、あとから内容や条文を確認する場面が意外と多く発生します。
LAWGUEは、契約書を一元管理し、条文単位で検索・整理できる環境を整えます。
👉 3分でわかる資料を見る

契約で使われる印鑑の種類

契約書で使われる印鑑には、①実印、②認印、③銀行印、④社印、⑤代表者印と用途別に複数種類があります。印鑑の法的な効果や組織的な承認体系に応じて使い分けましょう。
①実印
実印は市区町村役場に登録された印鑑で、契約時に印鑑登録証明書を添付すれば、押印が実印によるものであることを甲的に証明することができるので、強い証明力があります。
例えば不動産売買やローン契約、医療同意書など高額・重要契約で広く使用されます。
単に印鑑が本物であるというだけでなく、実印の押印は、それだけ重要な契約です。それを認識して慎重に契約したはずであるとも言えますので、意思表示の真意を明確にする要素として重視され、裁判でもその有効性が強く推定される傾向にあります。
②認印
認印は日常的な業務や軽微な契約書、社内文書などで使用されます。法的効力は実印より弱いものの、取引慣習上は「同意済み」を示す証しとして機能します。
メールや口頭確認などほかの意思表示と組み合わせることで、軽微な契約でも一定の証明力を担保できます。ただし、実印と違って印鑑登録証明書がないため、公的証明力は低い点に留意が必要です。
③銀行印
銀行印は金融機関との取引に用いられる印鑑で、口座開設や振込依頼書の提出などに必要です。契約書で使用されるケースは稀ですが、銀行との、金融取引に関連する契約(融資契約など)の添付に使われることがあります。
銀行印によって資金移動に対する正式な承認が付されるため、実務上は金融機関からも信頼性が支持されています。
④社印
社印は法人の正式な印鑑で、会社実印のほか代表者印の区別もあります。契約書に社印が押されることで「法人としての意思決定」を示し、取引先に対して法人格としての承認力を伝えます。
代表者ではなく、取締役会決議や委任を受けた担当者が押すケースもありますが、押す場所や権限の有無は社内規程によって管理されるのが一般的です。
⑤代表者印
代表者印は会社の代表者の印鑑で、法人登記の代表者氏名部分などに押印します。契約書上で代表者の押印があることで、法人だけでなく代表者個人の意思も明確になります。
判例では、代表者印押印は「法人意思と代表個人の意思が一致した」と見なされ、契約の確実性や法的構成の強化要素とされています。
契約書にはどの印鑑で押印する?
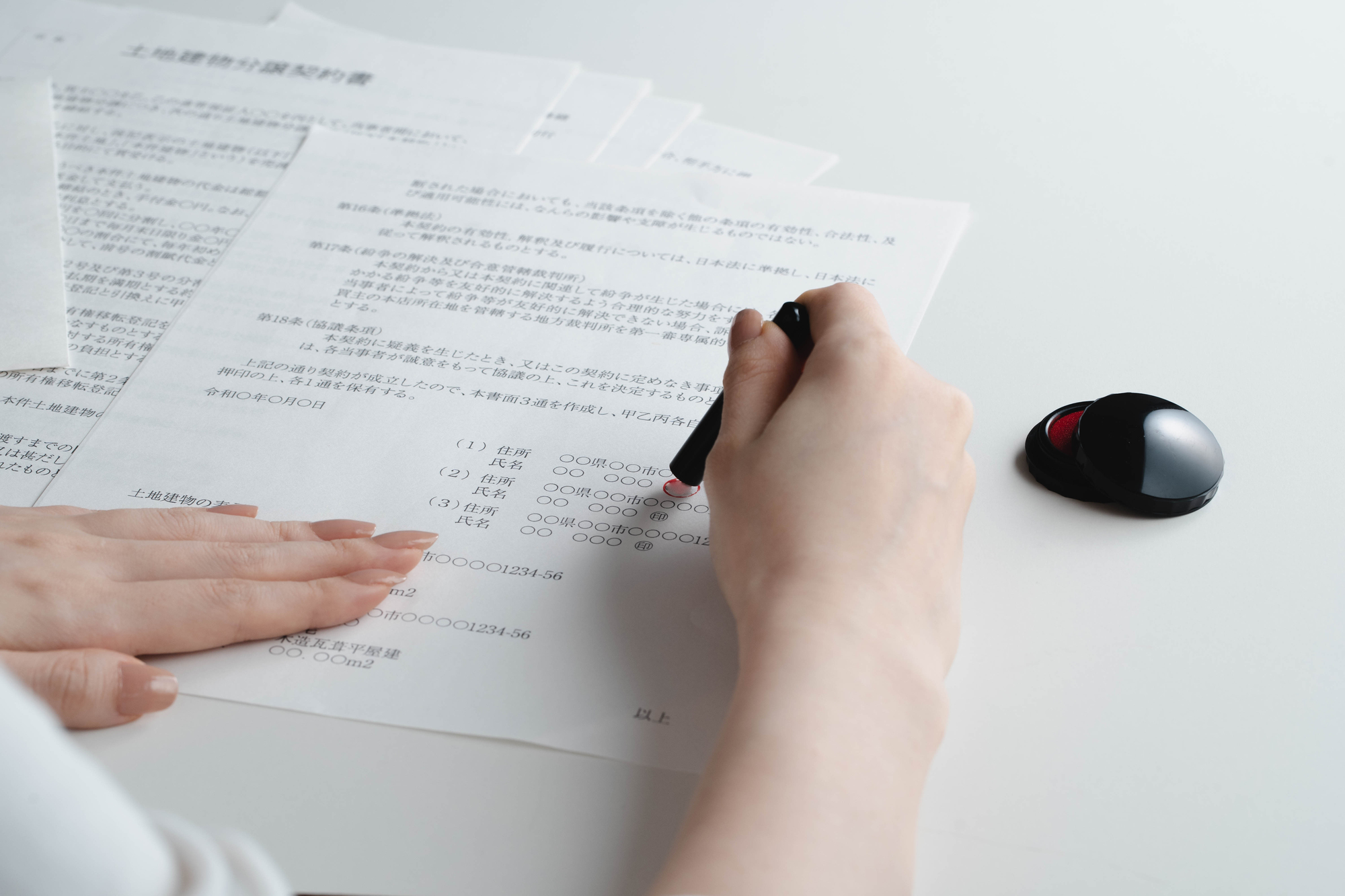
契約書に押す印鑑は契約の内容と重要性によって使い分けます。
高額・法的拘束力重視(不動産・売買・融資など):実印+印鑑登録証明書。
日常的な取引(業務委託・請負・秘密保持契約など):社印または代表者印で代替するのが一般的です。ただ、日常的な取引といえども、金融機関や公的機関に提出する場合には、実印であることが求められる場合もあるので、注意しましょう。
軽微な契約・社内文書:認印で十分です。ただし、取引先から社印の押印を求められた場合は、取引先の都合もあるので、社印に切り替えましょう。
このように、契約書の性質に応じ、法的証拠力や取引相手の信頼に合う印鑑選びが重要です。
契約書で押印が必要な場所
契約書には複数の押印箇所があり、用途によって使い分けられます。主に、①契約印(署名捺印)、②消印、③契印、④割印、⑤訂正印、⑥捨印、⑦止印の7種類です。
①契約印(署名捺印・記名押印)
契約当事者が自署または記名し、印鑑を押す箇所です。自署と押印が両方あると強い意思表示になりますが、記名+押印でも十分な効力があります。
署名はペン書き、記名には法人名・代表者名を書き、押印は上記の実印・社印・代表者印など取引内容に応じたものを利用します。
ここがもっとも重要な部分で、当事者が契約内容を了承した証拠となります。特に法人契約では、複数当事者(双方)の署名捺印が求められるのが一般的です。
②消印
契約書に収入印紙を貼る場合、当然のことですが、過去の契約書に貼った収入印紙を剥がして再利用することは許されません。そこで、契約書に印紙を貼った場合、印紙税法8条2項(「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」)に基づき、その契約書が再利用されることのないよう、消印を大洲必要があります。具体的な方法としては、契約に用いた印鑑で押すのが原則です。
しかし、代表者・使用人・そのほかの従業者などの氏名、名称、役職などが入った印章であれば、比較的幅広く許容されています。
いずれにせよ、これを忘れると、後で懈怠税を受ける恐れもあるので、注意が必要です。
③契印
契印(けいいん)とは、2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印章のことです。通常、契約印は、最終ページにのみ押され、ほかのページには押されていません。そのため、契約書全体に押印の効力を及ぼそうと思ったら、ページが複数であってもそれが押印の際に一体の文書であったということを証明できるようにしておく必要があります。
契印が両ページにまたがって押印されていることにより、後日、ページが飛ばされたり、逆に差し込まれたりしているのではないかとの疑いが生じることもあるでしょう。その場合でも、両ページの契印を合わせることで1つの印鑑の印章になるかどうか確認することで、ページが連続しているかを確認することができます。
④割印
割印は、2つ以上の文書にハンコをまたがるように押すことによって、文書の関連性を示すことをいいます。
通常、契約書を作成したら、両当事者ともにそれを保管します。そのため、通常契約書は2通以上作られるのですが、たとえば、甲・乙双方が同じ契約書を各1部ずつ保管する場合、契約時に、双方当事者が確認の上、コピーの表紙付近に割印を押すことで「これは同じ文書である」と明示され、原本と写しの整合性が担保されます。
割印に用いる印鑑は普通の社印・契約印または代表者印で十分です。しかし、重複押印されるため、印鑑の大きさ、形状によっては印影が分かりにくいケースもあります。そのため、割印用に小型の印を別途用意する企業もあります。
⑤訂正印
訂正印は、契約書に誤記や誤植があった際、横線などで訂正し、そのそばに押す印鑑です。訂正時には当事者全員が訂正箇所に押すことで、誤読や改ざんの疑念を排除します。
重要なのは、「二重線」「訂正文字」「訂正印」の3つを組み合わせて、後から都合よく書き換えられる可能性を実務的に防止することです。
判例でも、訂正印が押されていない訂正文書は「当事者が同意して訂正したとの明確な証拠がない」として、無効または効力を否定された例があります。
⑥捨印
捨印は、担当者が押印し、万が一の訂正や追記が後からあった際に、当該内容も承諾したことを示すものです。印鑑を押しておくことで、小さな誤字脱字の修正をスムーズにおこなうことができます。
しかし、捨印を巡っては、その、相手にこちらに断りなく訂正することを許すという性質上、後に、予期していなかった修正がされるなどしてトラブルになるケースも有り、トラブル回避という観点からは、安易におすすめできるものではありません。捨印を押すにしても、「軽微な修正に限る」など但し書きをつけておくほうがより良いと言うべきでしょう。
⑦止印
止印は、契印や割印とは異なり、ページや文書の最終部に「ここで終了」の意味を込めて押す印鑑です。署名欄や押印欄の最後尾に用いられ、文書終端を明示します。
契約書を作った際、レイアウトなどの関係で最終ページの下部に余白ができることはどうしても避けられません。
そういうとき、そこを何もせず空白のままにしておくと、後日、その部分に加筆して契約書を改ざんすることができてしまいます。
押印を失敗した場合の対処法
押印を失敗した際、一度作った契約書を破棄して一から作り直すのだと余分な手間がかかりますし、もし先に印紙を貼ってしまっていたりした場合には、破棄して作り直すと余分な印紙代までかかってしまいます。そのため、押印を失敗した場合の訂正の方法も知っておくことが必要です。
契約書で押印する際、場所を間違えた場合は、誤って押した印影に二重線を引き、その上から同じ印鑑を被せて押印し、正しい位置に再度押印します。印影が擦れたり欠けたりしたときも同様に二重線と訂正印を押し、隣に鮮明な印影を押し直さなければなりません。
印鑑の種類を誤った場合も、間違えた印影を二重線で抹消し、その上から誤印鑑を被せて押印した上で、正しい印鑑を隣に押す必要があります。ただし、二重線のみでの修正は当事者以外でもできてしまい信頼性が低下するためNGです。
また、やりがちですが、かすれた印影に重ね押しするのも推奨されません。特に実印の場合は厳密な照合が求められるため、押印ミスがあった際は、再作成や再押印も含め慎重に対応してください。
最新版の契約書を「探せる・確認できる」状態に
締結された最新版の契約書は、あとから内容や条文を確認する場面が意外と多く発生します。
LAWGUEは、契約書を一元管理し、条文単位で検索・整理できる環境を整えます。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
契約書の押印は、日本におけるビジネス契約の証拠力・成立性を担保する重要な慣習であり、法律上の推定を働かせる大きな要因です。実印や社印、代表者印などを用途に応じて使い分け、契約印・契印・捨印など複数の印鑑位置を正しく押すことで、後日の争いを防ぎます。押印ミスがあった場合には速やかに修正する必要もありますので、契約書作成時には丁寧な確認が不可欠です。安心・安全な契約書の運用を目指しましょう。
よくある質問
契約書に押す印鑑はどれですか?
契約書に押す印鑑は契約内容や重要性によって変わります。
不動産取引など高額なもの、法的拘束力重視するものは実印を使用します。
日常的な取引では、社印もしくは代表者印を使用します。
軽微な契約・社内文書は認印を使用します。
実印が最も証明力が高いので、全部の契約書に実印を押せばいい、と思いがちですが、それをしてしまうと、実印の管理に問題が生じたり、他の押印手続きで使っていて速やかな押印ができないなど、別の問題が生じかねません。
押印をする前に契約内容について確認し、誤りのないよう印鑑を準備しましょう。
契約書に押印するとき、甲印と乙印の位置は?
甲印と乙印の位置について法的な決まりはありませんが、一般的には甲印を右側、乙印を左側に押印します。
あくまでも慣例によるもののため、誤って乙印を左側に押印してしまっても法的拘束力がなくなる、といったことは起こりません。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








