法務DXとは何?メリットと実践法で業務改革【徹底解説】

日本でDXが一般化したのは、おそらく2018年の経済産業省のDXレポートからでしょう。
デジタル技術による企業改変がうまくいかなければ2025年からは年間12兆円もの損害が発生するという、当時は衝撃的なレポートが出されました。
これを受けてさまざまな業界でDXの必要性が叫ばれてきましたが、近年法務分野においてもDXの重要性が説かれるようになりました。
今回は、法務DXについて解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
法務DXとは?定義と概要

「法務DX」といっても、統一的な定義はありません。
経済産業省は、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」を「データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと」「そのためにビジネスモデルや企業文化等の変革に取り組むこと」としています。
法務DXは、法務分野におけるDX、すなわち「法務領域においてデータやデジタル技術を使って、新たな価値を創造し業務改革をしていくこと」と捉えることができます。
従来、法務は紙が基本でした。契約書をはじめ、あらゆるものを紙で作成・決裁・保存などをしてきました。ここにデジタル化の視点を取り入れようというのが、法務DXのスタートとなります。
法務業務のデジタル化とは何か
契約書を例に考えてみましょう。
紙の契約書を締結する際、条項の調整→契約書の作成(捺印・郵送・返送)→履行→保管→更新といった工程が発生します。
このうち、デジタル化による恩恵があるのは、契約書の作成段階と契約書の履行~更新段階です。
いわゆる電子契約書に移行すると、電子署名とタイムスタンプによってオンライン上で完結することになります。つまり、捺印のために出社することもなくなり、互いに郵送し合うこともなくなるのです。
また、電子契約サービスにより電子契約書を管理することで、履行タイミングの把握(不履行の場合の早期発見)ができますし、保管に場所を取ることもありません。更新時期もアラームの設定により忘れずに把握することができます。紙であれば、契約書へのアクセスに時間がかかり、時期の把握も難しく、保管コストもかかりますが、これらが大きく改善されることになります。
従来型法務部門からの脱却ポイント
従来の法務部門のどのような点が、法務DXによって変わっていくのでしょうか。
従来型の特徴であった属人性・アナログ・非迅速性の3点から考えていきます。
- 属人性
まず、従来型は職人的な法務部によって成り立っていました。どこに契約書があるのかから始まり、過去の同種事案の経験や検索も、ベテラン法務部に頼っていたといえます。
法務DXを取り入れても、法務経験の重要性は変わりませんが、少なくとも契約書の管理・検索など、外部記憶に頼ることができる分野については、「誰がやっても同じような成果が期待できる」ようになります。 - アナログ
法務部門の核となる契約書自体が紙を原則としていたため、決裁・署名捺印・ファイリングなど、あらゆる場面で紙が使われていました。
先の例のとおり、電子契約書を利用すれば契約書の作成・管理の場面で紙が不要になります。システムによっては、在宅勤務とも親和性が高くなるでしょう。 - 非迅速性
法務部門は、リスクを探知する役割を担うことが多く、どうしてもネガティブな判断になり、企業活動の足枷的な立場になりがちです。また、判断の内容だけでなく判断を出すまでの時間もかかりすぎるという問題がありました。
法務DXをおこなってもリスク探知の役割は変わりませんが、判断を出すまでの時間の短縮や意思決定の明確性が向上します。それによって、満足度の高い法務チェックが可能になります。
法務DX実現のための 3 つのステップ
法務 DX の導入は、主に①導入前の段階、②導入時の段階、③導入後の段階に分けられます。
①導入前の段階
現状把握と目標設定の 2 つに分けられます。
まず、現場からのヒアリングや業務フローを可視化して、どこに課題があるのかを把握します。
例えば、「関連する契約書の発見に時間を要している」「その結果契約書の法務チェックに 2 日以上かかっている」などの具体的な課題を見出すことが重要です。
その上で、法務DX導入によって何を達成したいか、目標を設定していきます。
例えば、「契約書の法務チェックの時間を半分にする」などの目標を策定します。
②導入時の段階
次に、①で設定された目標にあわせて、ツールの選定をおこないます。
ツールの選定においては、目標達成に有効であるかどうかに加え、使いやすさ、セキュリティ、コストなどの面も含めて決定していきます。
例えば、契約書の検索機能などに強いツールを選ぶのがよいでしょう。
③導入後の段階
導入後は、定期的に効果を検証します。
カスタマイズが必要なときもあれば、業務フローを再検討する必要もあるときもあります。
AIが“考える”ではなく、あなたの判断を支える「法務パートナー」
LAWGUEは、契約書レビューや規程管理に必要な比較・修正・条文検索をAIが支援。
自社ナレッジと外部情報を組み合わせ、常に正確で最新の判断を後押しします。
人の経験を活かしながら、レビューの質とスピードを両立。
👉 3分でわかる資料を見る
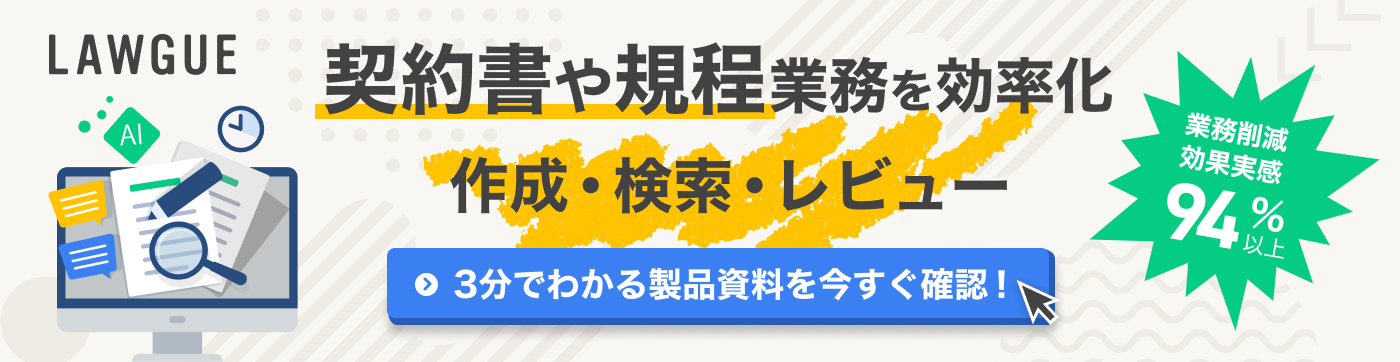
従来の法務業務における課題

上記①導入前の段階における「現状把握と目標設定」について、さらに具体的にみていきましょう。
法務業務における現状課題として、以下の3つがよく挙げられます。
- 契約書管理のコストや煩雑さとリスク
- 属人性が強いことによる非効率性
- ボトルネック問題
これらすべてを法務DXで解決できるわけではないですが、業態によっては大きく改善可能です。
以下、1つずつみていきます。
契約書管理のコスト・煩雑さ・紛失リスク
紙の契約書の場合、締結が終われば当然ながら紙の契約書が手元に残ります。要件を満たせばスキャナ保存も可能ですが、原本性を考えると紙の契約書を廃棄するという選択肢は取りにくいでしょう。
紙の契約書は、経年劣化します。日焼けで変色したり、文字がかすれたりします。温度や湿度を管理しなければなりません。
専用のキャビネットや部屋を用意している企業も多いですが、企業によっては契約書が分散しているところもあるでしょう。1つのキャビネットに入っていたとしても、ファイリングがうまくできていないと、やはり見つけるのは困難です。
このように、契約書の管理には大きなコストがかかります。
さらに、持ち出しについて、施錠したりルールを作ったりして制限している企業も多いでしょう。持ち出しに決裁を要するようにすればセキュリティは保てますが煩雑さは残ります。ルーズに管理されている場合も多いはずです。
ルールに則って持ち出したとしても、紛失や汚損のリスクがなくなるわけではありません。ましてや無断で持ち出された場合には、リカバリーができなくなります。
電子契約サービスを導入することで、保管・検索がしやすくなり、紛失・汚損のリスクをなくすことができます。
属人的な業務プロセスによる非効率性
管理が煩雑であるために、契約書や該当条項がどこにあるのかがベテラン法務にしか分からないという企業も多いでしょう。
「似たような契約は昔あったような気がする」「同じようなトラブルが昔あったような気がする」と、記憶の片隅にあるものについて、法務部に丸投げして見つけてもらった経験がある方も多いかもしれません。
このように、紙ベースでの蓄積は、えてして経験による検索を必要とします。
電子契約サービスの導入で全文検索ができるようになれば、ある程度属人的な検索から解放されます。
また、紙の契約書の場合、契約書チェックにも職人的な作業を必要としていました。
似たような条項を見つけてきて修正し、抜けがあれば加筆します。
ただ、どうしても人の目でチェックしますから、見逃しや誤った指摘もあり得ます。
AI契約書レビューを使えば、まだまだ不完全ではありますが、リーガルチェックのサポートになり、若干属人性から解放されます。
リーガルチェックのボトルネック問題
法務部が充実している企業は多くありません。多数の企業では専門の法務部がないか、1人ないし数人の法務部で構成されています。
さらに、法務部所属が数人いたとしても、総務や人事と兼任していることが多く、業務の多さに比べて十分なリソースを投入できていないのが現状です。
企業活動ではあらゆる場面でリーガルチェックを必要とします。取引先との関係では契約書チェック、人事であれば労務関係のチェック、法改正への対応、総務からはテナントの契約から備品のトラブル対応、顧客からはクレームが発生して訴訟対応を迫られるときもあります。
こうした数多のリーガルチェックを、少ない人数でおこなうわけですから、どうしても時間がかかってしまいます。
ときに、企業活動を止めてしまう要因にもなるでしょう。
電子契約サービスやAIレビューを使うことで、煩雑な業務から多少解放され、より集中的に対応すべき顧客対応などに注力できるようになります。
法務DXで得られる3つのメリット

改めて法務DXで得られるメリットを整理してみます。
最初に述べたとおり、法務DXの出発点はデジタル技術とデータの活用です。
デジタル技術により、保管・検索などの面で効率化が図られ、後回しになりがちだった本質業務に取り掛かれるようになります。
また、データ活用によって、過去のトラブルや予想されるリスクを把握することができ、対応策を検討できます。
さらに、いわゆる攻めの法務として、意思決定のサポートができるようになります。
これらを整理すると、法務DXで得られるメリットは以下の3つに整理できます。
①業務効率化(それによる本質業務への集中)
②リスク可視化と対応策の策定
③データから得られる企業価値の向上(意思決定支援と経営貢献)
以下、それぞれ説明していきます。
業務効率化による工数削減と本質業務への集中
電子契約を例に考えてみましょう。
紙の契約書の準備から保管までは、通常条項の作成→製本→郵送・返送→保管という流れになります。
製本のためには、原本の通数分出力し、それぞれに署名押印し、必要に応じて契印をしなければなりません。課税文書であれば印紙を貼ります。
それぞれ割印で繋ぎ、脱落などがないことを確認する必要があります。
来社でない場合は先方に郵送し、捺印と返送してもらうことが必要です。
返送してもらった契約書に捺印漏れなどのミスがないことを確認し、契約書用ファイルにファイリングします。
一方で、電子契約にすれば、まず製本の手間がなくなります。出力の必要もなく、捺印の必要もありません。何ページにわたったとしても契印は要りませんし、原本が何通あっても割印も印紙も不要です。
できあがった電子データを紙へ出力して郵送する必要もありません。データとしてやりとりをし、先方から電子署名とタイムスタンプがもらえれば、やりとりは完了です。
そのまま電子データとして保管すれば足ります。
削減できた製本・郵送の工数は、より重要な業務に振り分けることができます。例えば契約実行の10日前に製本まで終わらせていたなら、製本・郵送の手間がなくなるので10日間かけてじっくり条項を調整できるようになります。
早く業務が終わることで、別の契約書チェックにも手を付けられるかもしれません。
リーガルリスクの可視化と予防的対応の実現
リーガルリスクには多様なものが存在します。例えば取引の相手方の信用問題、知的財産権の侵害可能性、製造物責任、法令違反による行政処分などです。なかでも本記事では契約書レビューにひそむリーガルリスクの可視化について説明します。
契約書のリーガルリスクは、いくつかの類型に分類されます。
- 記載された条項に当方への不利になる条項が含まれている場合
- 記載されていない条項があるために、当方に不利になる場合
- 法改正に対応できておらず、将来的に契約が無効になるなどのリスクが潜在化している場合
現在のAIレビューでは、不利な条項や抜け漏れの条項を指摘してくれます。
サービスによっては、どうして不利なのか、代替案はどうかまで提示してくれる AI もあります。
契約締結前に、不利な条項や抜け漏れの条項を発見でき、ときには解決策まで提示してくれるのです。
法改正まで目配りしたAIレビューは難しいかもしれませんが、法務部が人の目でチェックする余裕が生まれ、法務部は最新法改正の学習やそれの反映に注力することができます。
データに基づく意思決定支援と経営貢献
法務は基本的に慎重な判断を下す傾向があり、前向きな経営判断には必ずしも結びつかないと考えられてきました。
ただ、データ活用によって、意思決定支援が可能になりつつあります。
- DD(デューデリジェンス)分野におけるデータ活用
DD分野では、膨大な経営データや財務情報などを読み込み判断する必要があります。データ分析をAIにゆだねることで、より根本的なリスク把握に時間を使うことができます。
DDが早くなれば、M&A全体も意思決定を早くすることができます。
社会情勢や国際情勢の変化で時機を逸することが増えてきましたが、意思決定のサポートによって時機を捉えた判断が可能になります。 - クレーム分析による経営改善
多数の顧客を抱える業態では、不可避的にクレーム対応に追われます。
従前単発的に対応してきましたが、データ蓄積によってより根本的な原因を発見し、対応することが可能になります。
クレームの原因は、契約書・約款の問題かもしれないですし、製品・サービスそのものの問題かもしれません。あるいは主要取引先のコンプライアンスレベルによるものかもしれません。
こうした分析ができれば、契約書・約款の修正、サービス改善、取引先の変更など、具体的に経営改善に向けた方策を立てられるようになります。
法務DXのためのリーガルテックの種類と選び方

法務DXの重要性について説明してきました。
ただ、現在リーガルテックは無数にあり、1つの技術にも複数の商品があります。どう選べばよいのでしょうか。
主なリーガルテックは以下のとおりです。
- 電子契約サービス
- 契約書レビュー支援
- 契約書・案件管理
- 支援サービス(リーガルリサーチ、知的業務支援など)
導入すべきリーガルテックを選定するには、導入前の段階で課題を把握していることが重要です。紙の契約書がネックになっているなら電子契約サービスと契約書・案件管理を組み合わせることが考えられます。膨大な契約書チェックがネックになっているならレビュー支援に強いものを導入するとよいでしょう。
それぞれ複数の商品があり、カスタマイズの必要性や導入コスト・ランニングコストの兼ね合いもあるでしょうから、試験的に導入して比較するというのも手かもしれません。
電子契約システム導入のポイント
リーガルテックの代表格である電子契約を例に、導入するときのポイントを考えてみます。
①どのような課題があるか
先に述べたとおり、まずはどのような課題があるか、洗い出しをします。
大きく分けて、以下のような課題が考えられます。
- 問題は契約書作成だけか。保存・管理まで含めて対応すべきか
- 過去の契約書も一元管理が必要か
- 多言語に対応できるか
②かけられるコストはいくらか(導入する範囲をどうするか)
続いて、かけられるコストを算出します。導入コストだけでなく、ランニングコストもかかるため、スモールスタートのほうがよいのかなども考えていきます。
また、全社対応にするのか、チームを限定するかなど、導入する範囲も含めて検討しましょう。
③取引先との関係やセキュリティはどうか
電子契約書には当事者型と立会人型があり、方式が異なります。
そのほか、例えば取引先に官公庁がある場合など、セキュリティを重視しなければならない場合もあります。
取引先との関係などで導入できるシステムの選択肢が狭まる可能性もあるでしょう。
以上の①~③を検討して、導入すべきシステムの絞り込みをおこないます。
文書管理に強いか、紙の取り込みに強いか(紙の保管サービスと組み合わせることも考えられます)、多言語対応しているかなどの要素から、コスト的に自社に合ったシステムを選びましょう。
導入したら、それで終わりではありません。利用者にヒアリングをし、使い勝手が悪ければカスタマイズをしたりシステムを変更したりします。
AIが“考える”ではなく、あなたの判断を支える「法務パートナー」
LAWGUEは、契約書レビューや規程管理に必要な比較・修正・条文検索をAIが支援。
自社ナレッジと外部情報を組み合わせ、常に正確で最新の判断を後押しします。
人の経験を活かしながら、レビューの質とスピードを両立。
👉 3分でわかる資料を見る
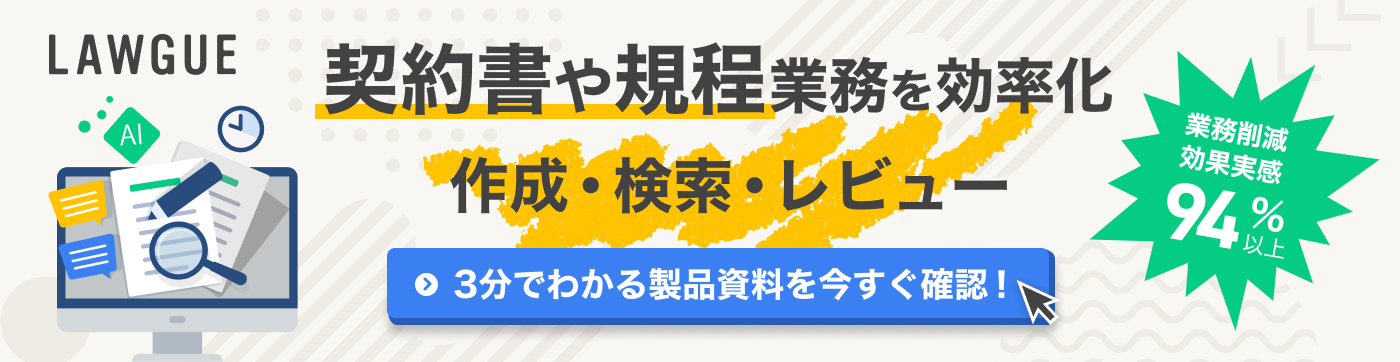
まとめ
今回は、法務DXを解説しました。
要点は以下のとおりです。
- 従来型の法務は、属人的であったりアナログであったりと、非効率な部分が多かった
- デジタル技術やデータの活用で、非効率な部分が改善され、業務効率向上が期待される
- リスクの可視化により、リスクが顕在化する前に予防策を立てられるようになる
- 意思決定のサポートができ、攻めの法務が実現できる
- 導入に当たっては、事前の課題把握が重要
法務DXはようやく導入が始まったところで、まだ多くの可能性を残しているでしょう。
DXの力を借りて、より効率のよい効果的な法務が実現することを願っています。
以下では、よくある質問について簡単にまとめておきます。
よくある質問
法務業務のDX化とは何ですか
多義的ではありますが、デジタル技術やデータの活用を通して、法務分野の業務改革をおこなうことです。
典型例としては、紙のもの(契約書など)を電子データ(電子契約書など)に変えていくことがあります。
法務DXを導入するメリットは何ですか?
まずは業務効率化です。電子データにすることで、保管・検索が容易になります。
また、データを活用することでリスクを把握しやすくし、意思決定の速度を上げることで経営にも貢献します。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








