契約書を電子化する方法とは?紙の契約書との違いやメリット・デメリットを解説
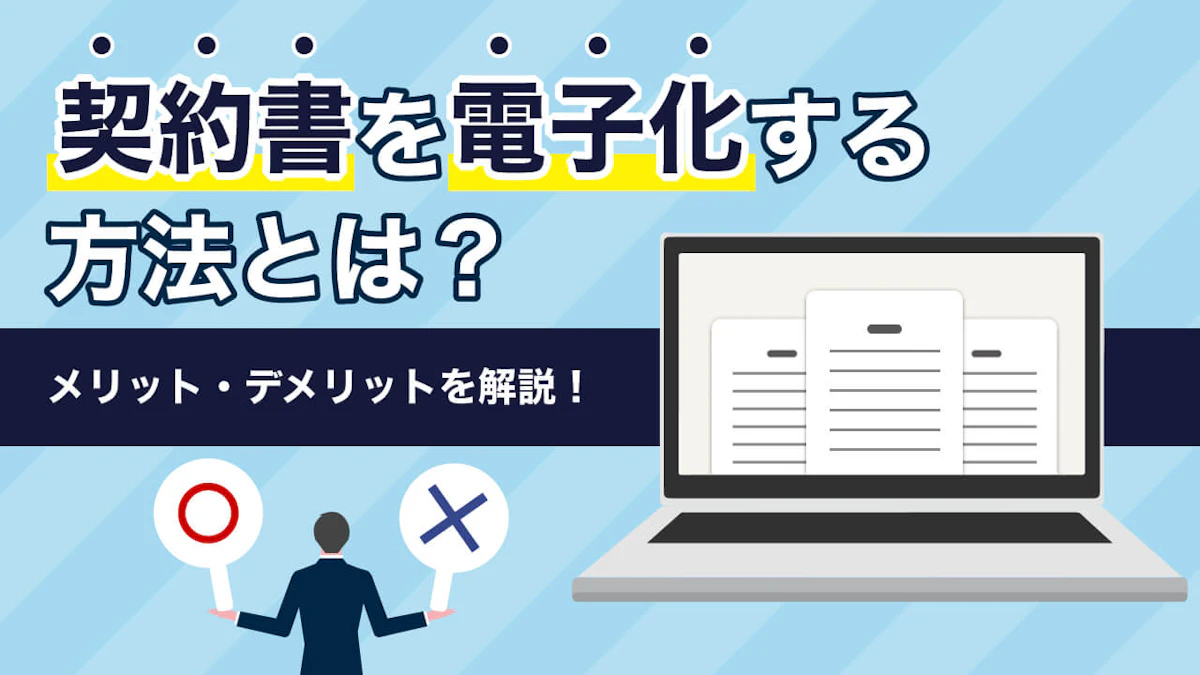
契約書の電子化は、ビジネスの効率化やコスト削減において重要であり、さまざまな企業が電子化の導入を進めています。
本記事では、紙の契約書と電子契約の違いやそれぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、電子化を進めるための具体的な手段や社内体制の構築方法についても紹介します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
電子契約と紙の契約書の違いとは?

契約書の電子化が進む中で、従来の紙の契約書と電子契約の違いを理解することは不可欠です。署名方法や証拠力、契約締結後の保管・管理にも違いがあり、それぞれの特徴を把握する必要があります。
署名方法
紙の契約書では、契約当事者が直筆の署名または押印を行うことで、本人の意思による締結であることを示します。日本では長年にわたり、印鑑による証明が法的にも社会的にも重視されてきました。特に実印と印鑑証明書の組み合わせは、強い証拠力を持ちます。
一方、電子契約では、電子署名やタイムスタンプが署名の役割を果たします。特定の電子署名(公的個人認証や商業登記に基づく法人署名等)は、法的にも本人確認・改ざん防止の機能があるとされています。民間の電子契約サービスでは、メール認証やワンタイムパスワードを使う方式もあり、利便性と法的有効性を両立しています。
したがって、紙の署名は「形としての証拠」が重視され、電子署名は「技術的証明とログ記録」が重視される点に違いがあります。
締結日時の証明方法
紙の契約書では、契約日を記載し、その日付を信頼の根拠とするのが一般的ですが、実際の締結日と異なることもあり得ます。証拠力を補強するためには、契約締結後に公証役場で確定日付を取得する必要があります。
電子契約では、電子署名とタイムスタンプにより、契約が「いつ」「誰によって」締結されたかを明確に記録できます。システム上の操作履歴も残るため、改ざんリスクの低減と締結日時の証明性が高いのが特徴です。
契約内容の受け渡し方法
紙の契約書では、原本を郵送や手渡しで交換する必要があります。そのため時間と手間がかかり、紛失リスクもあります。
電子契約では、クラウドサービスを通じて契約書を共有・保存でき、即時に内容を相手方に届けることができます。契約当事者が同じプラットフォームにアクセスし、ワンクリックで締結できるなど、効率的なやり取りが可能です。
契約書を電子化する手段とは?

契約書の電子化には、単純にPDF化する方法から、クラウド型の契約書管理システムを導入する方法まで、複数の選択肢があります。それぞれの手段の特徴を理解しましょう。
紙の契約書をPDF化して電子保存
最も簡易な電子化方法は、既存の紙の契約書をスキャナなどでPDF化し、電子ファイルとして保存する方法です。これにより、書類の物理的な保管スペースを削減し、検索性や共有性も向上します。
電子帳簿保存法に対応する形で保存する場合には、一定の条件を満たす必要があります。たとえば、真実性の確保のためのタイムスタンプ付与や訂正・削除履歴の記録、見読性の確保、検索性の確保などが求められます。
単なるPDF化では法的な証拠力が弱くなる可能性があるため、重要な契約書は電子署名付きで保存するか、保存方法について税理士や弁護士の確認を受けることが望ましいでしょう。
作成した契約書をPDFに変換して電子署名を付与
Wordなどで作成した契約書をPDFに変換し、そこに電子署名を付与することで、電子契約書としての体裁を整える方法です。電子署名には、一般電子署名と特定電子署名がありますが、特定電子署名のほうが法的効力が高くなります。
Adobe AcrobatやDocuSignなどのツールを使えば、簡単に電子署名を施し、タイムスタンプの付与も可能です。この方法は、紙のやり取りを省略でき、契約締結までのスピードを大幅に向上させます。
ただし、当事者双方が電子署名の有効性を理解し合意している必要があります。
契約書レビューを自動化する
AI契約レビューソフトを利用すれば、契約書の条項チェックやリスク抽出を自動化できます。例えば、定型業務委託契約における損害賠償条項や秘密保持条項の不備を即時に指摘することができます。
AIによる契約書チェックツールを活用することで、法務部門の負担を軽減し、スピーディーな契約締結が可能になります。レビューの質も一定のレベルで標準化され、属人化のリスクを軽減できます。
特に中小企業では、法務人員が限られるため、こうしたツールの導入により効率的な契約業務が実現します。
電子契約システムを導入してシステム上で契約
クラウド型電子契約サービスを利用すれば、契約書の作成から送信、署名、保管までをすべてオンライン上で完結できます。
この方法では、相手方も同じプラットフォームを使用することで、契約締結に必要な操作が一気通貫で行えます。また、契約ごとの操作履歴も記録され、証拠性が高まるのも利点です。
特にテレワークや複数拠点での業務が一般化している企業にとって、迅速かつ安全な契約業務が可能となります。
契約書管理システムを導入して契約書を一元管理
契約締結後の文書管理も、電子化によって効率化が可能です。契約書管理システムを導入すれば、契約書の版管理・検索・共有・更新スケジュールの管理を一元化できます。
従来のフォルダ管理では、担当者の異動や属人化により、重要契約の所在が不明になるリスクがあります。一方で契約書管理システムでは、契約日・更新日・満了日などに基づく自動通知機能やアクセス制限機能が備わっており、業務の透明性とリスク管理を強化できます。
また、コンプライアンス強化の面でも有効であり、監査対応の負担も軽減されます。契約情報の活用も容易になるため、経営判断への貢献も期待されます。
契約書を電子化するメリットとは?

契約書を電子化することで、業務効率化やコスト削減、コンプライアンスの強化など、さまざまなメリットが得られます。以下では主な5つの利点について解説します。
契約締結のスピードが向上する
電子契約では、郵送や対面による署名・押印の手間が不要となり、数分で契約が完了することもあります。特に遠隔地にいる相手との契約や、社内承認プロセスが複雑な企業では、電子化によるスピードアップは大きな利点です。
システム上でワンクリックで署名依頼を送信し、相手がそれを確認・承認するだけで契約が成立するため、ビジネスチャンスを逃すリスクも軽減されます。
コスト削減
紙の契約書では、印紙代・郵送費・印刷費・保管コストがかかります。特に印紙税は契約金額によっては高額になり、企業の負担となることも。
電子契約に切り替えることで、印紙税が不要になるケースが多く、コスト削減に大きく貢献します。年間で数百万円単位の経費削減が可能な企業もあります。
また、物理的な保管スペースも不要となり、倉庫コストの削減にもつながります。
契約書の検索・管理が容易
契約書を電子データとして管理することで、過去の契約内容の検索や参照が容易になります。キーワードや契約相手、締結日などでの検索機能を活用すれば、必要な契約書をすぐに見つけ出すことができます。
従来の紙管理では、保管棚を探す手間や、誤って廃棄されるリスクがありましたが、電子化によりこうしたリスクも回避可能です。
コンプライアンス・リスク管理の強化
電子契約は、誰が・いつ・どのように契約を締結したかをログとして記録できるため、監査や訴訟時における証拠性が高まります。また、アクセス制限機能を利用することで、情報漏洩リスクの低減にもつながります。
さらに、契約満了前の自動通知などを活用すれば、契約の更新漏れや無効化といったリスクも防止でき、法務部門の業務を強力にサポートします。
BCP(事業継続計画)対策にも有効
災害やパンデミック等の非常時においても、クラウドベースの電子契約システムを利用すれば、どこからでもアクセス可能で、業務を継続できます。
紙の契約書が社内にしか存在しない場合、出社が困難になると業務が停止してしまいます。
電子契約は、テレワークや分散型ワークスタイルにも対応しており、柔軟な働き方を支える重要なインフラになります。
紙契約の「電子化・整理」から、契約業務を軽くする
LAWGUEは、電子契約そのものを行うツールではありませんが、紙・PDFを編集できるデータにして文書として整理できます。最新版の契約書を検索しやすい状態に整えることで、確認・共有の手間を減らせます。電子化を進める際の“保管・参照の土台”として、バックオフィスの運用を支えます。
👉 3分でわかる資料を見る

契約書を電子化する際の注意点

契約書の電子化には多くのメリットがありますが、注意すべき点もあります。
まず、すべての契約が電子化できるわけではありません。事業用定期借地契約など、法律で書面化が求められている契約類型は、引き続き紙での締結が必要です。
また、電子契約の有効性を担保するためには、相手方の同意や契約プロセスの正確な記録が必要です。双方が電子契約に同意していない場合は無効とされるおそれがあります。
さらに、システムの選定や運用方法にも注意が必要です。電子署名がどの程度の証拠力を持つか、運営会社の信頼性、バックアップ体制、情報セキュリティなどを十分に確認したうえで導入しましょう。
契約書を電子化するための社内体制づくりの流れ
契約書の電子化を成功させるには、単なるツールの導入にとどまらず、社内全体でのルール整備や運用体制の構築が不可欠です。以下に、構築のステップを紹介します。
経営層の承認を得る
電子契約の導入は業務フローの大幅な変革を伴うため、現場レベルでは対応が困難です。まずは経営層が、契約の電子化がもたらすメリット(コスト削減、業務効率化、コンプライアンス強化、DX推進など)を正しく理解し、組織全体の方針として明文化することが重要です。
経営トップが「契約書の電子化を全社的に推進する」ことを明確にし、社内に周知・共有することで、各部門の協力を得やすくなります。また、プロジェクトに予算を割り当てる意思決定も、この段階で行う必要があります。
対象契約の選定
契約の電子化は一気に全契約に適用するのではなく、契約の種類やリスクに応じて段階的に進めるのが現実的です。まずは、以下のような観点から対象を選定しましょう。
- 定型的な内容で契約相手が多いもの(例:業務委託契約、秘密保持契約)
- 印紙税が発生するが電子契約で不要となるもの(例:請負契約)
- 紙のやり取りが煩雑なもの(例:全国に拠点を持つ企業との契約)
一方、公正証書化が必要な契約、実印や印鑑証明が必要な契約などは、電子化の可否や法的制約を確認する必要があります。法務担当者の関与のもと、対象契約をリストアップし、優先順位をつけて進めるとスムーズです。
法務・経理・IT部門との連携
契約に関する法的有効性の判断や印紙税の扱い、システムの導入可否に関しては、法務・経理・情報システム(IT)など専門部門の意見が不可欠です。
- 法務部門:電子署名の種類ごとの証拠力の違いや、契約の有効性、トラブル時のリスクを精査し、社内規程や業務フローを策定。
- 経理部門:印紙税の課税対象かどうか、契約形態の変更に伴う会計処理の見直しが必要かを検討。
- 情報システム部門:導入するクラウドサービスや電子契約システムのセキュリティ、社内ネットワークとの連携可能性を調査。
これらの部門と継続的に連携することで、導入後の混乱やリスクを最小限に抑えることができます。
電子契約サービスの選定
市場には多くの電子契約サービスが存在しますが、それぞれ料金体系、法的対応範囲、機能、UI/UXなどが異なります。
選定にあたっては、以下の観点を重視しましょう。
- 法的信頼性:電子署名法・電子帳簿保存法に対応しているか
- 機能性:複数契約者への同時送信、リマインド機能、更新期限の管理、API連携など
- セキュリティ:通信の暗号化、アクセス権限設定、操作ログの記録
- 操作性:現場スタッフが直感的に使えるかどうか
- コスト:件数課金か月額定額か、初期費用の有無など
実際の契約を使ってみて効果を検証し、自社の業務に適しているかを検証した上で導入を決定します。
運用ルールの整備
電子契約の導入にあたっては、「誰が契約書を作成し、誰が承認し、どのタイミングで送信するのか」など、従来の業務プロセスを再定義する必要があります。
また、社内規程も以下のように見直します。
- 電子契約に関する明文規定の追加(電子署名を正式な署名として認めることなど)
- 電子契約の保存年限、責任者、運用方法に関するルール整備
- 締結済み契約書の改ざん防止や閲覧権限の管理に関するルール
マニュアルやフローチャートの作成も有効です。特に電子契約が初めての現場にとっては、視覚的にわかる資料が重要です。
社員への研修
新しい業務プロセスを円滑に機能させるためには、関係者への研修が不可欠です。契約書の作成担当者、法務担当者、営業担当者など、対象者に応じた研修を実施します。
研修では以下の点を重点的に伝えます。
- 電子契約の基本知識(法的有効性やタイムスタンプの意味など)
- 利用する電子契約サービスの操作方法
- トラブルが起きた場合の対応フロー
- 紙との使い分け判断基準
定期的なフォローアップ研修やFAQの整備により、現場の混乱を防ぎ、定着を促します。
運用後の効果測定と改善
導入後は、定期的にKPI(重要業績評価指標)を設定して効果を可視化しましょう。例えば以下のような指標が考えられます。
- 契約締結までの平均所要時間の短縮率
- 印紙税削減額
- 紙使用量の削減率
- 紛失・漏洩等のインシデント発生件数の減少
数値に基づいた効果が明確になれば、他部門への展開や予算の追加も得やすくなります。また、ユーザーの声を吸い上げて改善を繰り返すことで、長期的な運用体制が整います。
紙契約の「電子化・整理」から、契約業務を軽くする
LAWGUEは、電子契約そのものを行うツールではありませんが、紙・PDFを編集できるデータにして文書として整理できます。最新版の契約書を検索しやすい状態に整えることで、確認・共有の手間を減らせます。電子化を進める際の“保管・参照の土台”として、バックオフィスの運用を支えます。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
契約書の電子化は、業務効率化やコスト削減、コンプライアンス強化など、多くのメリットをもたらします。一方で、法的要件やシステム選定、社内体制の整備には慎重な対応が求められます。まずは小規模な契約から段階的に導入し、自社に最適な電子契約の形を見つけていくことが成功の鍵となるでしょう。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








