リスクマネジメントとは?4段階プロセスと考え方を解説!

ビジネスにおけるリスクは多様化・複雑化しています。想定されるリスクに対して事前に対策しておかなければ事業や組織に多大な影響を与えてしまいます。そしてリスクに対する意識は担当者だけではなく従業員などかかわる人間全員がしっかりと理解しておかなければなりません。
そこでこの記事では、リスクマネジメントの基本から実践方法までを解説し、企業の安定経営に役立つ知識を提供します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
リスクマネジメントとは?意味と必要性

リスクマネジメントとは、ビジネス活動において発生し得る損失や障害を未然に防ぎ、影響を最小限に抑えるための一連のプロセスです。経営資源の保全、顧客や取引先からの信頼維持、法令遵守などに不可欠な取り組みであり、企業が持続的に発展していく上での基盤となります。近年は自然災害やサイバー攻撃、法規制の強化といった多様なリスクが顕在化しており、リスクマネジメントの重要性は一層高まっています。
ビジネスにおけるリスクとは何か?
ビジネスにおけるリスクとは、企業の目標達成を妨げる要因や出来事を指します。これには、自然災害、経済の不安定化、人的ミス、システム障害、法的問題、風評被害など、多岐にわたるリスクが含まれます。例えば、製品の不具合が発覚すれば顧客の信頼を失い、訴訟問題に発展する可能性もあります。また、サプライチェーンの分断や情報漏洩なども、業務に甚大な影響を及ぼす要因となります。これらのリスクを正確に把握し、事前に対策を講じることで、損失の回避や最小化が可能になります。
なぜ今、リスクマネジメントが重要なのか?
現代のビジネス環境は、グローバル化やデジタル化の進展により、かつてないほど複雑化しています。その結果、企業は従来想定していなかった種類のリスクにも対応せざるを得なくなっています。サイバー攻撃、パンデミック、環境問題、コンプライアンス違反、SNSによる風評被害など、予測困難かつ即時性の高いリスクが増加しています。
さらに、ステークホルダーの目も厳しくなっており、企業のリスク対応能力は社会的信用にも直結します。ESG(環境・社会・ガバナンス)経営が注目される中、適切なリスクマネジメントは企業の持続可能性を支える鍵といえます。また、万一のトラブルが発生した際に、迅速かつ適切に対応できる体制を整えておくことは、経営上のリスクヘッジとしても極めて重要です。
危機管理との違い
リスクマネジメントと危機管理(クライシスマネジメント)は、しばしば混同されますが、異なる概念です。リスクマネジメントは、リスクの発生を未然に防ぎ、損害を最小限に抑えるための計画的・継続的な活動を指します。一方、危機管理は、実際に重大な問題が発生した際に迅速に対応し、事態の悪化を防ぐための行動です。
例えば、地震による事業停止を防ぐために事前にBCPを策定しておくのはリスクマネジメントであり、実際に地震が発生した際にその計画に基づいて復旧作業を行うのが危機管理です。両者は相補的な関係にあり、どちらも企業活動に不可欠です。
リスクマネジメントの目的

リスクマネジメントの最大の目的は、企業の持続的な成長と安定的な経営を実現することです。リスクを正確に把握し、適切な対策を講じることで、突発的なトラブルによる損失を最小限に抑えます。結果として、業務の継続性を確保し、社会的信頼の維持にもつながります。
事業継続計画(BCP)とリスクマネジメント
BCP(Business Continuity Plan)は、自然災害やテロ、システム障害などの有事においても、事業活動を早期に復旧・継続するための計画です。リスクマネジメントの一環として位置付けられ、被害を最小限に抑えつつ、迅速な対応を図るために不可欠な要素です。
BCPの策定には、業務の優先順位づけ、代替手段の確保、情報伝達手順の明確化などが含まれます。実効性を高めるためには、定期的な見直しと訓練の実施が欠かせません。リスクを現実の危機に備えた形で具体化するのがBCPであり、企業のレジリエンス(回復力)を支える柱となります。
ステークホルダーからの信頼を維持するポイント
企業がステークホルダーの信頼を維持するためには、透明性の高い情報開示と一貫したリスク対応方針が不可欠です。特に上場企業やBtoBビジネスでは、取引先・投資家・株主などの信頼が企業価値に直結するため、リスクマネジメントの信頼性が問われます。
内部統制体制の整備や、定期的なリスク評価、迅速な報告・連絡体制の構築は、信頼性を高める重要な取り組みです。また、社会的責任(CSR)やサステナビリティを重視する企業姿勢も、長期的な信頼の構築につながります。誠実で一貫した対応が、ブランド価値向上の鍵となります。
法的要件と規制対応をスムーズに進める方法
各業界にはそれぞれ特有の法的要件や規制が存在します。リスクマネジメントを通じてこれらに適切に対応することは、コンプライアンス(法令遵守)上の重要課題です。企業はまず、自社の事業領域に関連する主要法令を洗い出し、リスクとの関係を明確にすることから始めます。
次に、法改正やガイドラインの動向に敏感である必要があります。社内に法務部門を設けるか、外部専門家と連携し、最新情報を踏まえてマニュアルやルールを整備しましょう。また、従業員への教育や内部監査の実施も、実効性を高めるうえで不可欠です。
契約書・規程のデータを“使える情報”に変える!
LAWGUEなら、過去の契約書や関連資料をまとめて保管し、横断的に検索できます。
紙・PDF・電子契約が混在していても、必要な契約文書や条文をすぐに参照可能。
蓄積された契約書データを活用でき、法務業務の属人化を防ぎます。
👉 3分でわかる資料を見る
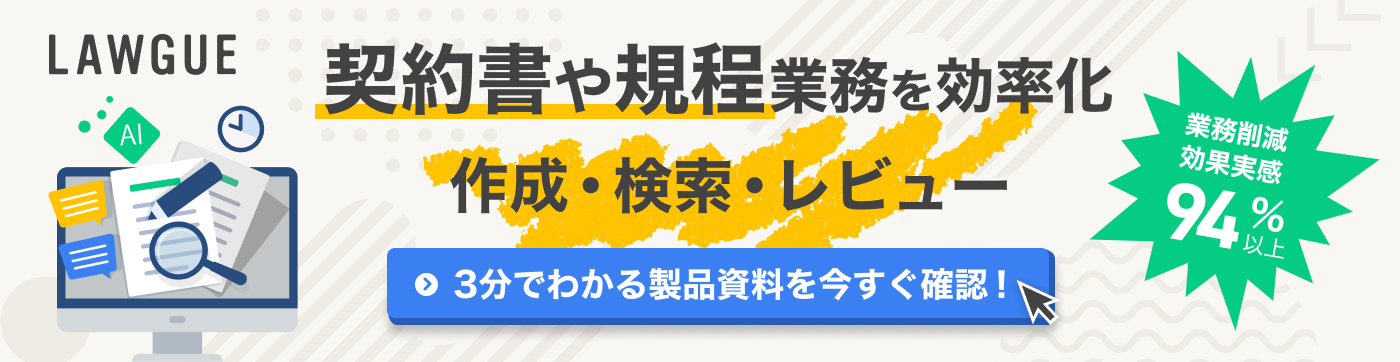
リスクマネジメントのプロセス

リスクマネジメントのプロセスは、組織が直面するリスクを系統的に管理するための段階的な手法です。主に、リスクの特定、分析、評価、対応計画の策定、そしてモニタリングと見直しという流れで構成されます。これにより、潜在的な問題の早期発見と予防的対策が可能となり、経営の安定性と持続性が高まります。特に環境変化が激しい現代においては、定期的なプロセスの更新と関係者の意識共有が不可欠です。
リスクの特定・把握 - 何がリスクか見極める技術
リスクマネジメントの第一歩は、リスクの特定です。企業活動に潜むリスクを把握し、どのような状況で発生し得るのかを明確にする必要があります。この段階では、過去の事例や業界特有のリスク、最新の社会動向などを分析しながら、包括的な視点でリスクの洗い出しを行います。
手法としては、ブレーンストーミング、チェックリスト、SWOT分析、ヒアリング調査、現場観察などが用いられます。部署ごとにリスクを把握し、全体像を共有することで、見落としを防ぎます。また、日常業務に隠れた潜在的リスクを浮き彫りにするためには、現場担当者からのフィードバックも不可欠です。
特定されたリスクは、項目ごとに整理し、発生頻度や影響度などの情報を併記してリスク台帳にまとめます。この資料は、以降のリスク分析や評価において基盤となる重要なデータです。
リスクの分析 - 発生確率と影響度の見極め方
リスクの特定が完了した後は、それぞれのリスクについて発生確率と影響度を分析します。このステップでは、リスクが現実化する可能性の高さと、発生時に企業へ与える影響の大きさを数値や定性的な基準で評価することが求められます。
発生確率の評価には、過去の実績データや業界統計、専門家の見解などが活用されます。影響度については、財務的損失、ブランドへの悪影響、法的責任、従業員や顧客への影響など複数の観点から総合的に判断します。
この分析により、リスクマトリクス(リスクの重大度を可視化した表)を作成し、どのリスクが特に重要かを明らかにします。高頻度かつ高影響のリスクは最優先で対応する必要があります。逆に、発生確率も影響度も低いリスクは、モニタリングを中心とした対応が適切です。
リスクの評価 - 優先順位づけの考え方
分析の結果を基に、リスクごとの優先順位を設定するのが評価のステップです。これは限られた経営資源の中で、どのリスクにどれだけ対応するかを判断するための重要なプロセスです。
優先順位は、リスクマトリクスに従って定量的に評価するだけでなく、経営戦略や事業計画との整合性、社会的責任の観点なども加味して決定します。
また、リスクの連鎖反応(複数リスクが連動して被害を拡大するケース)も考慮し、単独で軽微に見えるリスクでも全体への影響が大きい場合は、上位に位置づける必要があります。このようにして作成されたリスク優先順位表は、対応計画の策定に直結する実務的な資料となります。
リスクへの対応計画 - アクションプランの立て方
優先順位が決まったリスクに対しては、具体的な対応策を講じる必要があります。対応方法は大きく4つに分類されます:回避、低減、移転、受容です。それぞれのリスク特性に応じて最適な手段を選択し、具体的なアクションプランを設計します。
例えば、システム障害のリスクに対しては、冗長化による低減策や外部委託による移転策が考えられます。自然災害に備えるにはBCPの策定や訓練の実施が有効です。
アクションプランには、担当者、実施期限、必要予算、評価指標などを明確に盛り込むことが重要です。また、対応策の進捗を定期的に確認し、必要に応じて修正・強化する体制を整えましょう。
対応計画は単なる文書ではなく、実際に機能する体制の整備と従業員への周知徹底を通じて、はじめて実効性を持ちます。
4つのリスク対策の考え方

リスクへの対応には、主に「回避」「低減」「移転」「受容」の4つの方法があります。これらはリスクの特性や組織の許容度に応じて選択され、柔軟に組み合わせて活用されます。
例えば、下記のような判断です。
回避:事業拡大による新市場参入のリスクを避ける
低減:災害対策を強化して影響を軽減する
移転:保険や契約で損失を外部に移す
受容:そしてコスト効率の観点からあえて受け入れる
各対策の特性を理解し、状況に応じた適切な対応が、リスクマネジメントの成功を左右します。
リスク回避 - リスクを発生させない選択肢
リスク回避とは、リスクそのものが発生しないように活動を中止・変更することで問題の芽を摘む対応です。これは、リスクの影響が極めて重大で、なおかつ代替手段がある場合に有効です。
例えば、新規市場への参入を計画していたが、政治的不安定さや為替リスクが高すぎると判断された場合、参入そのものを断念することでリスクを完全に排除できます。また、外部ベンダーとの契約において、リスクのある条項を削除・修正することも回避策の一つです。
ただし、回避は事業機会の喪失を招く可能性もあるため、他のリスク対応策と比較して総合的に判断する必要があります。利益と安全性のバランスを見極めたうえでの戦略的決断が求められます。
リスク低減 - 発生確率や影響を小さくするテクニック
リスク低減は、リスクの発生を完全に防ぐことは難しくても、発生確率や影響度を下げることで損害を最小限に抑える手法です。多くの企業が最も頻繁に採用するリスク対応の手段といえます。
例えば、ITシステムの障害リスクに対しては、サーバーの二重化やバックアップ体制の強化、セキュリティ対策の導入などが効果的です。自然災害への対策としては、耐震補強、避難訓練、予備電源の確保などが挙げられます。
リスク低減策は、コストと効果のバランスを考慮しながら実施することが重要です。リスクの重大性に応じて、どの程度の投資を行うかを判断しなければなりません。また、低減策は一度導入して終わりではなく、継続的な改善と検証が求められます。
社内教育や標準業務手順(SOP)の整備もリスク低減に寄与します。従業員のリスク意識を高めることで、日常業務におけるヒューマンエラーを減らす効果が期待されます。
このように、リスク低減は現実的かつ実行可能な方法として、多くの場面で有効に機能します。
リスク移転 - 保険や外部委託を活用する方法
リスク移転とは、リスクによる損失を第三者に肩代わりしてもらう手法です。主な手段には「保険の加入」や「業務の外部委託(アウトソーシング)」があります。例えば、火災保険や賠償責任保険などを利用することで、予期せぬ損害が発生した場合でも経済的な打撃を軽減できます。
また、特定の業務を専門業者に委託することで、自社で発生するリスクを減らすことが可能です。例えば、情報システムの管理を専門会社に任せれば、障害対応やサイバー攻撃への備えが強化され、責任も契約上明確になります。
ただし、リスクを移転しても、完全に責任を免れるわけではないため、委託先の選定や契約条件の精査は極めて重要です。移転可能なリスクの種類や範囲を見極め、適切な手段を講じることが求められます。
リスク受容 - 戦略的にリスクを受け入れる判断基準
リスク受容とは、リスクを認識しながらも、あえて特別な対応をせずに許容する選択肢です。主に、発生確率や影響度が極めて低いリスクや、対応コストがリスクによる損害を上回る場合に採用されます。
例えば、軽微な設備故障の可能性や、発生頻度が低く損害も限定的なクレームなどが該当します。このようなリスクに対して無理に対策を講じれば、かえって非効率になる恐れがあります。
受容を選択する際には、明確な判断基準とその理由を記録に残し、関係者間で共有することが重要です。また、受容したリスクもモニタリングの対象とし、状況が変化すれば方針の見直しを行う柔軟性が求められます。
リスク受容は、対応を「しない」ことではなく、経営判断として「する価値がない」と評価することに他なりません。
中小企業でも実践できるリスクマネジメントとは?
中小企業にとってリスクマネジメントは、大企業のような専任部署や潤沢なリソースがなくても、十分に取り組むことが可能です。ポイントは「できることから段階的に始める」ことです。
まずは、自社の業務におけるリスクを洗い出し、一覧にすることから始めましょう。業種ごとの特性や過去のトラブル事例を参考に、想定し得るリスクを明文化することが重要です。
次に、そのリスクがどの程度の頻度で起こり得て、どのような影響を及ぼすかを簡易的に評価し、優先順位を付けます。
対応策については、無理なく取り組める範囲から選定しましょう。例えば、バックアップの仕組みを見直す、マニュアルを整備する、連絡網を作成するなど、低コストで効果的な施策も多くあります。また、地域の商工会議所や自治体、保険会社などが提供するリスク管理支援を活用するのも有効です。
継続的な見直しと従業員への共有も忘れずに行うことが大切です。小規模であることを強みに、機動力のあるリスク対応を目指しましょう。
リスクマネジメントに関する資格や学習リソースは?
リスクマネジメントの知識を体系的に学ぶには、資格取得やオンライン学習の活用が効果的です。代表的な資格には、「リスクマネジメント協会認定資格(CRM)」「BCMS監査員」「ISO 31000関連資格」などがあります。これらは基礎から実務的な応用まで幅広くカバーしており、企業内の信頼性向上にも寄与します。
また、各種オンライン講座(Udemy、Courseraなど)や、経済産業省・中小企業庁のガイドライン、専門書籍・業界団体の発行資料なども豊富に存在します。初学者向けから上級者向けまで多様な教材があるため、目的に応じて選ぶと良いでしょう。
資格取得や学習は、組織のリスク意識を高めるきっかけにもなります。個人だけでなく、チーム全体での学習体制づくりが重要です。
業界別(医療・介護)のリスクマネジメント対策は?
医療・介護業界は、人的ミスや情報漏洩、感染症の拡大など、日常業務の中にリスクが多く潜む業種です。そのため、業界特有のリスクマネジメント対策が求められます。
医療機関では、インシデントレポートの導入や、定期的なヒヤリ・ハット報告の収集と分析が重要です。これにより、再発防止策を講じるPDCAサイクルが機能します。また、電子カルテや個人情報の管理体制を強化し、アクセス権限やログ管理を徹底する必要があります。
介護施設では、転倒事故や虐待防止、職員の労務管理などが中心課題です。リスクアセスメントを定期的に行い、リスクの高い利用者に対しては個別の対応計画を作成するなどの工夫が求められます。職員教育も重要で、リスク感度を高めることでヒューマンエラーを抑制します。
両業界に共通するのは、「記録の徹底」と「チームでの情報共有」です。透明性の高いリスク管理が、利用者や家族からの信頼確保にもつながります。
契約書・規程のデータを“使える情報”に変える!
LAWGUEなら、過去の契約書や関連資料をまとめて保管し、横断的に検索できます。
紙・PDF・電子契約が混在していても、必要な契約文書や条文をすぐに参照可能。
蓄積された契約書データを活用でき、法務業務の属人化を防ぎます。
👉 3分でわかる資料を見る
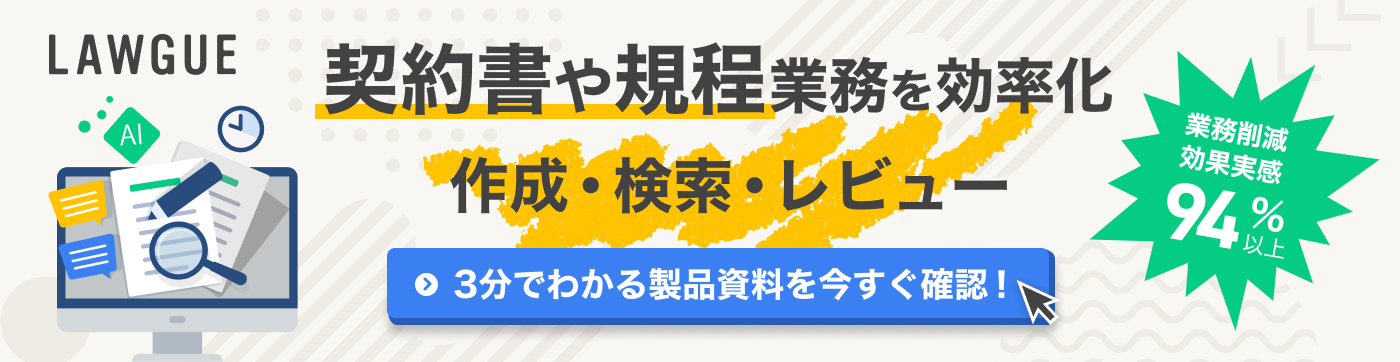
よくある質問
リスクマネジメントとはどういう意味ですか?
リスクマネジメントとは、企業活動における様々なリスクを特定・評価・対応し、損失の最小化と組織の持続的成長を目指す管理手法です。
リスクマネジメントの4つのプロセスは?
主な4つのプロセスは、リスクの特定、リスクの分析、リスクの評価、リスクへの対応計画の策定です。これに加えて定期的な見直しも重要です。
リスクマネジメントはどの部門が担当すべきですか?
企業によって異なりますが、一般的には総務部門、経営企画部門、法務・コンプライアンス部門が中心となって実施します。ただし、リスクマネジメントは全社的な取り組みであるべきで、各部門が自分たちの業務に関わるリスクを把握・対応する体制づくりが重要です。部門横断的な「リスク管理委員会」を設置し、情報共有と統一的な方針決定を行う企業も多く見られます。
リスクマネジメントとコンプライアンスの違いは?
リスクマネジメントは、企業活動におけるあらゆるリスク(自然災害、人的ミス、サイバー攻撃など)を対象とし、損失の回避や最小化を目的とする広範な概念です。一方、コンプライアンスは「法令や規則を遵守すること」が主眼であり、法的・倫理的なリスクの一部分に特化しています。両者は相補関係にあり、コンプライアンス違反もリスクの一種としてリスクマネジメントの中で扱われます。
中小企業でもリスクマネジメントは必要ですか?
必要です。むしろ、中小企業こそリソースが限られる分、大きなトラブルが経営に与える影響が大企業より深刻になることもあります。例えば、主要顧客からの取引停止や自然災害による設備被害が、倒産に直結する可能性もあるため、簡易的でも自社に合ったリスクマネジメントの導入が不可欠です。中小企業庁や商工会議所などの支援ツールを活用することで、効果的な取り組みが可能になります。
自然災害リスクに対して企業は何をすべきですか?
日本では地震、台風、豪雨など自然災害のリスクが高く、事前対策は欠かせません。まずはハザードマップを活用し、自社拠点が抱える災害リスクを把握しましょう。その上で、以下の対策が有効です。
- 事業継続計画(BCP)の策定
- 避難訓練の実施
- 建物や設備の耐震補強
- 重要データのクラウドバックアップ
- 緊急連絡網の整備 これらの備えにより、災害時の被害を最小限にとどめ、迅速な事業復旧が可能になります。
リスクマネジメント体制はどう構築すればよいですか?
リスクマネジメント体制の構築には、まず「トップのコミットメント」が不可欠です。経営陣がリスクマネジメントの重要性を認識し、資源や人材を割く姿勢を示すことで、組織全体の意識も高まります。次に、担当部署や委員会の設置、社内規程の整備を行い、運用ルールを明文化します。さらに、定期的なリスク評価と改善サイクル(PDCA)を組み込むことで、持続可能な体制が実現します。
契約書・規程のデータを“使える情報”に変える!
LAWGUEなら、過去の契約書や関連資料をまとめて保管し、横断的に検索できます。
紙・PDF・電子契約が混在していても、必要な契約文書や条文をすぐに参照可能。
蓄積された契約書データを活用でき、法務業務の属人化を防ぎます。
👉 3分でわかる資料を見る
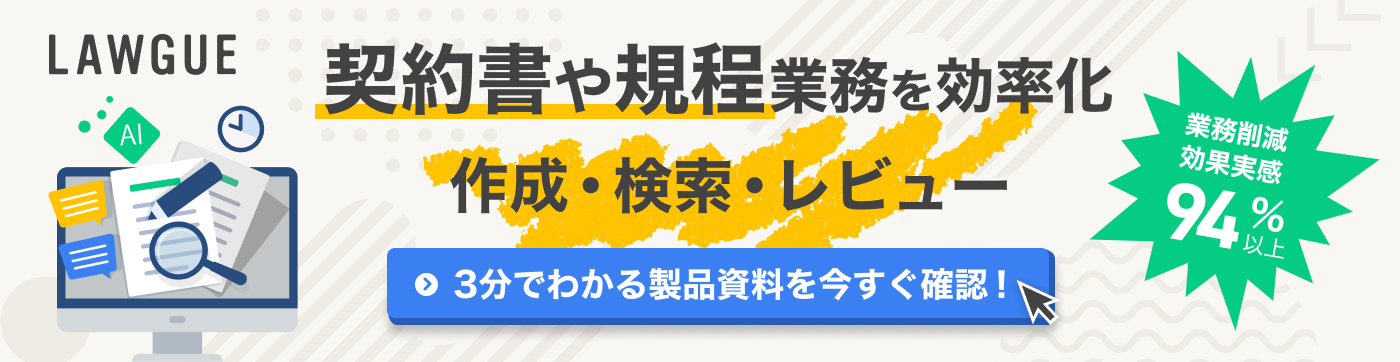
まとめ
リスクマネジメントは、企業が安定的かつ持続的に成長するために欠かせない取り組みです。リスクを正しく把握し、優先順位をつけて対応することで、トラブルを未然に防ぎ、信頼性の高い経営が実現します。大企業だけでなく中小企業でも実践可能であり、日々の業務に落とし込むことが重要です。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








