契約書のテンプレートを作る際のポイントとは?項目ごとの例文や注意点を徹底解説
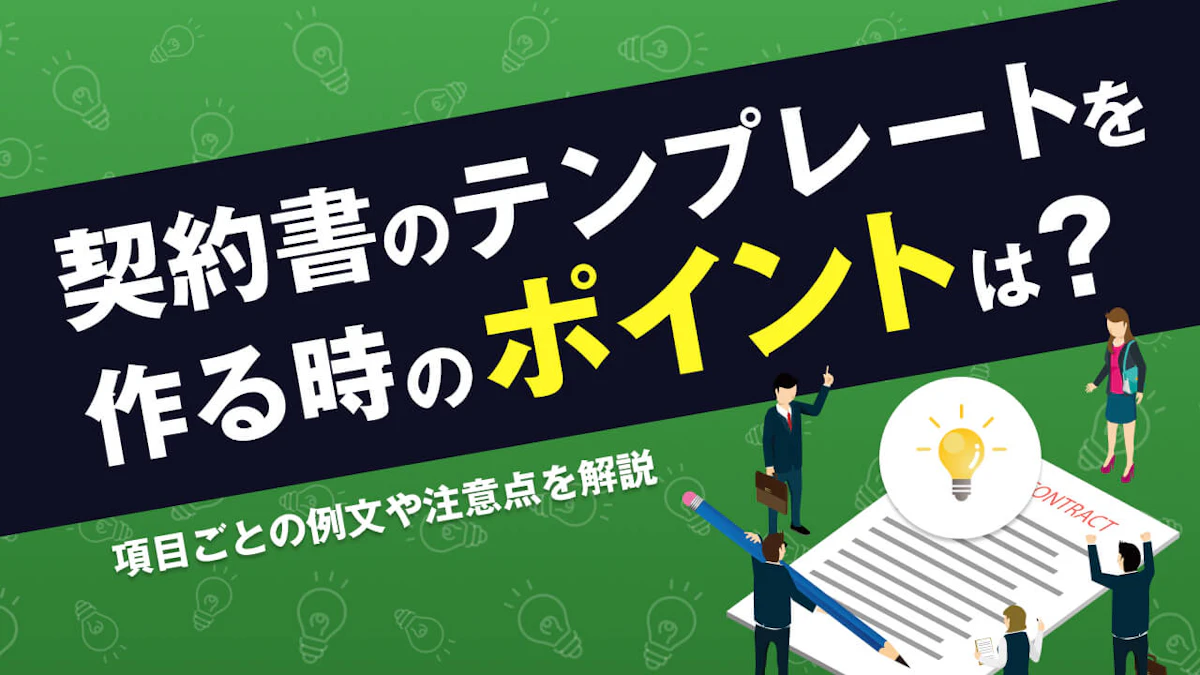
契約トラブルを未然に防ぐためには、明確で正確な契約書の作成が不可欠です。しかし、ゼロから契約書を作成するのは大変で、法的リスクを含む恐れもあります。そこで活用したいのが「契約書のテンプレート(ひな形)」です。
この記事では、契約書テンプレートのメリット、作成時の重要ポイント、項目ごとの記載例や注意点まで、法的観点からわかりやすく解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書ひな形とは何?

契約書のひな形(テンプレート)とは、契約に必要な基本項目があらかじめ記載された文書のことを指します。業務委託契約書や売買契約書など、用途ごとにフォーマットが存在し、必要に応じて内容を調整して利用します。法的効力を持たせるには、テンプレートをそのまま使うのではなく、実際の契約内容に即して修正・補足することが重要です。
契約書ひな形を作成する3つのメリット

契約書を一から作成するには、法的知識や文章構成力が求められ、時間も労力もかかります。特に業務が多忙な中小企業や個人事業主にとって、毎回契約書をゼロから作るのは非効率と言わざるを得ません。そこで活用したいのが「契約書のひな形(テンプレート)」です。
一定の形式と条項が整っているテンプレートを活用することで、作成作業が効率化されるだけでなく、記載漏れやミスを防ぎ、社内での契約書運用も統一しやすくなります。ここでは、契約書のひな形を作成・活用することによって得られる主な3つのメリットをご紹介します。
作成の効率化と時間短縮
契約書テンプレートを用意しておくと、新規契約時に条項を一つひとつ考える手間が不要になります。必要な項目が網羅されたひな形を選び、契約期間や金額、当事者名などを修正するだけで済むため、作成にかかる時間を数分~数十分で済ませられます。
また、ひな形を前提とすることで、社内承認フローも明確になります。ひな形の内容が事前に承認されていれば、変更した箇所のみを確認すればよくなり、法務部門や上長のチェックが迅速化します。
結果として契約締結のサイクルが早まり、案件の獲得や業務開始時期を逃さなくなります。
漏れや誤記の防止
ひな形には基本的な条文(契約目的、契約期間、解除条件、通知方法など)がすでに盛り込まれているため、新たに作成する際に「絶対に含むべき項目」を見落とすリスクが激減します。条文漏れ・数字や日付の記入ミスも減るため、対外的な信頼性も高まります。
社内での統一運用が可能
自社でひな形を整備することで、契約内容にばらつきがなくなります。部門や担当者ごとに異なる契約書を使うと、重要な条項が抜けていたり、同じ事象でも文言が違ってトラブルが生じたりしやすくなります。一方、契約のひな形に反社排除条項や個人情報保護条項、情報漏えい対策などのコンプライアンス要素をあらかじめ盛り込めば、毎回確認して追記する必要がなくなります。これにより従業員がルールを意識せずとも契約書に反映され、法令リスクや社会的信用の問題を未然に防止できます。
さらに、統一された契約書ひな形は、新人研修や社内勉強会の教材としても有用です。各条項の意味や目的を研修に取り入れることで、契約内容の理解を深め、法務リテラシーの底上げにもつながります。これにより、契約書作成を担当する社員全体の品質レベル向上が期待できます。
契約書のひな形・テンプレートを作成する際のポイントとは?
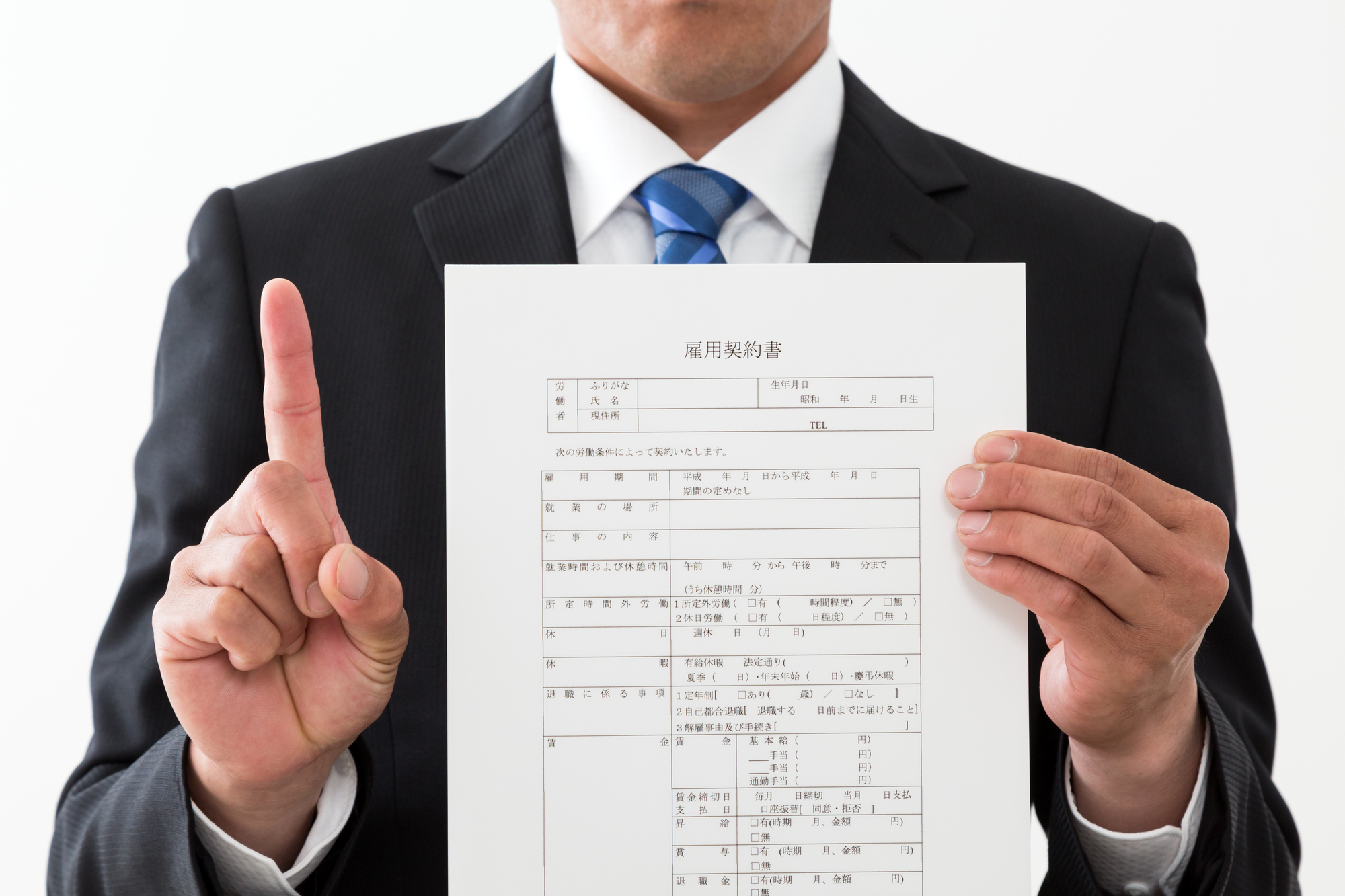
契約書のひな形は便利なツールですが、ただ形式を真似るだけでは不十分です。実際の取引内容やリスクに応じた調整を行わなければ、法的なトラブルに発展するおそれもあります。
ここでは、契約書テンプレートを作成・活用する際に押さえておくべき重要なポイントを5つに絞って解説します。
契約の目的を明確にする
契約書の前文や第1条では、契約の目的や内容を明文化する箇所が設けられています。この部分を曖昧にしておくと、後の契約解釈や履行時に齟齬が生じかねません。
文章例:「本契約は、甲が保有する〇〇商品に関する販売業務一式を、乙に委託し、その対価として報酬を支払うことを目的とする。」チェック項目:目的の明確性・当事者の呼称の一貫性・契約対象が網羅されているか。
双方の義務と責任範囲を明記する
ひな形による記載であっても、当事者それぞれの義務・責任範囲を具体的に明記することが重要です。ここが曖昧だと、自分たちの契約違反や履行不履行の根拠となりやすくなります。特に、社内の業務フロー上不可能なことを強制されることのないよう、社内の他部門(経理・営業・開発等)と連携し、実務に沿った要件に調整してください。
文章例:「甲は本契約に基づき、乙に対し週1回の納品報告書を電子メールで提出し、乙は納品月の月底日までに請求書を提出するものとする。チェック項目:納期や業務範囲が明示されているか・双方の責任範囲は過不足なく定義されているか。
契約期間や更新条件を設定する
ほとんどのひな形では「契約期間」「更新条件」欄がありますが、実務ではこれが抜けていたり不明確だったりすることで、更新や終了のタイミングでトラブルが起きやすくなります。また、社内決裁の間に更新拒否の通告期限を過ぎてしまう、というトラブルも起こりがちなので、自社の意思決定のあり方も踏まえて決することが重要です。
文章例:「本契約の期間は、令和○年○月○日から同年○月○日までとし、両当事者が書面で合意した場合に限り、自動更新とするものとする。」チェック項目:期間の開始日・終了日・自動更新などの条項が明示されているか・更新拒否の事前通告の期限は明記されているか。
紛争時の対応方法を規定する
ひな形にはよく「協議条項」「合意管轄条項」が含まれていますが、これらを入れて安心してはいけません。内容が曖昧だと、万一裁判に至った際、コストや事務負担が増える可能性があります。そもそも、円満な協議で解決できない場合に備えて契約書があるという側面もあるので、紛争の際に自社に不利な形で対応させられることのないように考えておくことが大事です。
文章例:「第◯条(協議) 本契約に関し疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し解決するものとする。」「第◯条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」チェック項目:協議の期限・管轄裁判所はどこか・特別なADR(調停・仲裁)を前提にするのか。
最新の法改正を反映する
特に労働法や個人情報保護法など、頻繁に改正される法律には注意が必要です。
契約書テンプレは「作成」より「統一・更新・運用」が重要
LAWGUEなら、目的・業務範囲・報酬・解除・反社など“抜けやすい必須条項”をテンプレ化して、社内で統一運用しやすくなります。
変更履歴・最新版管理・承認フローを揃えることで、担当者ごとの文言ブレやレビューの手戻りを減らせます。
👉 3分でわかる資料を見る

契約書の記載項目別テンプレート

契約書は、内容の正確さだけでなく、記載すべき項目を適切に網羅することが重要です。不備のある契約書は、万が一のトラブル時に法的効力を十分に発揮できないおそれがあります。ここでは、契約書に盛り込むべき基本的な項目を取り上げ、それぞれの役割や具体的な記載例を交えてわかりやすく解説します。
①表題(タイトル)
契約書の冒頭に記載するタイトルは、契約の種類を明確に示すための重要な要素です。内容と一致した表題を付けることで、文書の目的が一目でわかります。
記載例:「業務委託契約書」「販売代理店契約書」「秘密保持契約書」
②前文
前文には、契約当事者の名称・所在地・代表者氏名および契約の目的を簡潔に記載します。契約の背景や趣旨を明らかにする役割があります。
記載例:「株式会社〇〇(以下『甲』という)と株式会社△△(以下『乙』という)は、以下のとおり業務委託契約(以下『本契約』という)を締結する。」
③契約条項
契約条項は、契約の中心部分であり、業務内容・対価・納期など具体的な条件を明示します。条文ごとに分けて整理するのが一般的です。
記載例:「第◯条(業務内容)甲は乙に対し、別紙業務仕様書記載の業務を委託し、乙はこれを受託する。」「第◯条(報酬)甲は乙に対し、本業務の報酬として金◯円を支払う。」
④損害賠償
契約違反や債務不履行があった場合に、どのような損害賠償責任を負うかを明確に定めます。損害の範囲や上限金額、過失の有無に応じた責任制限も記載するのが一般的です。
記載例:「一方当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反当事者は通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負うものとし、その上限額は本契約に基づく支払総額を超えないものとする。」
⑤契約期間
契約の有効期間、開始日・終了日、自動更新の有無、更新条件を明記します。終了後の措置や再契約の有無についてもあわせて定めることが重要です。
記載例:「本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の1カ月前までに双方から書面による終了の申出がない場合、自動的に同一条件で1年間更新されるものとする。」
⑥契約解除事由
一方的に契約を解除できる条件を定める条項で、債務不履行・破産・信用失墜などを想定します。即時解除か、催告後解除かを区別しておくことが望まれます。
記載例:「一方当事者が本契約に重大な違反をし、相手方が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、これに応じない場合、相手方は書面により本契約を解除することができる。」
⑦反社会的勢力の排除(反社条項)
相手方が暴力団等の反社会的勢力でないこと、および関与が判明した場合の契約解除の根拠となる条項です。企業リスク回避の観点から必須です。
記載例:「当事者は、相手方が反社会的勢力に該当しないこと、今後も関与しないことを表明・保証する。違反が判明した場合、催告なく契約を解除できるものとする。」
⑧権利義務の譲渡禁止
契約上の地位、権利、義務を第三者に無断で譲渡できない旨を規定します。無断譲渡による混乱や法的リスクを未然に防ぐ効果があります。
記載例:「当事者は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位、または本契約に基づく権利および義務を第三者に譲渡、承継してはならない。」
⑨合意管轄
万が一、訴訟に発展した場合にどの裁判所で争うかを定める条項です。所在地の地方裁判所を合意管轄とする例が多く、事前の明記で訴訟リスクを軽減できます。
記載例:「本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」
⑩協議条項
解釈の違いやトラブルが生じた際には、裁判前にまず協議で解決を図る旨を明記します。関係維持や迅速な対応を意図した条項です。
記載例:「本契約に関して疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。」
⑪後文
契約の最終確認に関する条項で、契約の成立事実や部数、紙面か電子か、署名押印の位置づけを明記します。
記載例:「本契約書は、正本2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。また、電子契約システムにより締結された場合は、当該電子データを契約書とみなす。」
⑫日付欄と署名欄
契約の成立日と、両当事者の署名・押印欄です。
契約書作成における形式面について
契約書を有効な法的文書とするためには、内容だけでなく形式面にも十分な注意が必要です。印紙の貼付、割印・契印の押印など、形式を整えることで契約書の真正性や証拠力が高まります。ここでは、契約書作成時に押さえておくべき基本的な形式面のルールと実務上の注意点について解説します。
印紙
売買契約書や請負契約書、金銭の貸借に関する書面などには印紙税がかかります。例えば、金銭の貸借契約で借入金額が1万円超の場合は200円~納税、売買契約の売買金額が1万円超の場合も同様に該当します。印紙税法では「非課税文書」「課税文書」が定められているため、契約書を作成する際には印紙税を正確に確認しましょう。
割印
契約書の冒頭、もしくは表紙部分に印紙を貼り、印紙に”契印”あるいは債権者・債務者両者がまたがる位置に捺印します。印紙を貼り忘れると過怠税処分があり(貼付税額の3倍)、貼り過ぎた場合は還付申請が可能です。ただし還付には領収証や契約成立年月日の記載といった添付書類が必要です。
割印と契印
- 割印(わりいん)
複数ページにわたる契約書を“1つの文書である”と示すため、隣り合うページの余白にまたがるように印章を半分ずつ押印します。これにより、ページの順番や内容の改ざん防止になります。 - 契印(けいいん)
契約書を綴じ合わせたホチキスや綴じひも部分に印章を押します。これも綴じた順序や改ざんを防止する役割があり、「契約文書全体は一体である」ことを担保する証拠機能を果たします。 - 使い分け
割印はページごと、契印は文書を綴じた後に主に表紙で使われます。どちらも省略すると裁判で真正性を問われるケースがあるため、実務では両方押印することが一般的です。
契約書はどちらが作成するべき?
契約書の作成は取引当事者のいずれが行っても構いませんが、内容によっては作成主体が契約条件に大きな影響を与えることもあります。ここでは、作成の主導権を握るべきケースや注意点を解説します。
自社商品や自社サービスに関する契約書の場合
原則として自社で予めテンプレートを作成しておくのが望ましいです。自社商品や自社サービスに関する情報や知識は自社が一番保有しているわけですし、契約書が相手によってまちまちだと社内が混乱してしまいます。
また、当初は想定しなかった問題が起こることもありえますので、その場合、必要に応じて雛形をアップデートしていくことが重要です。
重要な契約書の場合、作成を相手にまかせない
特に、取引の重要性が高い場合は、相手任せにせず、弁護士に相談のうえ、自社作成もしくは慎重なレビューを行いましょう。
契約書テンプレは「作成」より「統一・更新・運用」が重要
LAWGUEなら、目的・業務範囲・報酬・解除・反社など“抜けやすい必須条項”をテンプレ化して、社内で統一運用しやすくなります。
変更履歴・最新版管理・承認フローを揃えることで、担当者ごとの文言ブレやレビューの手戻りを減らせます。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
契約書のテンプレートは、契約トラブルを防ぎ、業務の効率化にもつながる重要なツールです。ただし、法的有効性を持たせるには、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の契約内容やリスクに応じた調整が不可欠です。企業法務における契約書作成には、最新の法律知識と実務経験が求められます。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








