契約書における反社会的勢力排除条項(反社条項)とは?ひな形(例文)や義務を解説
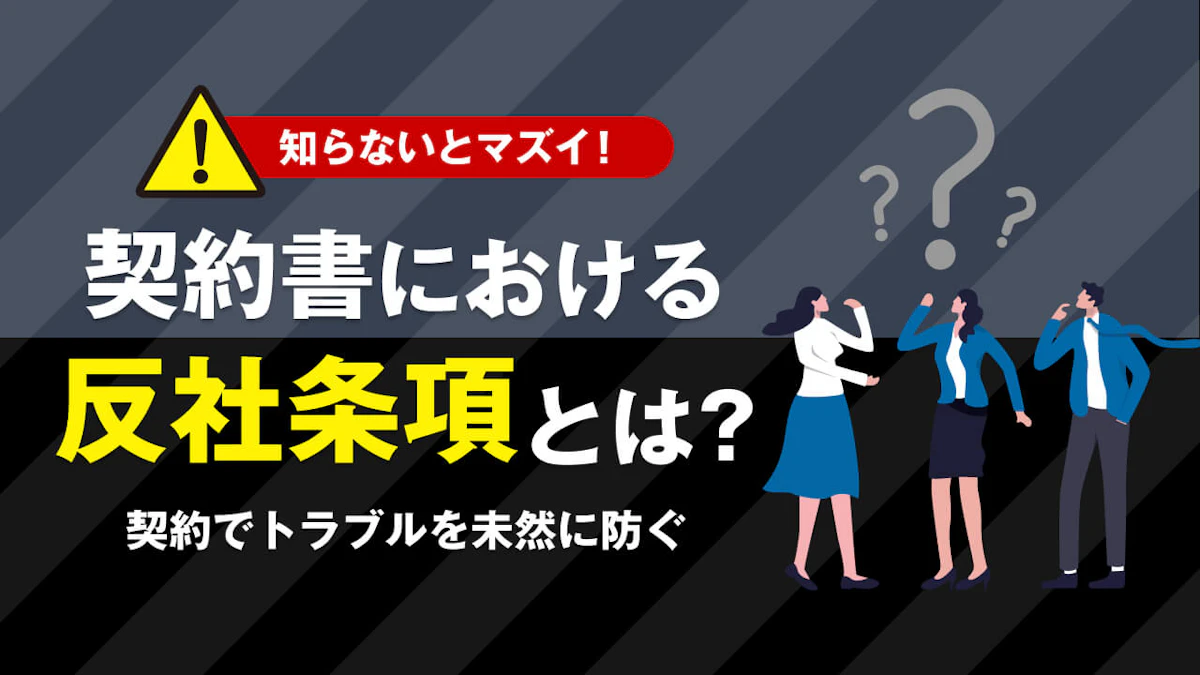
みなさんは、最近「反社会的勢力の排除」という条項を目にする機会が増えたと思います。
会社でみる契約書だけでなく、アプリなどの規約にも入っています。
この反社会的勢力排除条項(反社条項)が取り入れられ始めたのは、10年以上前のことです。この反社条項とは何かを説明した後、その重要性をご説明します。
さらに、反社条項を記載しなければならない場合にどのような条項を入れればよいか、そのひな形を示しながらご説明します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書に必要な反社会的勢力排除条項(反社条項)とは何?
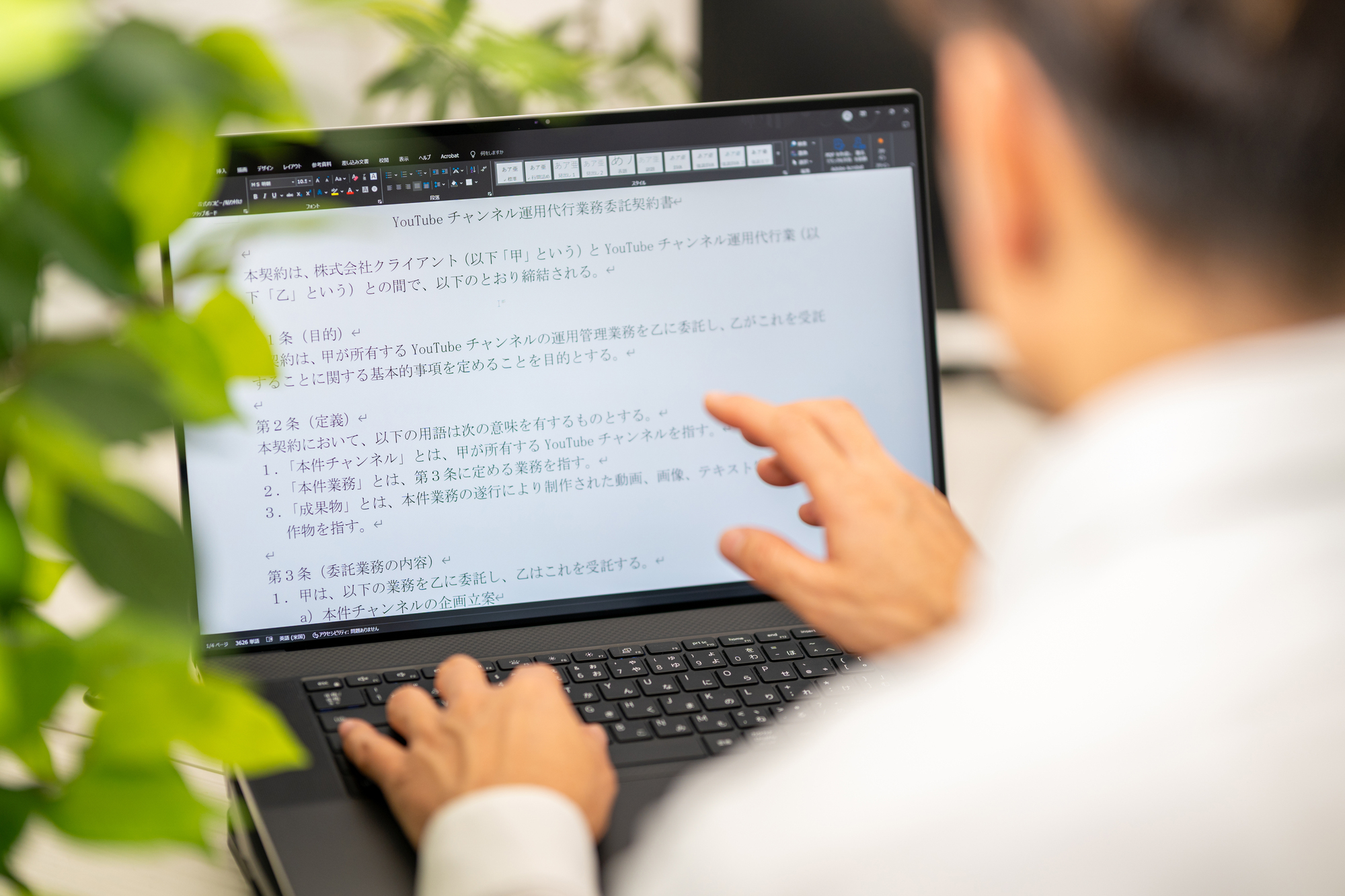
反社会的勢力排除条項(略して反社条項、時に暴排条項とも呼ばれます)とは、契約を結ぶときに、契約当事者(関係者を含む)が反社会的勢力ではないこと、暴力的な行為をしないことなどをお互いに約束する条項のことです。
よほど旧知の仲であるとか、何度も契約しているなどの特段の事情がなければ、ほとんどの契約書で目にする条項です。
2007年(平成19年)の犯罪対策閣僚会議の出した指針に、「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する(後略)。」とあり、この辺りから一般的に使われるようになりました。
反社会的勢力の定義とは
どのような者・団体が反社会的勢力に当たるかは必ずしも明確な定義があるわけではありませんが、上記指針に、例示として「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」とされており、多くの場合ここに記載されている者・団体が反社会的勢力とされていると考えられます。
「暴力団」とは、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴対法2条2号)とされています。
暴力団関係企業は、いわゆるフロント企業のことで、総会屋とは株主総会に出席して不当な要求をするなどする者です。社会運動標ぼうゴロ・政治活動標ぼうゴロとは、社会運動・政治活動と称して不当な利益を得るために暴力行為などをする者です。特殊知能暴力集団とは、暴力団との関係やその資金などを使い、不正行為などを行っている者のことです。
反社会的勢力該当者・反社会的行為の例
この定義を基準として、反社会的勢力該当者を具体的に契約条項に落とし込んでいきます。
現在、全国の都道府県に暴力団排除条例がありますので、それを参考にすることも考えられます。また、警察庁や各地の警察がモデル条項例を公表していることも多いですので、それらを参考にすることもあります。
例えば東京都であれば、「規制対象者」として、暴対法上の中止命令を受けてから3年を経過しない者、暴力団の名前をよく出す者が代表をしている企業の従業員なども含めています。
いわゆる暴力団の構成員だけでなく、その周辺の者や関連企業など広く該当すると考えるのがよいでしょう。警視庁の出しているモデル条項例でも、自らが反社会的勢力でないだけでなく、反社会的勢力を利用する場合も含めています。
反社会的行為は、業界や企業によって異なっていて問題ありません。基本的には「法律で認められる範囲を超えた過度な要求」「暴力や犯罪行為を伴う行為」となりますが、例えば多数の一般ユーザーを抱える企業であれば、他のユーザーに迷惑をかける、他のユーザーに犯罪行為を持ちかける行為なども反社会的行為として規定します。
警視庁のモデル条項例でも、
①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
を含めています。
反社条項と暴力団排除条例の関係性について
先に述べたとおり、暴力団排除条例は全国にあります。
暴力団排除条例は、事業者に対していくつかの義務を定めていることが多く、契約書に反社条項を入れるべきとする規定が含まれていることが多いです。
したがって、反社条項を入れることが、すなわち暴力団排除条例を遵守することに繋がっていると言えます。
契約自由の原則があるので、必ず反社条項を入れなければならないというわけではないのですが、反社条項は相手を疑っているようで本来的には入れづらい条項ではあります。それを暴排条例に定められているからと比較的気兼ねなく契約条項に入れることができます。
これだけ反社条項が広まった一因としては、暴排条例の存在もあるでしょう。
【東京都】暴排条例における事業者の努力義務
参考に、東京都の暴排条例を紹介しておきます。18条に、事業者の契約時の努力義務が定められています。具体的には以下のような義務が定められています。
①契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認すること(1項)
②契約時に以下のような内容の条項を盛り込むようにすること(2項)
- 暴力団関係者と分かったら催告なく解除できるとする条項
- 工事において例えば相手が使う下請が暴力団関係者と分かった場合、相手に対し、その下請と契約を解除するなどの対応をするよう求める条項
- 上記の対応をするよう求めても、契約の相手が正当な理由なく対応してくれない場合には契約解除できるとする条項
これらは努力義務なので契約に定めなくても罰則はないですが、多くの契約書ではこれに準じた対応がされています。
この条項があることで早期に関係を断つことができます。
先に述べたとおり、暴力団だけでなく、その周辺の者も規制の対象となっています。契約書に反社条項を入れず確認を怠っていると、自身も周辺の者として認定されかねません。自己防衛のためにも、暴排条例に準じておくことは重要です。
他方で、利益供与の禁止は具体的な法的義務として定められています。違反すると公表されることがあり、継続して違反すると場合により罰則まであり得ます。
東京都「東京都暴力団排除条例」
契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)が必要な理由

このように契約書には反社条項を入れることが一般的となっていますが、ここで反社条項を入れる理由を整理しておきます。
主に企業の内部的な理由から来るもの(不当な不利益を負わないようにする、自身が反社会的勢力とみなされないようにする、ブランドイメージを守るなど)と、企業の外部的な理由から来るもの(条例を遵守する)に分けられます。
以下、それぞれ詳しく説明していきます。
企業の内部的理由①~不当な不利益を負わないようにするため
まず、企業の内部の理由として、不当な不利益を負わないようにすることが挙げられます。
一番現実的な理由ですが、反社会的勢力と関わることで、法律上認められる義務を超えて高い金銭を負担することになったり、やらなくて良いことをやらされたりします。
反社条項により反社会的勢力と関わることを防げますので、不当な要求にさらされることを防止できます。
企業の内部的理由②~自身が反社会的勢力とみなされないようにするため
さらに、企業側の事情として、自身が反社会的勢力とみなされないようにするためという目的もあります。
先述しましたとおり、反社会的勢力はかなり広範に捉えられており、契約相手方の確認を怠っていることも反社会的勢力に該当しかねません。
また、反社条項が浸透しており、反社条項を入れようとしないことは、自身が反社会的勢力であることを隠しているのではないかと相手方に思われても仕方ないとも言えます。
このように、反社条項を入れることは、自身が反社会的勢力とみなされることを防ぐためともいえるのです。
企業の内部的理由③~コンプライアンスを遵守しブランドイメージを守るため
企業側の事情のうちもう少し抽象的なものとして挙げられるのは、コンプライアンスの遵守でしょう。
現在の取引環境では、どの業界でも一般消費者からどうみられるかが重視され、そのためにコンプライアンスの遵守が求められています。
反社会的勢力と繋がりがあるとされてしまえば、ブランドイメージが低下し、自社製品が売れなくなったり、取引先が取引してくれなくなったりします。
反社会的勢力との繋がりを断つことはコンプライアンスの遵守そのものであり、ブランドイメージを守ることになります。
企業の外部的理由~暴排条例を守るため
続いて、外部的な要因ですが、やはり暴排条例を遵守するためという理由は外せません。
先ほど述べましたとおり、暴排条例は契約書の内容そのものについて規定が設けられています。反社条項を入れることそのものがすなわち暴排条例を守ることになります。
暴排条例は努力義務ではありますが、ここまで反社条項が浸透していることを考えると、努力義務を超えてもう少し強い義務になっているとも思われます。
このように、暴排条例からの要請として、反社条項を入れていると考えられます。
反社条項、入れ忘れ・文言ブレを防いで“定型運用”に
LAWGUEなら、反社条項を含む契約書テンプレを社内で統一し、案件ごとの文言ブレを減らせます。締結前の確認ポイント(条項有無・最新版か)をチェックしやすく、承認〜保管までの流れも整理できます。
総務・法務・現場のやり取りを一本化して、契約対応を安定運用に。
👉 3分でわかる資料を見る

契約書における反社会的勢力排除条項(反社条項)のひな形・テンプレート
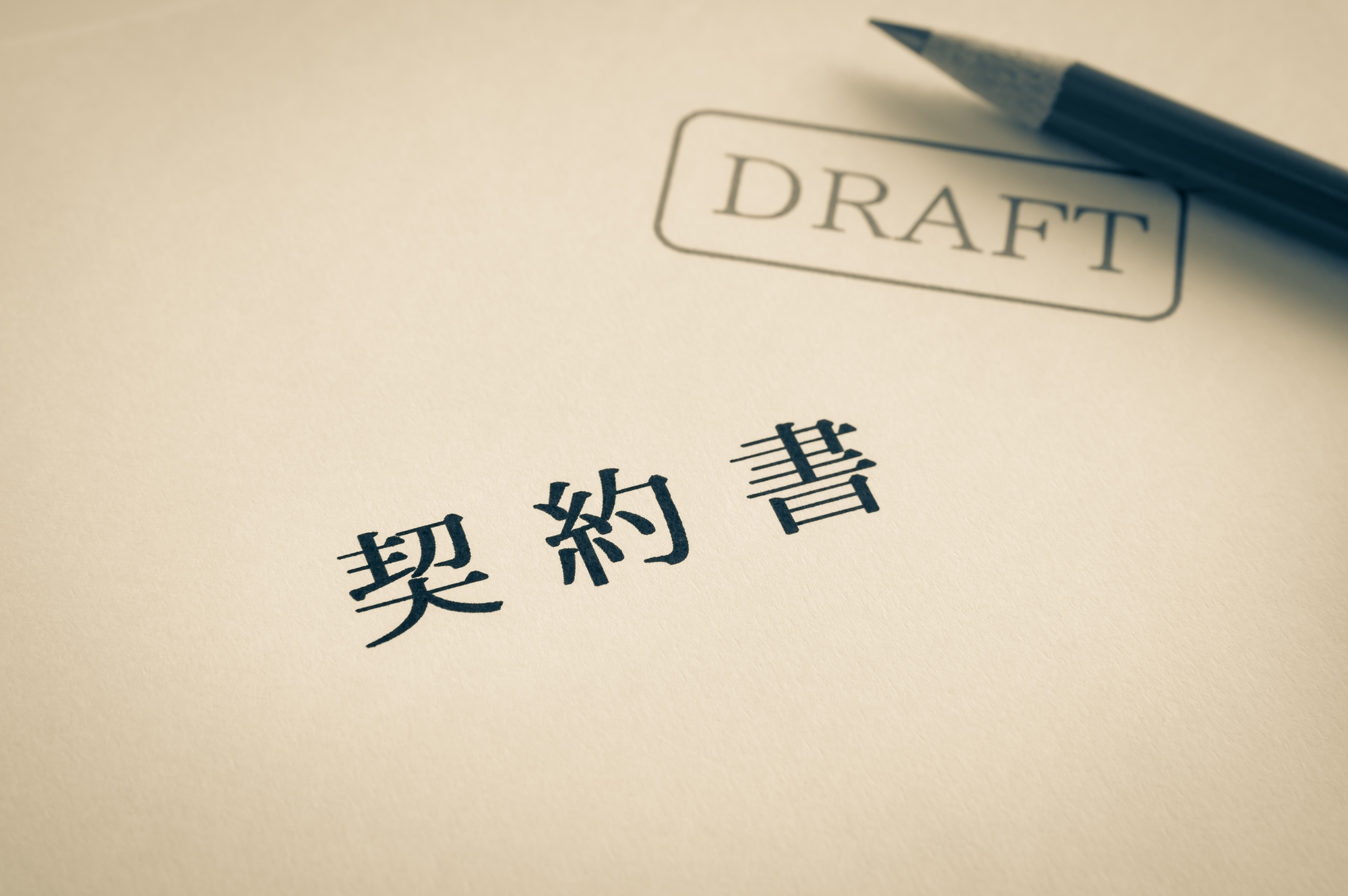
それでは、具体的にどのような反社条項を入れればよいでしょうか。
ここでは、条項のひな形を示し、説明していきます。
①反社会的勢力の定義及び不該当の表明
まず、反社会的勢力とは何かを定義し、自己がそれに該当しないことを表明します。
例えば、以下のような条項が考えられます。
(参考条項例)
甲及び乙は、互いに相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(解説)
①で広めに反社会的勢力を定義し、②で対象者を契約当事者ではなくその周辺の者にも拡大しています。下請・孫請が存在するような契約類型の場合、他の関連企業が登場する可能性がある場合などには、下請・孫請・関連企業も同様に反社会的勢力ではないことを確約させることもあります。
②反社会的勢力との密接関連性の排除
さらに、反社会的勢力との密接関連性を排除する条項を入れることもあります。①が自己あるいは関係者が反社会的勢力でないこと、②で自己が反社会的勢力ではないけれど繋がりはないことを示すことになり、②は①をさらに強化するものです。ただ、②まで入れることはそこまで多くありません。
(参考条項例)
甲及び乙は、互いに相手方に対し、自らが、次の各号について、本契約の締結日においてかつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
①反社会的勢力が経営に関与していないこと
②反社会的勢力を利用していないこと
③反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与していないこと
④前各号のほか、自ら又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難される関係にないこと
③禁止行為の確認
以上の表明で反社会的勢力に関係していないという主体の規定をしました。次に、暴力行為などをしないという行為の規定をします。
(参考条項例)
甲及び乙は、互いに相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。
①反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
②本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(解説)
①は、当該契約の締結に関してのことなので、一般的な禁止行為といえます。
②は、業界や企業によってアレンジを加えます。例えば、一般ユーザーが多く関係するような業態であれば、一般ユーザーへの迷惑行為を規定することがあります。
④違反した場合の契約解除を明記
以上で義務規定・禁止規定を定めたところで、これらに違反した場合の効果を定めていきます。まずは、反社会的勢力との繋がりを一刻も早く断つことが重要ですので、契約解除条項を入れます。
(参考条項例)
甲及び乙は、相手方が第1項ないし前項のいずれかに違反していると合理的に判断したときは、違反した相手方に対し、何らの催告もなく直ちに本契約を解除することができる。
(解説)
通常、契約の解除には催告といってラストチャンスを促す警告を発してからになります。ただ、反社条項は早い対応が重要ですので、無催告解除を許す規定とすることが一般的です。
また、本契約の解除としていますが、多くの契約がある場合には、「甲乙間の取引に関する全ての契約」を解除できるとするなど、広く定めることが考えられます。
⑤違反した場合の損害賠償(違約金)
さらに、反社会的勢力やその周辺の者と取引をしてしまうと、その取引において損害が発生するほか、他の取引先や一般ユーザーへの影響もあり得ます。そこで、解除のほか損害賠償の定めも置いておくのが一般的です。
(参考条項例)
甲及び乙は、相手方が第1項ないし第3項に違反したことにより損害を負った場合、解除した者はその損害の賠償を相手方に請求できるものとする。解除された者は、解除した者に対し、違約金として金〇万円を直ちに支払う。
前項の規定により本契約を解除した者は、解除された者が損害を負ったとしても、損害を賠償する義務を負わない。
(解説)
賠償義務の範囲(損害の範囲)を決めることがあります。例えば、請求に必要な弁護士費用を含むかどうかなどを決めることがあります。一般には、反社条項に違反した場合の損害は制限しないことが多いでしょう。
また、損害額を立証することが難しいこともあることから、あらかじめ賠償額を違約金として定めておくこともあります。
なお、違反した側(反社会的勢力に該当した者・関連した者)からの損害賠償は封じることが一般的です。
契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)を記載しても取引先に不安がある場合

このように契約書に反社条項を入れたとしても、なお相手方に不安を感じることがあるでしょう。そのような場合、どのように対応すればよいでしょうか。
可能な限り情報を収集する
まず一般的にはできる限りの情報を集めるところから始めましょう。上場企業であれば上場時に反社チェックを受けているので問題ないことも多いですが、少しでも不安に感じた場合にはやはり調査をすることが考えられます。
会社名、代表者名、役員名などでネット上の検索をかけるのが手っ取り早いです。SNS上に疑わしい証拠がアップされていることもあります。
企業の登記を取ってみるのも一手です。代表者や役員名が分かるほか、本社所在地も分かります。契約書記載の住所と異なる場合などには、登記上の住所と契約書上の住所の両方を現
地調査に行くこともあります。
このように、まずは一般的に考えられる方法で情報を収集してみて、判断してみるのが良いでしょう。
第三者機関による調査を検討する
一般的に得られない情報については、第三者機関に調査を依頼することが考えられます。
信用調査会社などに調査を依頼することが多いでしょう。どのような情報がほしいかをよく検討し、第三者機関とよく調整しましょう。
ただ、近年では、信用調査会社といえども情報の取得が難しいことも多くなっています。
費用も相応にかかるので、必要性をよく吟味することが重要です。
警察等に相談する
以上のように自己又は第三者機関を通じて調べることがありますが、やはり限界があります。
そこで、警察や暴力団追放運動推進センター(暴追センター)に相談することが考えられます。事案に応じて、可能な範囲で情報が得られる場合があります。
警察に相談する方法は、警視庁のサイトが参考になります。
警視庁「東京都暴力団排除条例 Q&A」
警視庁によれば、契約相手の氏名・生年月日・住所(・可能であれば携帯電話番号等)が分かる資料、契約書等、疑いをもった資料などを準備するとよいとしています。
場合によっては、民事介入暴力に強い弁護士に相談することも考えられます。
反社条項、入れ忘れ・文言ブレを防いで“定型運用”に
LAWGUEなら、反社条項を含む契約書テンプレを社内で統一し、案件ごとの文言ブレを減らせます。締結前の確認ポイント(条項有無・最新版か)をチェックしやすく、承認〜保管までの流れも整理できます。
総務・法務・現場のやり取りを一本化して、契約対応を安定運用に。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
以上のように、反社会的暴力排除条項(反社条項)について説明してきました。
導入のきっかけとなった平成19年の指針からは10年以上が経過し、契約書に盛り込むのはもはや常識と化しています。
条項例は先に示したとおりで、業界や企業に応じて多少アレンジした後は、基本的には使い回していき契約によって少し変化を加えるといった使い方が良いのではないでしょうか。
特にコンプライアンスが重視されるようになってきており、反社条項を入れ、自らも反社会的勢力と関わりを持たないことが企業の存続条件となりつつあります。
是非この記事を参考にし、反社条項を活用いただければと思います。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








