書式フォーマットとは?ポイントや重要性について解説!

今回は法律業界の書式フォーマットについて説明します。書式フォーマットには、どのようなイメージをお持ちでしょうか。見やすくするため、楽するためなどさまざまあるかと思います。
法律業界では、見やすさのほか、「誰かを説得しなければならない」、つまりは論理性や説得性も重視されます。
こうした書式フォーマットの特殊性に着目しながら説明していきます。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
書式フォーマットとは
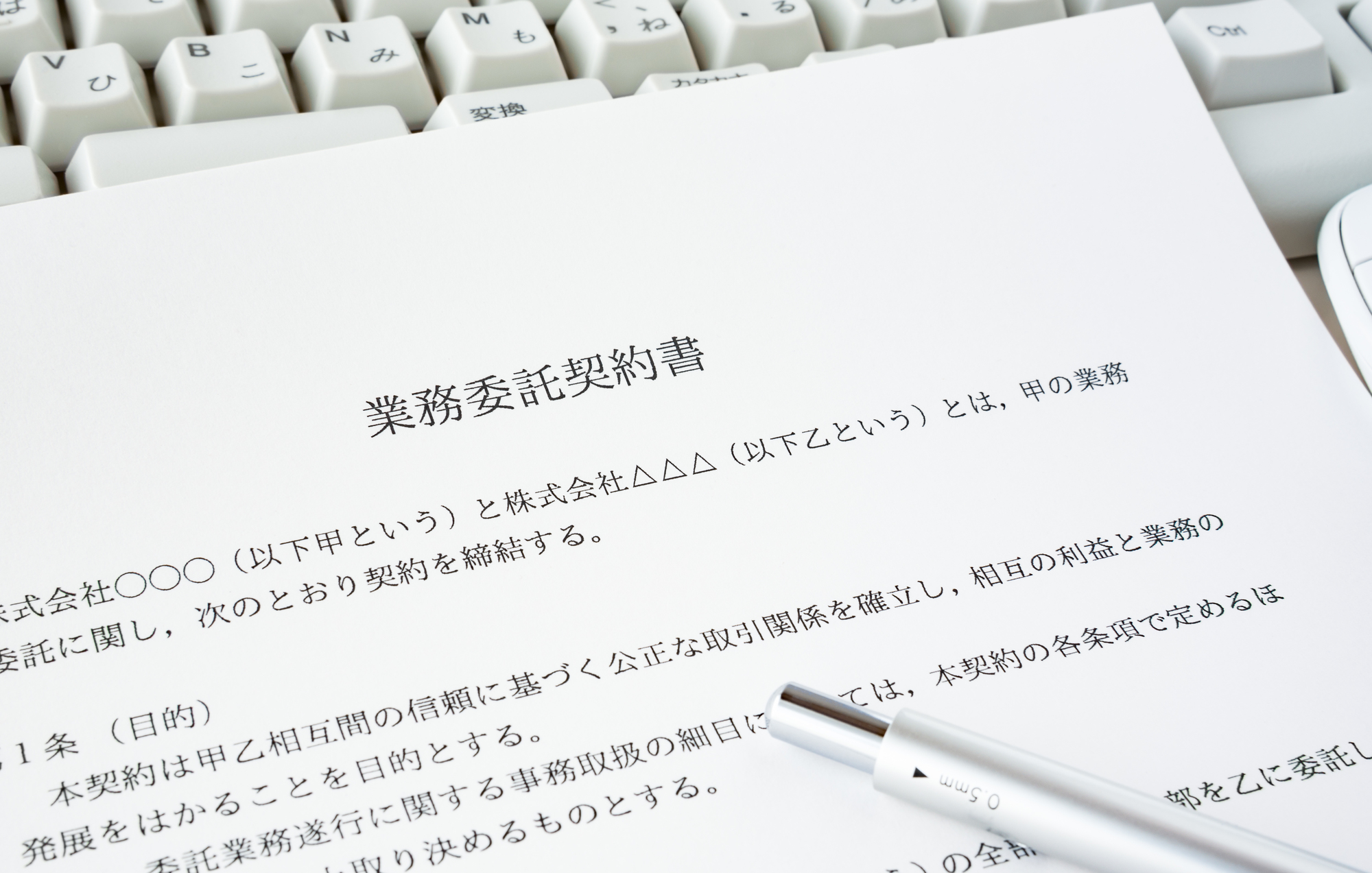
書式フォーマットと言っても、その位置付けや重要性は業界によってさまざまでしょう。
許認可などが絡む業界では、書式フォーマットに従うことなしには業務が動かないくらいのところもあります。医療や建築、不動産などです。
他方で、それ以外の業界では、決まった書式がなかったり、あっても重視されなかったりするところもあるでしょう。
以下、法律業界における書式フォーマットをご説明した上で、その重要性について考えてみます。
定義
書式フォーマットは多義的ですが、法律業界では一般に「決められた様式そのもの」を指したり、「決められた様式で作られた書類」を差したりします。
「〇〇という書類のフォーマットを教えてください」といえば、「〇〇」という書面を作る上での形式的なルールや決まり事(文字の大きさ、余白の大きさなど)を教えてほしいという意味になります。
「〇〇という書類のフォーマットをください」といえば、形式的な決まり事に則った〇〇のひな型がほしい、という意味になります。
法令でフォーマットが決まっているものは多くありません。金融商品取引所等に関する内閣府令で届出書などの要式が決まっていますが、例外的です。
ただ、実務上は裁判所や官公庁が用意しているひな型のとおりに作成することが多く、書式を使わない申請などは出し直しを求められることもあります(裁判所の各種報告書など)。
他方で、ひな型でなくても受理されるものもあり、法令で決まっているもの、出し直しを求められるもの、出し直しは求められないものの順で、書式としての決まりが強いことになります。
書式フォーマットの重要性
前述のとおり、書式フォーマットを使う必要性が法令で定められている場合があります。この場合は、「重要」というより「必須」と呼んだほうがよいでしょう。
さらに、出し直しを求められる性質の書類であれば、事実上法令で定まっているのと同じです。
こうした書類の場合には、書式フォーマットが申請などを適法に行う上で必須の知識となります。
他方、出し直しは求められないものの、書式フォーマットを遵守していないものは、裁判所や官公庁のチェックが厳しくなります。例えば破産の申立書をひな型で出せば裁判所での手続はスムーズになり判断も早くなります。他方でひな型を使わないと、裁判所からの指摘は増え、迅速な判断がもらいにくくなります。
このように、書式フォーマットが必須な場面ではもちろん、それ以外の場面であっても、書式フォーマットを使うことで申請などが通りやすくなったり速くなったりするメリットを享受できることがあります。
書式フォーマットのポイント
法律業界にも様々な書類があり、全ての書類について説明し切れないですが、ここでは一般の方も作る可能性のある「裁判所に提出する書類」について、その書式フォーマットを説明していきます。
フォント
裁判文書は、一太郎ソフトで作られることが多かったですが、ここ15年ほどでWordでの作成が主流になりました。なお、さらに前は縦書きだったころもありました。
フォントに明確な決まりはなくは可読性の高いものであればよいですが、MS明朝体がよく選ばれています。その場合は、英数字も同じMS明朝体で統一します。
タイトルと本文とでフォントを変えるかどうかも決まりはないですが、可読性を重視しタイトルや重要な文言にMSゴシックを使う方法もあります。
裁判官の作る文書はタイトルを含め全て明朝が多かったですが、最近ではタイトルなどをゴシックで強調しているものも見かけるようになりました。
文字サイズ
文字サイズにも決まりはありませんが、12ポイントが基本とされており、注釈を除き、見出しなども同じ12ポイントを使うことが多いと筆者は感じます。裁判官が文字サイズを変えないので、それにならっているのではないかと考えられます。
おそらく、タイトルを含め本文については整然としていることに重きを置かれているからでしょう。文字サイズが違うと行数なども変わってしまうことがあるのも嫌われる理由でしょう。「〇ページの〇行目」という形で言及することがあるため、ページによって行数が変わると扱いが煩雑になってしまうからです。
他方、例えば「訴状」「準備書面」といった書面の標題などは、16ポイントにするなど工夫することも多いでしょう。
行間
行間そのものを意識されることはほとんどありません。
先に述べたとおり、大事なのは1ページにおける文字数(行数)です。1行の文字数は37文字、1ページの行数は26行が標準とされており、多くはこれに従って作られています。
また、後述のとおり、余白もだいたい決められています。
この行数などと余白から、おおむね標準的な行間(1行~1.5行)で作成していると考えられます。おそらくWordの初期設定から変えていないことがほとんどでしょう。
余白
余白についてはっきりとした決まりはありませんが、適切な余白を設定しておくことは重要です。上下は上35mm、下27mmとすることが多いです。左右は左30mm、右は15~20mmとすることが多いです。
下よりも上の方が余白が大きいのは、上にスタンプ(「正本」「副本」や受付印など)を押すことが多いからだと考えられます。
右よりも左の方が余白が大きいのは、左をステープル留めしたり穴を開けたりすることが多いからでしょう。
余白は、受領者が読みやすいようにすることはもちろん、紙での保管方法なども考えて設定しておくことが肝要です。
見出し
見出しは階層を意識するのが大事です。同じレベルの項目であれば、見出しの階層を合わせる必要があります。逆に、違うレベルの項目を同じ階層にするのは、大きく論理性を欠き、書面全体の信用性を失うことにもつながりかねません。
見出しの付け方は行政文書に準じています。第〇、〇、(〇)と続いていきます。
見出しを強調するのに色を使う業界もあると思いますが、法律業界ではあまりみられません。FAXで送ることが意識されるからでしょう。
色を付ける書面も増えてきていますが、見出しに求められるのは論理性であって視認性ではないと筆者は考えています。ある階層の見出しが「~こと」で揃っていて、一部だけ体言止めがあれば、見栄えも悪いですし論理的に文章が間違ってしまうことも起こり得ます。
箇条書き
同じレベルのものを列挙するとき、箇条書きを用いる場合もあります。裁判文書でも多用されている印象です。
例えば契約条項を列挙するのに、
- 第〇条 ~
- 第〇条 ~
のように、簡潔に箇条書きにするケースが多いです。
裁判文書の場合は読みやすさもさることながら、「要素をもれなく記入する」という観点も重要です。
あまり箇条書きに頼ってしまって不完全な日本語になってしまっては元も子もありませんが、そこまでいかなければ、箇条書きは要素を漏れなく記載するのに適した形式といえますので、多用されているのだろうと推測されます。
画像・図表
裁判文書でも、画像や図表を使うことがあります。あるものとあるものを比較する、時系列に分かりやすくまとめるなど、図表と記載したい事項がマッチすることが多く、見やすくもなるのでここぞというところで使います。
ただ、画像はそこまで使わないかもしれません。裁判文書自体が証拠になるわけではないので、画像は書面に入れるというより証拠として別に提出することが多いからだと考えられます。ただ、専門的なもの(建築、医療など)であれば、画像を引用する形で書面にも盛り込むことが多くなります。
あくまで文章が主、画像は補助資料ですので、文章との配置や分量のバランスは考える必要があります。
強調
重要な部分は、フォントを変える、太字にする、下線を引くなどの方法で強調します。
先に述べたとおりフォントサイズの変更による強調は多くありません。色による強調も、あまり使われていません。
一番多く行われている強調は、おそらく下線でしょう。
ただ、下線は引きすぎるとただ見づらくなるだけで、逆に強調できなくなってしまいます。
適度な分量を意識することが必要です。
目安としては、1ページに1箇所、多くても3箇所くらいでしょう。
統一感
全体を通して言えるのは、統一感を持たせることの重要性でしょう。
裁判文書は伝えたいことが階層になっていて、それを書面上でも反映させる必要があります。
書面全体で3つのことが言いたくて、1つ目はさらに4つに分かれていて、2つ目は2つに分かれていて、といった具合です。
書類を読んで階層を意識させるには、統一感が重要です。ある階層の見出しのポイントや強調方法などが統一されていないと、同じ階層であることが認識しにくくなります。
逆にいえば、階層を変えるときにフォーマットを変えると決断したのであれば、全ての階層の変更にも同様のフォーマット変更をすべきです。
文書形式
記事であればhtml形式が推奨されるように、裁判文書はWordで作られることが増えたため、docx形式が多いでしょう。
以前は一太郎のjtd形式もよくみられましたが、裁判所と共有する際にdoc(x)が求められるため、事実上jtdは使われなくなったとみています。
文書の共有の際は、見た目も含め確認いただくことが多いため、PDF形式を用いるとよいでしょう。
書式フォーマットを“迷わず統一”する!
LAWGUEなら、過去の書面やひな形を横断検索しながら、書式・構成をそろえた文書作成を効率化。
条番号のズレや表記ゆれ、構成の不統一を抑えられるため、論理性・説得性が求められる法務文書でも品質を保ちやすくなります。属人化しがちな書式ルールを文書として蓄積・共有でき、チーム全体で安定したアウトプットが可能です。
👉 3分でわかる資料を見る
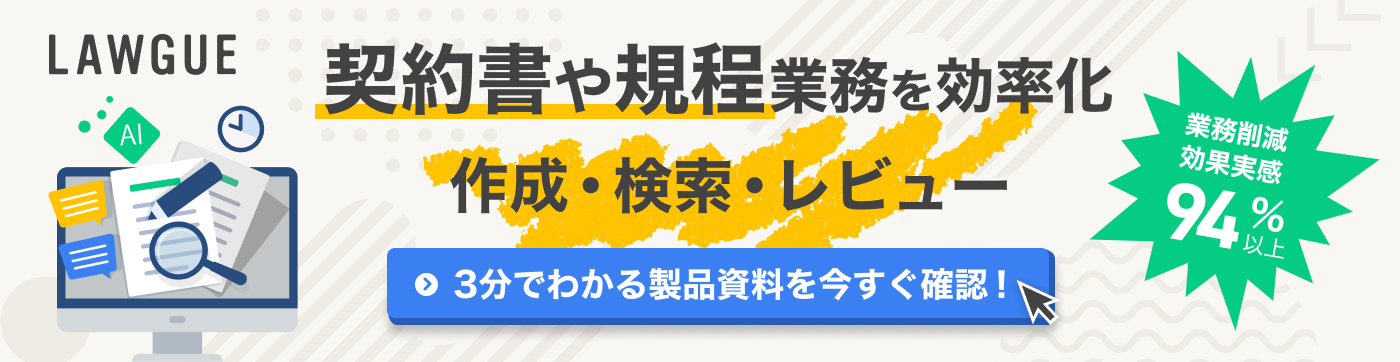
まとめ
以上、法律業界、特に裁判所に提出する文書について説明してきました。
法律で決まった書式フォーマットはありませんが、余白など使い勝手がよいように工夫されており、事実上決まった書式を使っていることが多いでしょう。ただ、ここまでは他の業界と大きく変わらないと思います。
法律業界の特色としては、読みやすさと内容の整理のされ具合が直結している点です。すなわち、階層を含む内容の整理をすれば、自ずと読みやすくなる点に特徴があります。論理的な文章が必要とされるからでしょう。そこで、形式的な強調よりも内容の充実が好まれてきたのだと考えられます。
ただ、色を使うなど、視覚的な見やすさを求める書面も増えてきた印象です。個人的には小手先に逃げているようにも感じてしまいますが、各自工夫する時代に入ってきているように感じています。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








