契約書の修正方法を解説!修正方法のパターンから修正の際の注意点まで
.jpg?fm=webp&q=80&w=1200&fit=crop)
契約の締結後、後から契約書の誤りに気づいたり、事情が変わったりして契約内容を変更する必要が生じる場合があります。
本記事では、契約実務にかかわるビジネスパーソン向けに、契約書の修正の方法やその際の注意点について解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書の修正は当事者の合意がある場合のみ

一度締結した契約書の修正は、当事者の合意によって行うことが必要となります。当事者が合意して締結した以上、その内容で法的拘束力が生じているためです。一方当事者が手元にある契約書を修正しても、効力は生じません。
契約書の修正が必要なケース
契約書の修正が必要となるのは、以下の例のように、契約の締結後に表記の誤りが見つかったり、取引に関する事情が変わったりして契約内容を見直す必要が生じたケースです。
表記の誤りの修正
表記の誤りとして契約書の修正(訂正)が必要となるのは、典型例としては、契約金額や商品名、納期、納品方法の記載を誤っている場合です。これらは契約内容に直接影響しますので、訂正が必要です。
それ以外には漢字の誤りや脱字などがあります。軽微な誤記であればそれだけで契約が無効となることや、意図した内容どおりの法的効力が認められないということにはなりませんが、疑義をそのまま残すよりは、正しい方法により訂正しておく方が適切です。
契約内容の変更
契約締結時点の誤りではなく、契約締結後に事情が変わり、契約内容を見直す必要が生じた場合です。
例えば、次のようなケースです。
- 材料価格の高騰により値上げする必要が生じた場合
- 当初の契約内容で定めた商品が不要となり、代わりに別の商品が必要となった場合
- 災害により納期を遅らせる必要が生じた場合
- 工場の移転により納品場所を変更する必要が生じた場合
このような場合は、当初の契約内容を実質的に変更するものなので、正しい方法により確実に契約書を修正(変更)しておく必要があります。
契約当事者の変更
契約締結後に契約当事者が変わる場合も、契約書の修正(変更)が必要となります。この場合は、後述のように、「契約書の修正(変更)」というよりは、「新たな契約の締結」という面が強いといえます。
例えば、次のような場合です。
既存取引の商流から卸売業者が外れ、小売店とメーカーが直接取引することになった場合
法改正への対応
法改正により、契約当事者が遵守すべきルールが変わり、契約に際して一定の事項を定めておく必要が生じることがあります。これを履行していることを確認するために、契約書を修正するケースもあります。
例えば、次のような場合です。
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が制定されたことから、同法で定められている報酬の支払期日に違反しないように、報酬の支払期日を前倒しする。
契約書の修正方法のパターン
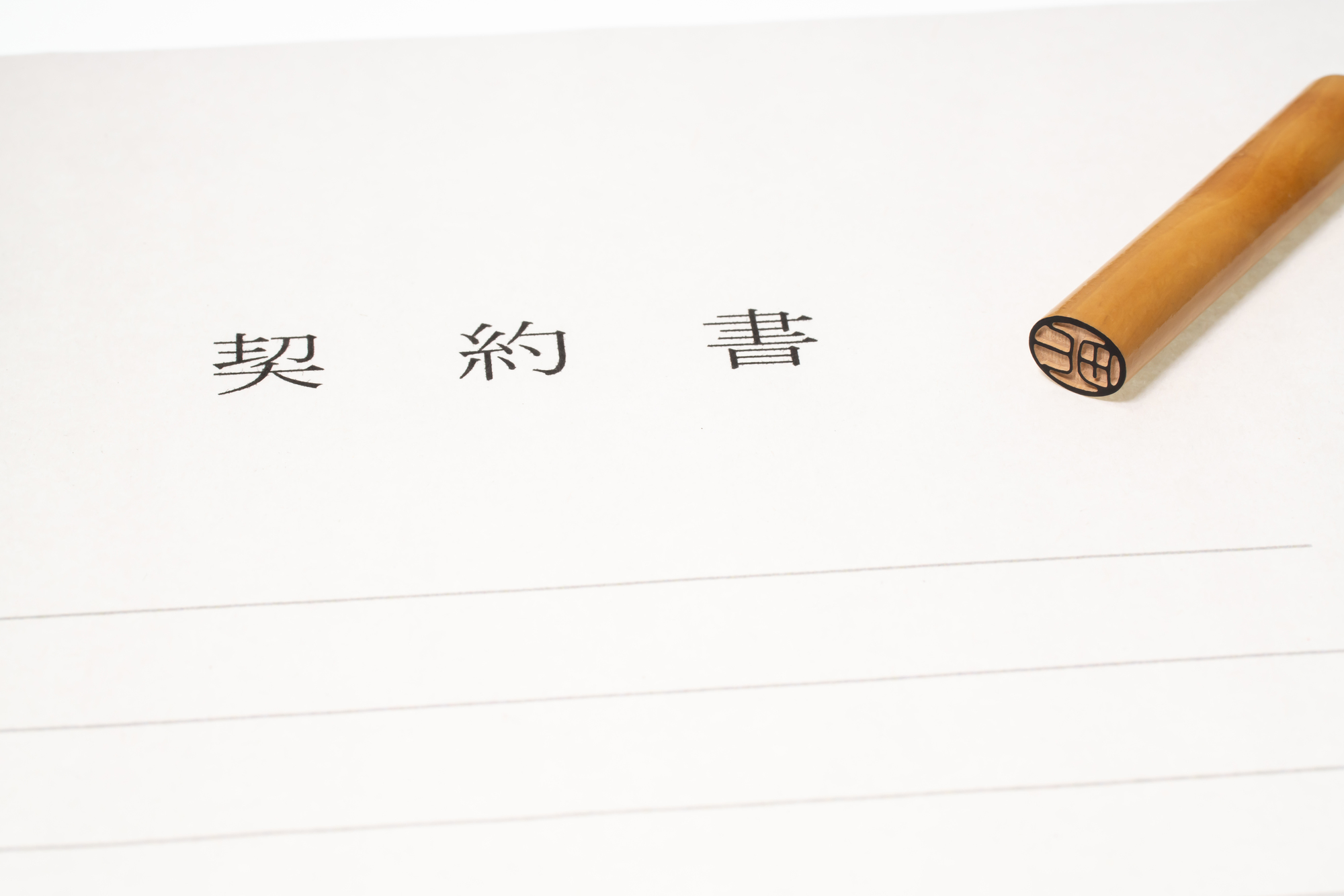
契約書の修正方法としては、例えば次のようなものがあります。目的に応じて適切な方法で行いましょう。誤りの修正の場合は訂正印又は捨印、内容を変更する場合は変更契約書、または新たな契約書による方法が一般的です。
訂正印と二重線による修正
紙の契約書の表記の誤りについては、訂正印により訂正することが一般的です。
- 誤っている箇所をペンで二重線で削除し、そのすぐ上部に正しい文字を記載します。修正前の内容が分かるよう、修正液や修正テープは使用しません。また、修正内容が改ざんされないよう、消えるペンや鉛筆も使用しません。
- 訂正箇所の付近に、「削除2文字、加筆3文字」のように削除した文字数と加筆した文字数を記載します。漢数字を用いると「一」を「二」に書き換えるなど、改ざんが容易なので、英数字を用います。
- 二重線で削除した部分に重ねて訂正印を押します。契約書の修正は当事者全員の合意に基づいて行う必要があるため、当事者全員の訂正印が必要です。また、訂正印は、契約書の締結時の印鑑と同じ印鑑を使用するのが適切です。異なる印鑑を用いると、権限のある者が訂正したのか疑義が生じかねないためです。
捨印を用いた修正
「捨印」とは、後に文書に誤りが見つかった場合に訂正印として使えるようあらかじめ文書に押印しておくものです。文書の冒頭上部の余白に押印しておくことが一般的です。
本来は訂正箇所に当事者全員が押印すべきところ、あらかじめ契約締結の際に訂正印として捨印を押印しておくことで、軽微な誤記などの訂正のために当事者全員に契約書を回付して押印する手続を省略することができます。
反面、捨印を押すことで契約書原本を保有する当事者に訂正を委任することになります。そのため、捨印を押す側としては、重要な事項が書き換えられてしまうリスクがないか、慎重に検討する必要があります。
一部変更契約の締結
取引内容や取引条件の変更などの実質的な変更を行うものの変更箇所が少ない場合は、締結済みの契約書を直接修正するのではなく、これを変更する旨の契約書を新たに締結する方法があります。
変更契約書作成にあたっては、例えば以下の点がポイントとなります。
- 表題は必ずしも「変更契約書」である必要はなく「覚書」などとすることもあります。
- 頭書で、締結時期及び契約書の名称を記載して何の契約を変更するのかを明確にします。
- 訂正印による修正の場合と異なり、変更する文字や数字のみ記載するのではなく、原契約の変更後の条項全体を記載するのが適切です。
- 新たに条項を追加する場合は、挿入箇所を原契約の最後の条項の後にするなどして、挿入によって条文番号がずれないようにします。また、必要に応じて、条文が原契約の既存の条文の対象となるのか否かについても定めておきます。
- 変更契約の効力発生時期を明記します。過去に遡って効力を発生させることも可能ですが、変更契約締結時から将来に向かって生じるとするケースが一般的です。
- 変更された箇所以外は引き続き原契約が効力を有することも明記します。
変更契約書の記載例としては次のようなものが考えられます。
【記載例】
変更契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は、甲及び乙の間の×年×月×日付□□契約書(以下「原契約」という。)に関して、以下のとおり変更契約書(以下「本変更契約」という。)を締結する。本変更契約で用いられる用語は、本変更契約で別途定義される場合を除き、原契約において定義された意味を有する。
第1条(原契約の変更)
1. 原契約第○条を以下のとおり変更する。
(変更前)
……
(変更後)
……
2. 原契約第○条として、以下の条文を追加する。原契約第×条は本条にも適用される。
……
3. 原契約第○条第○項を削除する。
第2条(変更の効力)
1. 本変更契約に基づく原契約の変更の効力は、本変更契約締結日から将来に向かって生じるものとし、原契約に基づき既に行われた行為の効力に何らの影響も与えるものではない。
2. 本変更契約に基づき明示的に変更された原契約の条項を除き、原契約の他の条項は、引き続き有効にその効力を維持する。
変更後の条件を反映した新たな契約書の締結
取引内容や取引条件の変更などの実質的な変更を行い、かつ変更箇所が多い場合は、元の契約書に変更箇所を反映した契約書を改めて取り交わす方法が適しています。
この方法は、最新の契約書のみを確認すれば現在有効な契約条件を把握できる点で優れており、変更箇所が多数に及ぶ場合でなくても採用されることがあります。
また、契約当事者が変更となる場合は、新たな当事者間ではそもそも原契約書が存在しないため、新たな契約書により契約を締結する必要があります。
新たな契約書を締結する場合は、原契約に変更後の契約内容を反映し、原契約と新契約の効力が重複・矛盾しないよう、原契約を終了させる旨記載しておきます。
例えば、次のような条文が考えられます。
第●条(原契約の終了)
甲及び乙の間の×年×月×日付●●契約は、本契約の締結により、本契約の効力発生日をもって終了する。
契約書に修正スペースがない場合の修正方法
修正箇所のすぐ上又は横にスペースがあれば、そのスペースに修正後の内容を記載し、上記のように二重線と訂正印により修正を行うことができますが、スペースが足りない場合は工夫が必要です。例えば、次のような方法が考えられます。
周辺の余白に訂正を記入する
訂正箇所のすぐ上にスペースがない場合、同じページ内のほかの余白部分を利用して訂正することも可能です。この場合、どの部分を訂正したのか明確にするため条文番号(条・項・号)を特定する必要があります。
訂正内容を別の用紙に記載する
同ページ内の余白に収まらない分量の誤りがある場合は、原契約とは別に訂正内容を記載した文書(表題は「覚書」などとすることが考えられます。)を作成する方法があります。
この場合は、契約書名・当事者・締結時期により原契約を特定し、原契約と同じ当事者全員がこの訂正文書に押印する必要があります。
電子契約の場合の修正方法とは?

電子契約の方法により契約を締結した場合、原本ファイルを訂正印や捨印により訂正することは不可能です。
原本ファイルを印刷して訂正印による訂正を行うか、PDFファイルに編集機能で修正することなどが考えられますが、いずれにしても、契約の変更には当事者全員の合意が必要です。
そのため、変更契約書、または新たに契約書を締結する方法によるのが、簡便かつ確実です。変更契約書、または新たな契約書は紙によって締結することも可能ですが、元の契約を電子契約、変更契約書又は新たな契約書が紙であると契約管理が煩雑ですので、元の契約と同様に電子契約による方が適切な場合が多いでしょう。
契約書を修正する場合の注意点

契約書を修正する際は、例えば以下の点に注意が必要です。
- 注意点①当事者全員が合意した内容を反映させる
- 注意点②変更箇所以外への影響を検討する
- 注意点③バージョンの一元管理
- 注意点④収入印紙の貼付を忘れない
注意点①:当事者全員が合意した内容を反映させる
契約書の修正は、いずれの方法による場合も当事者全員の合意が必要です。一方当事者が勝手に修正しても有効になりません。
契約当事者間で訴訟となった場合は、契約書が重要な証拠となることが多いですが、契約書は原則として原本を証拠として提出することになるため、一方当事者が勝手に原契約書の記載を削除、加筆などをしても結局は発覚する可能性が高いです。このような修正は有効な契約と認められません。
また、他の当事者と合意の上修正する場合も、悪意ある修正や改ざんができてしまうと自社に損失をもたらすことになりかねないため、例えば、次のような点に注意しましょう。
- 当事者全員が合意した修正内容が修正箇所に正確に反映されているか確認する。また、契約書の修正を機に、悪意ある他方当事者が合意していない点まで修正しようとすることがあるため、合意していない内容が記載されていないか確認する。
- 捨印を求められた場合は、相手方当事者が信頼できるのか慎重に検討する。そもそも取引内容や条件が記載されている重要な文書に捨印を押すことは極力避ける。
- 訂正内容を書き換えられてしまう可能性がある鉛筆、消えるペンや、訂正内容を消されてしまう可能性のある修正液や修正テープは使用しない。
- 漢数字を用いると「一」を「二」に書き換えるなど改ざんが容易なので算用数字を用いる。
注意点②:変更箇所以外への影響を検討する
契約書の修正により、原契約の変更箇所以外の条項にずれや矛盾が生じないか検討する必要があります。例えば次のような場面が考えられます。
原契約に、各条文の存続期間について定めた条文(第●条は本契約終了後も×年間継続する。」といった条文)がある場合に、新たに条文を追加することで対象となる条文番号がずれたり、追加の必要が生じたりする場合は、適用対象となる条文番号も併せて修正する。
このような変更箇所に関係する原契約の条文が多い場合は、適用関係が複雑になるのを避けるため、変更契約書によるのではなく新たに契約書を締結し直す方法も選択肢です。
注意点③:バージョンの一元管理
最新の有効な契約書の内容を確実に把握できるよう、修正後の契約書は原契約とともに一元的に管理しておく必要があります。修正が複数回行われた場合や、契約締結時と担当者が変わった場合などは、特に最新の有効な契約内容が分からなくなることが少なくないため、注意が必要です。
その際は、例えば次のような点に注意しましょう。
- 原契約書と変更契約書・新たな契約書は同じ場所に保管する(紙であれば同じファイル、電子契約であれば同じフォルダに保管しておく。文書管理ツールを用いる場合は各契約書を紐づけておくなど。)
- 変更契約により変更した箇所をさらに変更する場合は、新たな契約書を締結し直すなど、複数の契約書を参照しなければならない状況を避ける
注意点④:収入印紙の貼付を忘れない
変更契約は一度締結済みの契約の内容を変更するものなので、収入印紙の貼付を失念しがちです。変更契約であっても、原契約の重要な事項を変更する場合は印紙税の課税文書に該当し、収入印紙の貼付が必要となります。
貼付が必要な印紙の金額は、文書の種類や取引金額によって異なる点は原契約の場合と同じです。
国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)では、変更契約の場合に印紙税の課税文書と扱われる例として、次のものが挙げられています。
- 工事請負契約書により定めた取引条件のうち、工事代金の支払方法を変更する場合
- 製造請負基本契約書により定めた取引条件のうち、製品の納期を変更する場合
- 清掃請負基本契約書により定めた取引条件のうち、清掃範囲を変更する場合
契約書の「修正漏れ」をゼロに
LAWGUEなら、差分比較・版履歴の可視化・表記ゆれ/不足条項の検知までワンストップ。
クラウドで最新版を一元管理できるから、変更契約も迷わず正しい版でレビューできます。実務の手戻りを根本から削減。
👉 3分でわかる資料を見る

まとめ
以上、契約書の修正が必要となるケースと修正時のポイントを解説しました。
修正方法を誤ると契約の有効性に疑義が生じたり、トラブルに発展したりする可能性がありますので、適切な対応をするために、本記事を参考にポイントを押さえておきましょう。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








