リーガルチェックとは?重要性や、社内実施・弁護士依頼の流れ、費用を解説

事業をしていると、日々契約書の作成業務が生じます。その契約書の法的リスクを減らすのがリーガルチェックです。
どうしてリーガルチェックが重要なのかをご説明した後、社内のリーガルチェックと社外(特に弁護士)のリーガルチェックについてそれぞれご説明していきます。最後には、リーガルチェックをする上でよくあるチェック項目もご説明します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
契約書のリーガルチェックとは?

契約書のリーガルチェックとは、契約書に含まれる法的リスクを洗い出す作業のことです。法務チェックという言い方をするときもあります。
契約書は、時に法令に違反して無効とされたり、無効とまではいえなくても当方に不利になったりします。さらには、当方の言い分が十分に反映されていないときもあるかもしれません。そうした法的リスクを、契約締結前に洗い出す必要があるのです。
リーガルチェックすべき契約書とは
非常に多岐にわたります。例えば以下のものになります。
- 企業間の取引に関するもの
取引基本契約書や個別契約書、単発の売買契約書など - 企業間の業務に関するもの
業務委託契約書など - 取引の前提になるもの
秘密保持契約書(NDA)など - サービス受領者に関するもの
約款、プライバシーポリシーなど - 従業員に関するもの
雇用契約書や就業規則など
契約書のリーガルチェックが重要な理由

契約書のリーガルチェックが重要な理由は、主に以下の5点です。
- 法令違反の契約を結ぶことを回避するため
- 自社にとって不利益な条項を是正するため
- 契約が無効になってしまうのを防ぐため
- ルールブックとして実際の取引に役立てるため
- その他のトラブルを避けるため
以下、1つずつ説明していきます。
法令違反の契約を結ぶことを回避するため
法律は強行法規と任意法規に分けられます。強行法規というのは、「これに反する契約はできない」というもので、強行法規違反の契約は(一部)無効になります。
この強行法規の中に、「これの記載が漏れていると無効になる」というものがあります。典型例はクーリングオフです。この場合の契約書を法定書面と呼ぶこともありますが、法定書面に不備があると、いつでもクーリングオフができてしまうため、記載事項の漏れがないかは特に確認する事項です。
自社にとって不利益な条項を是正するため
無効とはいえないまでも、自社にとって不利益なものがあれば、法的リスクとして洗い出します。
例えば代金の支払い方法や返品の可否などに不利なものはないかをみていきます。近年では、知的財産の帰属もよくチェックの対象になります。
難しいのは、無効とは異なり、不利益は飲み込めるということです。力関係からみて妥協したり、経営判断に委ねたりします。
契約が無効になってしまうのを防ぐため
先に説明した強行法規は、反すると契約が無効になってしまいます。そこで、リーガルチェックでも、強行法規違反がないかをみていきます。
代表例としては労働基準法、利息制限法、消費者契約法などですが、近年では公正な取引を実現するため、社会的に弱い立場の者を保護するような強行法規も増えてきました。下請法やフリーランス法などです。法改正も多く、正確な知識が求められるので注意が必要です。
ルールブックとして実際の取引に役立てるため
取引を行っていると、あいまいになっていて不都合が生じていたり、ミスが起きたりすることもあります。
こうした不都合やミスを、契約書に落とし込む作業が必要です。こうしてできた契約書は、実際の取引のルールを書いたものとして機能します。
例えば発注の仕方、検品の仕方などを、実態に合わせてあるいはミスが生じないように契約書に盛り込んでいきます。
その他のトラブルの発生を防ぐため
契約書には様々な要素があり、あいまいにしておいた方がよいもの、きちんと決めておいた方がよいものなど多様なものが含まれます。
トラブルの未然防止のため、文言の定義に漏れがないかみる、条項間に矛盾がないかみる、それぞれの条項の有効期間が必要十分かを検証するなどもリーガルチェックの一環です。例えばNDAなどでは、秘密情報の範囲や有効期間が主なチェックポイントです。
リーガルチェックを社内で実施する流れ
それでは、実際にリーガルチェックを実施する流れをみていきます。社内で実施する場合と社外で実施する場合がありますが、まずは社内で実施する場合をみていきます。
主に下記の流れになります。
- 取引をする部署から依頼を受け付ける
- 契約書の全体像や重要条項を把握する
- 内容・体裁共に修正点を洗い出す
- 担当部署に返答し、契約相手方と交渉する
- 内容確定後、相手方と契約を締結する
①取引をする部署から依頼を受け付ける
多くの企業では、法務とそれ以外は分かれていると思います。取引関係であれば営業から、労務関係であれば人事から、法務にリーガルチェックの依頼が来ます。
企業によって依頼の方法は異なりますが、可能な限り方法は一本化し、漏れがないようにするのが肝要です。
リーガルチェックで重要なのは、①期限と②交渉の余地の有無です。依頼する側は、できるだけ明確に①いつまでチェックすべきか(その理由)、②相手方との関係でどの程度交渉できそうか、この契約がどれくらい重要なのかを伝えるようにしましょう。
②契約書の全体像や重要条項を把握する
法務が依頼を受けると、担当者が複数いれば誰が担当するか、複数人に当たらせるかを決めます。
ここからは、新規の契約なのかまき直しなのかによって変わってきます。
新規の契約であれば、契約自体の重要性、相手方との取引の重要性なども踏まえつつ、契約書の全体像を把握し、重要な条項を見つけていきます。特に法令違反がないか、自社に不利にならないかなどに着目していきます。
まき直しであれば、変更点に注目すると共に、変更しない点についてもこれまでのトラブルを落とし込み、法改正も落とし込む必要があります。
③内容・体裁共に修正点を洗い出す
重要な条項を中心に、問題点を拾い出し、どう修正すればよいかを検討していきます。社の方針や法務の立ち位置にもよりますが、グラデーション(修正必須、なるべく修正したい、可能であれば修正したい、修正は不要だが交渉次第で盛り込みたい、趣味のレベルなど)も付けると良いでしょう。
体裁も修正対象ですが、条項番号がズレることもありますので、最後に確認することを忘れないようにしましょう。
④担当部署に返答し、契約相手方と交渉する
修正点を記載したものを、担当部署に戻します。戻し方も社によって異なると思いますが、ドキュメントやスプレッドシートなどで管理しているところが多いと思います。
最終的に相手方と交渉するのは担当部署でしょうから、修正の目的も含めて理解してもらう必要があります。修正の理由と修正の必要性の程度は明確に伝えておくべきです。
⑤内容確定後、相手方と契約を締結する
相手方と何往復かするかもしれませんが、最終的に契約内容が固まり、契約締結となります。以前は紙が一般で、契印・割印や印紙の知識も必要でしたが、最近では電子契約が主流になりつつあります。
注意しなければならないのは、保存期間と要式性のあるものでしょう。保存期間は業界によって法律で定められていることがありますし、書類によっては税法上の決まりもあります。内部規程で定まっている場合もあるでしょう。
要式性とは、多くはありませんが、業界や契約書によっては公正証書などで形が決まっているものがあります。
リーガルチェックを弁護士に依頼する流れ
続いて、リーガルチェックを社外で実施する場合について説明します。
弁護士に依頼することになるでしょうが、主に下記の流れになります。
- 確認してほしい契約書と申し送り事項を用意する
- 弁護士にリーガルチェックを依頼する
- コメントを確認し、疑問点があれば問い合わせる
- 契約書を修正し、契約相手方と交渉する
- 内容確定後、相手方と契約を締結する
①確認してほしい契約書と申し送り事項を用意する
まず、確認してほしい契約書と申し送り事項を法務で検討します。
顧問弁護士でありかつまき直しであれば、ある程度理解できてはいるとは思いますが、それでも申し送り事項があると助かります。
申し送り事項として考えられるのは、例えば次のような点です。
- 取引及び契約相手方の概要
- 新規かまき直しか
- 交渉の余地がどの程度あるか
- 気になっている条項とその理由
- 譲れない点があればその点とその理由
特にNDAの場合、どのような秘密情報をやりとりする可能性があるか、どちらが秘密情報を出すことが多そうかも教えてもらえると助かります。
②弁護士にリーガルチェックを依頼する
通常は法務(時に代表・秘書)から弁護士に、契約書と申し送り事項を送付します。
共有の仕方は様々ですが、メールやクラウド上で共有することが多いでしょう。
弁護士にリーガルチェックをする上で大事な点は、①期限と②料金です。社内で検討するときと同じように、いつまでにリーガルチェックをする必要があるのか、急ぐのであればその理由を共有いただきたいです。リーガルチェックは、訴訟などと異なり、書面からは必ずしも期限が分からないからです。また、②顧問料に含まれるかどうかも、顧問契約をご確認ください。
③コメントを確認し、疑問点があれば問い合わせる
弁護士は、メールの返信やクラウド上のコメントなどの方法で、基本的に法務にお返しします。
温度感や取引実態を把握し切れているわけではありませんので、どうしてもコメントが見当違いになることがあります。そのときは、質問も含めご相談いただけるとよいです。「法的にはそうだが、当社ではこういった点でそれは難しいのでこういった代替案は可能か」といった具合です。
先に述べたとおり、契約書は無効にならない限り修正可能であって、答えは1つではありません。
④契約書を修正し、契約相手方と交渉する
弁護士のリーガルチェックを踏まえ、契約書を修正し(あるいはチェックを踏まえてもなお修正しないと決断し)、契約相手方と交渉します。
場合によっては相手方と何往復かし、時々また弁護士のリーガルチェックが必要になる場合もあるでしょう。その場合にも、弁護士に丸投げはせず、「先方からこういう要望が出されてきたけれど、ここまでは飲めるがここはこうしたい」などと譲歩のラインを教えていただけると助かります。
⑤内容確定後、相手方と契約を締結する
最後に、相手方と契約を締結します。これは社内の場合と変わりません。
弁護士のリーガルチェックは、近時の法改正なども含まれていたり、最新の裁判例に基づいていたりしますので、ある程度汎用性のあるコメントも多いはずです。可能な限り社内で蓄積・共有いただき、同様の契約締結の際に活かしていただくのがよいでしょう。
リーガルチェックの費用の目安

弁護士にリーガルチェックを依頼する場合の費用は、顧問契約の範囲内であればそれで対応可能です。スポットで依頼する場合の費用の目安について、説明します。
弁護士に依頼する費用の相場
単純な契約書(売買契約書、賃貸借契約書など)であれば、3万円から10万円くらいの幅で収まるでしょう。
他方、内容が重要であったり専門的であったりする契約書(株主間契約書、事業譲渡契約書、特許権や商標に関する契約書、テレビなどの出演契約書など)、日本法以外の知識が必要な契約書などであれば、10万円から数十万円といったあたりですが、ものによっては数100万円以上になる場合もありますので、担当の弁護士によく確認しましょう。
また、タイムチャージで受けることもあります。時間当たりの報酬は、弁護士によって異なりますが、最終的な金額は相場からは大きく外れないでしょう。
費用を抑えるには?
申し送り事項を充実いただくのが早道です。特にタイムチャージで受ける場合などは、かかる時間が減りますので費用も抑えられます。
事前に検討いただきたいのは例えば以下のような点です。
- 事業における相手方の位置付けの整理
- 事業における当該契約の位置付けの整理
- 疑問点の洗い出し
- まき直しの場合の変更点の指摘
- 実現したい事項の整理
- 拒否したい事項の整理
- 相手方との交渉の難易度
また、期限がタイトであれば他の案件より優先させる必要が出てくるので費用が高額になる傾向にあります。ある程度早めにご依頼いただけるとディスカウントが効く可能性があります。
リーガルチェックの際のポイント

最後に、リーガルチェックをする際のポイントについてご説明します。実際には契約書や状況によって大きく異なりますので、以下はよく出てくるポイントとお考えください。
内容面でのポイント
①契約の目的に過不足がないか
案外軽視されるのは、契約の目的条項です。契約の文言に疑義が生じた場合、契約の目的を踏まえて解釈されることになりますので、契約の目的に過不足がないかをチェックします。
②契約の重要部分が取引の目的を満たしているか
売買契約であれば目的物の特定と代金の支払い、NDAであれば秘密情報の定義と契約期間など、契約の重要部分をみていきます。当該取引として実現したい内容が網羅されている必要があります。
③違反した場合や解約したい場合などの緊急事態に対応しているか
契約は、通常の取引を規定すると共に、違反した場合や解約したい場合など、緊急事態についても規定されています。相手方が違反しそうであればペナルティを厚めにする、契約関係から解放されやすくしたいのであれば解約条項を使いやすくするなど、平時以外の場面を想定してチェックをします。
④変更点に対応可能か
まき直しなのに条項の修正要望が入っている場合には、先方の要望、すなわちこちらに不利になり得る事項が入っていることがほとんどです。変更点が対応可能か、当方に不利になりすぎていないか、妥協の範囲を超えているかなどについてチェックしていきます。
ラリーが行われている場合にも、先方が出してきた案に付された修正点には着目しておくべきです。
体裁面でのポイント
①契約当事者は合っているか
特に関連企業がある場合などには、当該契約の主体として適切かはチェックします。許認可の関係でグループ会社の中の特定の会社でしか契約できない場合などもあります。
②定義ズレはないか
ある条項である文言を定義した場合、その後の条項でその定義が機能しているか、意味合いが変わっていないかなどをチェックします。別の要素が含まれている場合には定義のし直しをしたり、元の定義条項を修正したりします。
「本件〇〇」と「本〇〇」など、表記揺れも生じやすいので注意が必要です。
③誤記はないか
案外多いのが、不動産の特定や金額の誤記です。ただ、これは弁護士のリーガルチェックではまず防げないので、主に法務がチェックすべき事項になります。
④条項ズレはないか
非常に多いのが、条項を挿入したために条項番号がズレてしまった場合です。「前条の」としていたところ、一つ前に別の条項を挿入したために「〇条の」と修正しなければならなくなった場合などもあります。
AIが“考える”ではなく、あなたの判断を支える「法務パートナー」
LAWGUEは、契約書レビューや規程管理に必要な比較・修正・条文検索をAIが支援。
自社ナレッジと外部情報を組み合わせ、常に正確で最新の判断を後押しします。
人の経験を活かしながら、レビューの質とスピードを両立。
👉 3分でわかる資料を見る
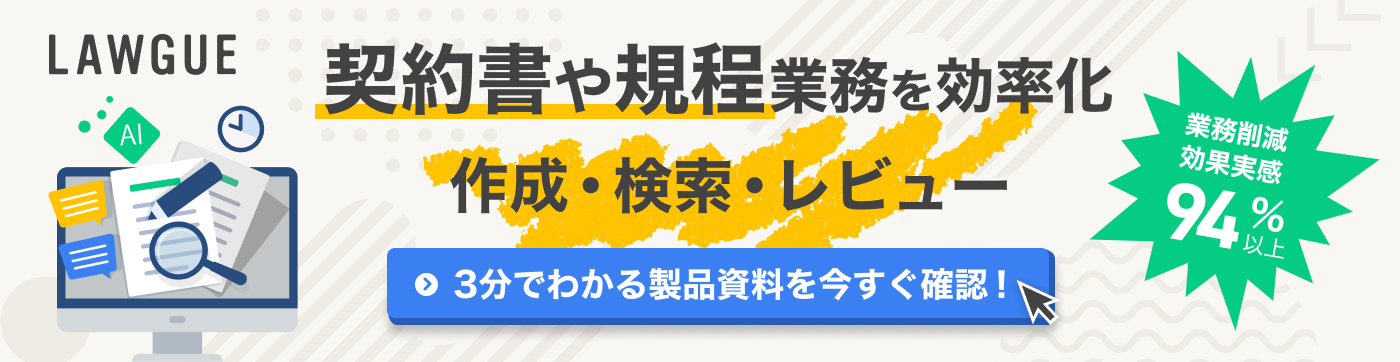
まとめ
以上、契約書のリーガルチェックについて説明しました。リーガルチェックは、契約書が無効になるリスクを減らし、不利になるリスクも減らします。社内でのチェックと社外でのチェックをうまく使い分け、法的リスクの軽減に努めてください。特に重要な契約書や初めての類型の契約書には、どのような問題が含まれているか分かりません。早めにリーガルチェックを受けるよう、心がけてください。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








