文書管理業務とは?目的や具体的な管理方法、ポイントを解説
.jpg?fm=webp&q=80&w=1200&fit=crop)
企業や団体において、日々の業務で作成・受領される文書は多数存在します。こうした文書を効率的かつ適切に管理することは、組織運営の効率化だけでなく、こういった文書が証拠として裁判で証拠として用いられることもあることから、法的リスクの回避にも直結してきます。本記事では、「文書管理業務」とは何か、その目的や具体的な手法、業務成果を高めるためのポイントについて、法律の観点も交えて丁寧に解説します。
【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験
👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー
👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで
👉 不足している条項をAIが提案
文書管理業務とは?
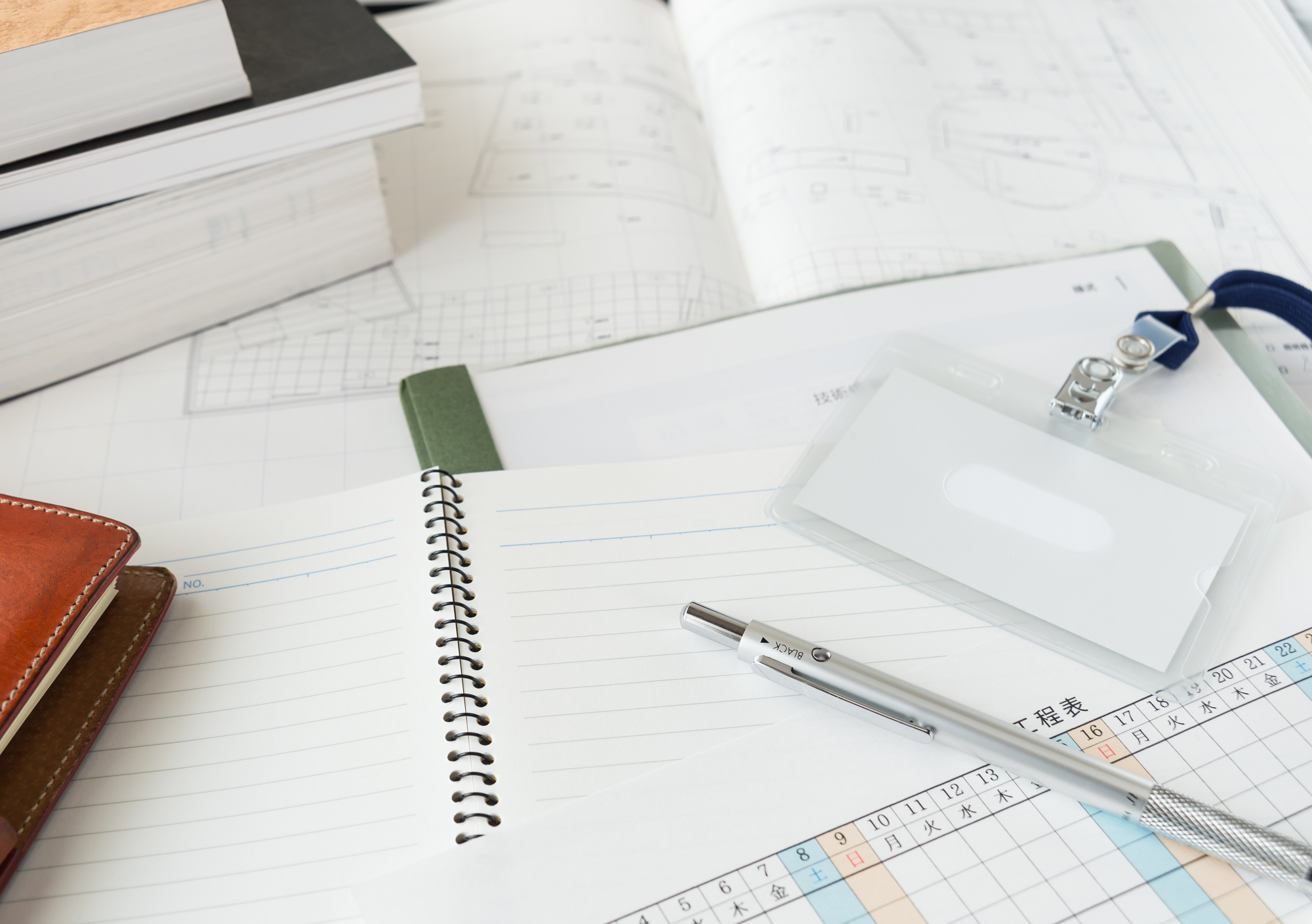
文書管理業務とは、業務上作成・取得するあらゆる文書を、作成から保存・廃棄に至るまで一貫して整理・管理する業務です。文書の所在や内容が明確になり、情報共有や証拠保全の観点からも非常に重要です。
業務文書の種類
企業における業務文書は、大きく「規定」「業務要領」「マニュアル」「様式・帳票」に分類され、それぞれ異なる役割を担います。
まず「規定」は、組織全体の行動基準やルールを定める最上位文書であり、就業規則や情報セキュリティ規程などが含まれます。次に「業務要領」は、規定で定めた方針を現場の具体的な手順に落とし込んだもので、業務の標準化を目的とします。
「マニュアル」は業務要領をさらに作業レベルにまで詳細化し、誰でも同じ作業ができるよう図解や手順を明確にした文書です。
そして「様式・帳票」は、申請書や届出書といった定型フォーマットで、業務情報を統一的に記録・管理する役割を果たします。
これらは「規定」から「様式・帳票」へと段階的に具体化され、組織内の業務運用を円滑かつ効率的に支えています。
このように、各業務文書がどの文書に該当するのかを意識して体系的に整理・整備することで、文書管理の質が飛躍的に向上します。
文書管理業務の目的
文書管理業務は、単なる整理整頓にとどまらず、組織の業務効率化や情報共有を促進するために不可欠な役割を担います。ここでは、文書管理業務の目的について詳しく解説します。
組織的に管理することで共有や検索の時間を短縮する
業務文書を組織的に管理する最大のメリットは、必要な情報へのアクセス時間を大幅に短縮できる点にあります。文書が体系的に整理されていれば、誰が探しても、その体型に従って検索しさえすれば迷うことなく目的の資料にたどり着けるため、業務のスピードと精度が向上します。特に、部署や担当者をまたぐプロジェクトでは、情報共有がスムーズに進み、無駄なやり取りや確認作業を削減できます。
また、過去の経緯や承認履歴なども簡単に追跡できるため、トラブル発生時にも迅速な対応が可能です。適切な文書管理は、企業のリスク管理や、組織全体のパフォーマンス向上に直結するといえるでしょう。
文書管理のルールが浸透するようプロジェクトを推進させる
文書管理を円滑に進めるには、単に整理方法を定めるだけでなく、組織内にルールを徹底的に浸透させることが重要です。そのためには、文書管理の標準化を目指すプロジェクトを立ち上げ、関係部署を巻き込みながら計画的に推進する必要があります。ルール作成時には現場の意見を取り入れ、実用性を高めることがポイントです。また、研修やマニュアル整備を通じて全社員への周知を徹底し、ルール遵守を組織文化として根付かせることが求められます。
ルールについては一度定めたらそれで終わりにするのではなく、継続的な運用と見直しも行いながら、プロジェクトを段階的に進めることが成功の鍵となります。
文書管理の具体的な業務内容

文書管理の手法にはさまざまなアプローチがありますが、ここでは代表的な手法をいくつかご紹介します。いずれの手法にも一長一短があり、自社の置かれた状況等を踏まえて、自社にあった方法を構築していくことが重要です。
ワリツケ方式とツミアゲ方式を組み合わせた「ハイブリッド方式」
文書管理における「ハイブリッド方式」とは、ワリツケ方式(トップダウン型)とツミアゲ方式(ボトムアップ型)を組み合わせた分類手法です。
ワリツケ方式では、上位組織の視点から業務区分や管理方針に基づき文書を体系的に分類します。これにより、組織全体で統一された整理基準を作ることが可能になります。一方、ツミアゲ方式は、実際に現場で扱われている文書群を基にカテゴリを形成するため、実務に即した柔軟な管理が実現できます。
ハイブリッド方式では、まず組織全体の基本的な分類枠組みをワリツケ方式で設計しつつ、現場の実態に応じた調整をツミアゲ方式で行うことで、理論と実務の両立を図ります。このアプローチにより、使いやすく、かつ抜け漏れのない文書管理体系を構築することが可能になります。
書類のライフサイクルを理解して管理する「ファイリングシステム」
ファイリングシステムとは、書類のライフサイクルを理解し、各段階に応じて適切に管理する仕組みを指します。書類のライフサイクルは、作成・受領に始まり、活用・保管を経て、最終的に廃棄される流れで構成されます。各段階で必要な管理方法や保存基準を明確にすることで、効率的な文書管理と情報資産の保護を両立できます。
たとえば、現行業務で頻繁に使用する書類は即座に取り出せる形で管理し、一定期間を経過した後は、保管専用スペースへ移動するなどのルールを設けます。また、保存期限が過ぎた文書は、適切な廃棄手続きに従い処理する必要があります。ファイリングシステムを導入することで、文書の所在が明確になり、業務の効率化やコンプライアンス対応にも大きな効果を発揮します。
①バーチカルファイリング
書類を個別フォルダに入れ、キャビネット内に縦置きで保管する方式です。出し入れがしやすく、検索性に優れるため、日常的に使用する文書管理に適しています。
②ボックスファイリング
書類を分類したうえでボックスにまとめて保管する方式です。大量の文書を一括管理できる反面、個別検索にはやや手間がかかります。長期保存文書に適しています。
③薄冊式ファイリング
書類をテーマ別に薄い冊子状に綴じて保管する方式です。中規模の文書群を整理しやすく、閲覧や持ち運びにも便利です。定期的な更新にも柔軟に対応できます。
文書管理業務の成果を高めるポイント

文書を管理するにも、分類や整理がされていなければ、文書を探すだけでも毎回余計な手間がかかってしまいます。文書管理業務の成果を高めるには、以下のポイントが重要です。
まとめ方・並べ方の明確な基準を決める
どの文書をどこに・どう分類するかのルールを明確に定め、組織全体で共有しましょう。混乱を防ぎ、誰でも同じ方法でアクセスできます。
MECEに文書分類する
文書管理においては、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)、すなわち「漏れなく、重複なく」分類することが重要です。MECEに分類することで、どの文書も一意に整理され、探しやすくなり、管理の手間も大幅に削減されます。
たとえば「契約書類」「社内報告書」「会議資料」といったように、分類基準を明確に設定し、文書がどのカテゴリにも重複せずに収まる状態を目指します。曖昧な分類や二重登録を防ぐことで、情報の整合性が保たれ、業務の効率化やリスク管理にもつながります。文書分類を行う際は、初めにMECEの原則を意識して設計することが成功の鍵となります。
同一階層内のレベル感を統一する
文書管理においては、同一階層内で文書のレベル感を統一することが重要です。レベル感が統一されていないと、分類が不自然になったり、情報の探しにくさを招いたりします。
例えば、第一階層に「人事」「総務」「経理」と並べた場合、そこに「給与明細」など個別具体的な項目を並列させるのは不適切です。あくまで同じ抽象度・粒度で項目を揃えることが、整理された体系を作るポイントです。レベル感の統一を意識することで、利用者にとって直感的にわかりやすい文書構造を実現できます。
全ての文書を同じ構成で作成する
文書管理業務を円滑に進めるためには、全ての文書を統一された構成・フォーマットで作成することが重要です。文書の作成者が異なっても、基本的な構成が統一されていれば、読む側にとって理解しやすく、情報の比較や確認も迅速に行うことができます。
たとえば、タイトル、目的、背景、手順、注意事項といった項目を共通化することで、どの文書を開いても情報の流れが一貫している状態を作ることができます。また、統一された構成は、後から情報を検索・整理する際にも非常に効果的です。
さらに、法的な証拠管理の観点からも、統一されたフォーマットは重要です。記載漏れや不備を防ぐとともに、記載の趣旨等を巡る無用な争いを防ぎ、第三者に対しても文書の正確性と信頼性を示すことができます。統一のためには、テンプレートを作成・配布し、作成時のガイドラインを明示することが有効です。組織全体でルールを徹底することで、文書管理の品質が飛躍的に向上し、業務効率化やコンプライアンス強化にもつながります。
文書管理業務の属人化を防ぐ!
LAWGUEは、契約書や社内規程などの業務文書を一元管理できる文書管理プラットフォームです。ひな形や過去文書を横断検索しながら作成でき、最新版の判別や更新履歴の把握も容易になります。ドキュメントをまとめて管理できるため、「どれが正しい文書か分からない」といった課題を解消できます。
👉 3分でわかる資料を見る
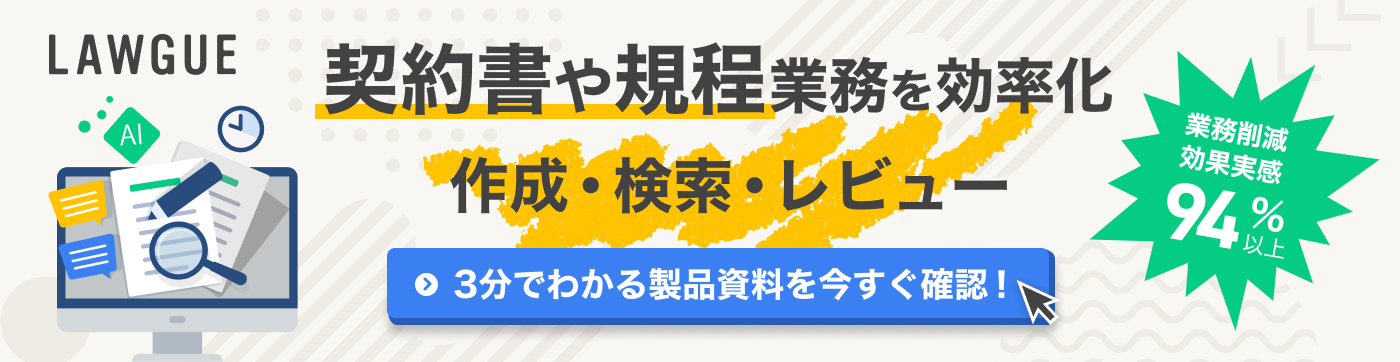
まとめ
文書管理業務は、単なる「整理整頓」にとどまらず、組織の情報資産を守り、業務効率や法的リスク対応力を高める重要な業務です。効果的な文書管理を行うことで、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)にもつながるでしょう。ぜひ、今日から見直し・改善に取り組んでみてください。
AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。








